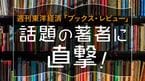「仏教・儒教・旧約思想」が同時期に生まれた理由
「資源・環境の限界」で考える「地球倫理」思想
このたび『人口減少社会のデザイン』を上梓した広井良典氏が、今回は、同じような資源・環境問題に直面していた紀元前5世紀頃の「枢軸時代/精神革命」を切り口に、人類史的な視点から「地球倫理」が企業行動や経営にもたらしている変化を論じる。
「枢軸時代/精神革命」をめぐる構造
前回、スウェーデンのグレタさんをめぐる動きを手がかりに、現在という時代が人類史の中での3度目の「拡大・成長から成熟・定常化」への移行期にあたること、またそこでは「地球倫理」とも呼ぶべき新たな思想や価値が求められていることを述べた。
ここで「地球倫理」の内容を考えていくにあたり、1つの手がかりとなるのは、紀元前5世紀頃の「枢軸時代/精神革命」をめぐる動きである。
なぜなら、1万年前に始まった農耕文明が、その発展に伴って人口や経済の規模が大きくなる中で資源・環境制約にぶつかり、「物質的生産の量的拡大から文化的・精神的発展へ」という方向に移行する際に生じたと考えられるのが紀元前5世紀頃の「枢軸時代/精神革命」であり、それは工業文明が資源的・環境的制約にぶつかっている現在の状況とよく似ているからだ。
そこでは、前回も少し述べたように、地球上のいくつかの場所で“同時多発的”に、現在につながるような普遍的な思想(ないし普遍宗教)が生まれた。
具体的には、ほぼ同時期に、ギリシャではいわゆるギリシャ哲学、インドでは仏教、中国では儒教や老荘思想、中東ではキリスト教やイスラム教の源流となった旧約思想(ユダヤ思想)がこの時代に生成したのである。