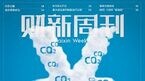日本人の「仏壇離れ」が招いた意外すぎる副作用
手土産を仏壇にすぐ置くのはマナー違反?
「嫁ぎ先の実家へ手土産を持参したら、仏壇へお供えされた……」、そんな発言に対して、ツイッター上でさまざまな意見が飛び交っていたのを目にしました。
祖父母や父母から「いただきものは、先に神棚や仏壇にお供えしてからいただく」と教えられた人もいれば、「持参する側としては、中身も確認せずいきなり仏壇にお供えというのはちょっと抵抗あり」という意見もあります。
確かに、仏壇にお供物をしたからといって、実際にご本尊やご先祖が食べるわけでもないし、水がないからといって喉が渇いたと訴えるわけでもありません。文化の違い、考え方の違いと言ってしまえばそれまでですが、いただいたものをそのまま仏壇へお供えするという行為、現代人はどのように捉えているのでしょうか。
急速に進む「日本人の仏壇離れ」
仏教では仏像を安置する場所を設けるために、さまざまな形式の「住まい」がつくられてきました。岩や土壌の一部をくりぬいたくぼみに仏像を納めるのもその1つ。屋内用としては仏像だけでなく仏画や舎利(遺骨)・経典などを安置する目的で厨子(ずし)といわれる小仏堂が考案されるようになります。
例えば法隆寺にある「玉虫厨子(たまむしのずし)」は、国宝に指定されている厨子ですが、これは推古天皇が仏像を安置するために愛用していたものだと知られています。
庶民の間に仏壇が普及するようになったのは江戸時代になってから。檀家制度の確立に伴い、仏像と位牌を一緒にお祀りするようになり、仏壇は先祖供養のシンボルとなりました。
これは松尾芭蕉の弟子である向井去来(むかいきょらい)が、玉棚(たまだな)を通じて、別の世にいる親への思いを読んだ句とされています。玉棚とは魂棚のことであり、お盆に先祖の霊を迎える精霊棚(盆棚)のことを指します。故人を慕い、懐かしむ気持ちを表出する場として、こうした精霊棚や仏壇が長年その役割の一端を担ってきたわけです。
最近は仏壇を置く家が少なくなったといわれています。2012年から2019年にかけて、いくつかの民間業者が仏壇保有率の調査をしていますが、「仏壇が家にある」という回答はいずれの調査結果でもおおむね40%という数値がでています。ちなみに、子供のころに「仏壇があった」という回答は66.2%(2012年第一生命経済研究所調査)でした。
市場規模も、仏壇を含む宗教用具の製造・卸は2003年の466億円から2017年には316億円(工業統計)と減少。小売りについても1994年の3669億円をピークに2016年は1794億円(商業統計)と大幅に減少していますから、数十年の間に仏壇離れは進んでいます。