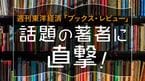魔法級!「1枚の紙」で仕事も家事もラクになる
デキる人は「箇条書きのリスト」を書いている
仕事で「やることリスト」を作っている人や、買い物に出かける前に「買い物リスト」を作ったことがある人は多いでしょう。何かメモをとるときに、意識せずとも「箇条書き」にしている人も多いはずです。
無意識に使われるので見過ごされがちですが、箇条書きのリストは、考え事をするときや、ものごとを整理したいときに、私たちが自然に選んでいる方法(ツール)です。
しかし、このありふれたツールをもっと意識的に、人生のあらゆる場所で利用することで、さらに多くのメリットを得ることができます。
仕事の進め方がラクになったり、家事や子育てのストレスが減ったり。誰にも教わっていないのに私たちがいつの間にか使っていて、仕事や家庭で驚くほどの力を発揮する「魔法」ともいえるものが、「箇条書きのリスト」なのです。
リストをつくるときの「ひと工夫」
リストを作るのは簡単です。難しく考える必要はありません。考え事や、記録したい内容を、行の先頭に記す点(バレットと呼ばれる)で区切りながら箇条書きにするだけで、立派なリストになります。
しかしいくつかの工夫をすることで、リストはより便利になります。その工夫の1つが、「字下げ」をすることによる、リストのアウトライン化です。
例えば「プレゼン資料をまとめる」というタスク(仕事)をリストにする際、
→ データの円グラフを作成する
→ 使用するイラスト素材を購入する
という具合に、タスクの詳細を、一段字下げした項目としてぶら下げてみましょう。たったこれだけで、仕事の「大まかな部分」と、「詳細な部分」を分離できます。
すると、あとからリストを見たときにも「そうか、プレゼン資料を作らなくてはいけないな。具体的にはどういう作業だったかな?」といったように、仕事の流れも、リストを書き出したときの思考の流れも、瞬時に思い出すことができます。