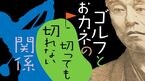日本人は「失われた30年」の本質をわかってない
原因と責任を突き止め変えねば低迷はまだ続く
今から30年前、1990年の東京証券取引所は1月4日の「大発会」からいきなり200円を超える下げを記録した。1989年12月29日の「大納会」でつけた史上最高値の3万8915円87銭から、一転して下げ始めた株式市場は、その後30年が経過した今も史上最高値を約4割ほど下回ったまま。長期的な視点に立てば、日本の株式市場は低迷を続けている。
その間、アメリカの代表的な株価指数である「S&P 500」は、過去30年で約800%上昇。353.40(1989年末)から3230.78(2019年末)へと、この30年間でざっと9.14倍に上昇した。かたや日本は1989年の最高値を30年間も超えることができずに推移している。
この違いはいったいどこにあるのか……。そしてその責任はどこにあるのか……。アメリカの経済紙であるウォールストリートジャーナルは、1月3日付の電子版で「日本の『失われた数十年』から学ぶ教訓」と題して、日本が構造改革を行わなかった結果だと指摘した。
日本は失われた40年を歩むことになるのか
この30年、確かに株価は上がらなかったが、極端に貧しくなったという実感も少ない。政治は一時的に政権を明け渡したものの、バブル崩壊の原因を作った自民党がいまだに日本の政治を牛耳っており、日本のあらゆる価値観やシステムの中に深く入り込んでいる。
バブルが崩壊した原因やその責任を問われぬまま、失われた30年が過ぎてきた。自民党政権がやってきたことを簡単に総括すると、景気が落ち込んだときには財政出動によって意図的に景気を引き上げてリスクを回避し、その反面で膨らむ一方の財政赤字を埋めるために消費税率を引き上げ、再び景気を悪化させる……。そんな政治の繰り返しだったと言っていい。
2012年からスタートしたアベノミクスでは、財政出動の代わりに中央銀行である日本銀行を使って、異次元の量的緩和という名目で、実際は「財政ファイナンス(中央銀行が政府発行の国債を直接買い上げる政策)」と同じような政策を展開してきた。政府に逆らえない中央銀行総裁が登場したのも、日本経済の「失われた20年、30年」と無縁ではないだろう。
実際に、近年の日本の国際競争力の低下は目に余るものがある。
生産能力は低下する一方であり、加えて少子高齢化が顕著になってきている。新しい価値観をなかなか受け入れない国民や企業が蔓延し、失われた30年が過ぎたいま、日本はこれから失われた40年、あるいは失われた50年を歩き始めているのかもしれない。