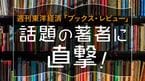コンサルばかり儲けさせる「国の補助金」の問題
バラマキになり下がった「事業承継補助金」
いまコンサルティング業界では、2つのバブルが起こっています。
1つは、大手コンサルティング会社の就職人気バブルです。人手不足で事業会社は軒並み採用で大苦戦するなか、大手コンサルティング会社が就活生の人気を集めています。
とくに東大などトップ校の学生には、外資系ファームがいちばん人気です。コンサルティング発祥のアメリカでは、起業家や投資銀行家と比べてコンサルタントは「かなり見劣りする職業」。優秀な学生が競ってコンサルタントになろうとするのは、日本特有のバブル現象と言えます。
もう1つは、中小コンサルティング会社や自営コンサルタントの事業承継バブルです。国が後継者難に直面する中小企業への支援を強化していることから、事業承継のコンサルティング案件が激増しています。今回は、世間であまり知られていない「事業承継バブル」の実態と問題点を紹介しましょう。
バブルの発端は中小企業庁の「雑な計算」
事業承継バブルのきっかけは、2017年9月に中小企業庁が公表した試算です。全国約400万社の中小企業のうち、今後10年で平均引退年齢の70歳を超える経営者は6割の245万人に達するが、半数の約127万人の後継者が決まっていない。今後、後継者不足から中小企業の廃業が進み、2025年頃までの約10年間で、全国で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性がある、というのです。
この試算を信じるなら、「これは国家的な危機だ。何としてでも事業承継を支援する必要がある」となりますが、本当にそうでしょうか。
GDPが22兆円失われ、失業者が650万人発生するというのは、「可能性」としているものの、ずいぶん雑な試算です。中小企業庁は、2025年までに経営者が70歳を超える法人の31%、個人事業者の65%が廃業すると仮定し、2009~2015年に廃業した中小企業が雇用していた従業員数の平均値(5.13人)と、2011年度の法人・個人事業主1社当たりの付加価値をそれぞれ利用し、試算しています。