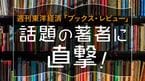日本はこの先もずっと経済成長を維持できるか
各機関の長期推計をベースに考えてみた
今後、日本では、労働力が減少する可能性が高いため、経済成長のためには、技術革新によって生産性を高めることができるかどうか、これによって1%台の成長率を維持できるかどうかが問題です。
OECDの予測である1%成長を実現できるか?
短期的な成長率は、さまざまな要因によって影響されます。例えば、貿易摩擦によって貿易額が減少すれば、経済成長率が落ち込みます。為替レートの変動によっても、大きな影響を受けます。
このような要因は見通しにくいことが多いので、短期経済予測は的中しないことがよくあります。
これに対して、長期的な成長率(潜在成長率)は、一定期間の平均成長率を問題とするので、上記のような変動は平均化されます。その意味では、短期予測より正確にできる面があります。
以下では、2020年から40年という長期にわたる、日本の経済成長率を問題にします。
「2060年、日本の1人当たりGDPは中印に勝てるか」(2020年1月5日配信)で触れたOECDの予測では、2060年までの日本の平均実質成長率は1.15%です。
これが妥当かどうかを検討することとしましょう。
まず、これまでの日本の実質GDP成長率の実績をみると、下図に示すとおりです。
(外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があるので、その際は東洋経済オンライン内でお読みください)
2000年代の中頃には年率2%台の成長が続きましたが、2008年のリーマンショックで成長率が大きく低下。その後、落ち込みを取り戻す動きなどがあり、2015年以降は1%台の実質成長率となっています。
2012~2018年の実質GDP年平均増加率は1.16%でした。