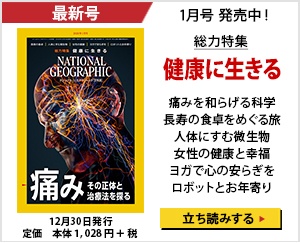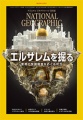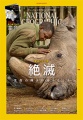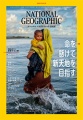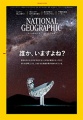激しい炎はときに強力な積乱雲を発生させ、気候に大きな影響を与える可能性があることが明らかとなった。 8月13日、ブラジルのフォス・ド・イグアスで開かれたアメリカ地球物理学連合の会合での発表によると、炎によって発生する積乱雲は、火山噴火と同じように煙や微粒子を成層圏まで噴き上げるという。通常の雷雲より高層で形成されるため、温暖化や寒冷化など、地球の気候に予期せぬ影響をもたらす可能性がある。
火災による雲の存在は気候モデル上の単なるシミュレーションではない。ロシアで先日発生した大規模森林火災が産んだ前代未聞の積乱雲を、ワシントンD.C.にある米国海軍研究所(NRL)の気象学者マイケル・フロム氏が衛星画像で確認している。
これまで火山噴火による火山灰雲と混同されていたが、フロム氏のチームは1979年までさかのぼる衛星画像を調査し、樹木全体に火が回る激しい森林火災「樹冠火災」と関連付けた。樹冠火災は、火が木の幹までいかず、樹冠から樹冠へと広がっていく森林火災で、そのようなとき積乱雲は発生する。
樹冠火災による煙と熱で発生した積乱雲は、通常の積乱雲に比べ高密度で規模が大きく、高層にまで発達する。
このタイプの積乱雲は火災による煙とエアロゾル粒子をまるで“煙突”のように集め、高度17キロの成層圏まで噴き上げる。その後、物質は積乱雲の外に出て、広範囲に撒き散らされていくのである。
「火災による積乱雲は1つだけでも地球の半球に影響を及ぼす可能性があり、広がった煙や物質は数カ月にわたって残存し続ける」と前出のフロム氏は米ナショナルジオグラフィック ニュースに語った。
炎で発生するこの種の雲が異質な理由は他にもある。例えば、危険な雷や竜巻の発生原因になる一方で、雨を降らせることはほとんどない。これについてフロム氏は、「煙に含まれる微粒子を大量に吸収するためだ」と説明する。
「煙の微粒子が水分子の結合を妨げるため、雨や雪などの生成プロセス(降水過程)が妨害されることになる」。また、通常の雷雲のように移動せず、火災現場の上空に留まる性質もあるという。
今回の研究は科学者たちに、コンピューターの気候モデルを修正し、“火災積乱雲”がもたらす影響を考慮に入れる必要性を突き付けた。
「成層圏のエアロゾル粒子の層は火山噴火によって形成されるケースが多いと考えられていたが、実際にはその多くが、この種の雲が噴き上げる煙によるものだとわかった。大気中のエアロゾル粒子についてのこれまでのデータを再調査する必要があるだろう」とフロム氏は語る。再調査によって、火災による積乱雲形成のプロセスやタイミングなどを解明する手掛かりとなるだろう。
アメリカ地球物理学連合の会合でフロム氏は、「この雲が撒き散らす煙の幕は太陽からの放射エネルギーを吸収し、気温上昇や天候の変化をもたらす可能性もあるため、気候学的に重要な研究対象だ」と述べている。
「逆に大気を極度に冷やしてしまう危険性もある。いずれにせよ影響は無視できない。また、積乱雲による直接的な影響の研究も欠かせない。なぜなら局所的に甚大な被害をもたらすほど強力なのだ」。
Video grab by Ross Andreson, Elko Daily Free Press/AP
火災による雲の存在は気候モデル上の単なるシミュレーションではない。ロシアで先日発生した大規模森林火災が産んだ前代未聞の積乱雲を、ワシントンD.C.にある米国海軍研究所(NRL)の気象学者マイケル・フロム氏が衛星画像で確認している。
これまで火山噴火による火山灰雲と混同されていたが、フロム氏のチームは1979年までさかのぼる衛星画像を調査し、樹木全体に火が回る激しい森林火災「樹冠火災」と関連付けた。樹冠火災は、火が木の幹までいかず、樹冠から樹冠へと広がっていく森林火災で、そのようなとき積乱雲は発生する。
樹冠火災による煙と熱で発生した積乱雲は、通常の積乱雲に比べ高密度で規模が大きく、高層にまで発達する。
このタイプの積乱雲は火災による煙とエアロゾル粒子をまるで“煙突”のように集め、高度17キロの成層圏まで噴き上げる。その後、物質は積乱雲の外に出て、広範囲に撒き散らされていくのである。
「火災による積乱雲は1つだけでも地球の半球に影響を及ぼす可能性があり、広がった煙や物質は数カ月にわたって残存し続ける」と前出のフロム氏は米ナショナルジオグラフィック ニュースに語った。
炎で発生するこの種の雲が異質な理由は他にもある。例えば、危険な雷や竜巻の発生原因になる一方で、雨を降らせることはほとんどない。これについてフロム氏は、「煙に含まれる微粒子を大量に吸収するためだ」と説明する。
「煙の微粒子が水分子の結合を妨げるため、雨や雪などの生成プロセス(降水過程)が妨害されることになる」。また、通常の雷雲のように移動せず、火災現場の上空に留まる性質もあるという。
今回の研究は科学者たちに、コンピューターの気候モデルを修正し、“火災積乱雲”がもたらす影響を考慮に入れる必要性を突き付けた。
「成層圏のエアロゾル粒子の層は火山噴火によって形成されるケースが多いと考えられていたが、実際にはその多くが、この種の雲が噴き上げる煙によるものだとわかった。大気中のエアロゾル粒子についてのこれまでのデータを再調査する必要があるだろう」とフロム氏は語る。再調査によって、火災による積乱雲形成のプロセスやタイミングなどを解明する手掛かりとなるだろう。
アメリカ地球物理学連合の会合でフロム氏は、「この雲が撒き散らす煙の幕は太陽からの放射エネルギーを吸収し、気温上昇や天候の変化をもたらす可能性もあるため、気候学的に重要な研究対象だ」と述べている。
「逆に大気を極度に冷やしてしまう危険性もある。いずれにせよ影響は無視できない。また、積乱雲による直接的な影響の研究も欠かせない。なぜなら局所的に甚大な被害をもたらすほど強力なのだ」。
Video grab by Ross Andreson, Elko Daily Free Press/AP