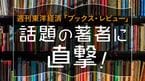男の子は「鶏口より牛後になるべき」深い理由
名物校長が語る「自己肯定感の高め方」
スポーツを本気でやってきた人というのは、「負ける経験」をたくさん積んでいます。そしてその中で、悔しい思いに耐えながら、勝つための方法、レギュラーになるための方法を必死で考え、実践し続けます。この経験が、社会人になったときにも、生かされるのです。負けても、負けても、そこから這い上がる力があることが、就職で評価されているのです。
負けるために、上へ上へとチャレンジしよう
逆説的に響くかもしれませんが、「負ける」という経験をするためにも、勉強においても、スポーツにおいても、上へ上へとチャレンジさせてください。そうすれば、必ず負ける経験にぶち当たります。
例えば開成への合格は、一見「成功体験」に見えるかもしれませんが、そうではありません。開成には小学校時代トップクラスの子が集まるわけですが、5月の末にある中間試験で、「成績上位だ」と思える子というのは、ほんの一握り。残りの大多数の子は「なんで俺がこんな順位になるんだ?」と、自分が初めて経験する成績にびっくりするわけです。
ここで子どものころから持っていた「成績がいい」というところを拠り所にした自己肯定感が崩れ去ることになります。ですから生徒たちは、勉強以外で自分の自己肯定感を支えてくれるものを、学校生活の中で見つけていかなければならないのです。
そういった意味で、中学受験や高校受験は、上を目指してチャレンジすることで、合格しても、不合格であっても、子どもにとってプラスの財産になる「負ける経験」をすることができます。親が安全策ばかり立てていると、子どもは失敗しないまま人生を進み、初めて失敗したときには、立ち直れないほどのダメージを受けてしまうかもしれません。
スタートは「牛後」でいいのです。そんな自分を見つめることも、そこからトップになるように奮起することも、男の子の生きる力を育むうえで、大きなプラスになるからです。
(構成:黒坂真由子)