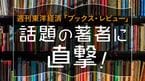なぜ社会の底辺にいる人々は「見えない」のか
「7つの階級」調査が示す「貧困ポルノ」の誤り
見えない人々
社会階層の最底辺に位置するプレカリアート階級は、経済資本、文化資本、社会関係資本のいずれも、その蓄積が非常に少ない階級である。
年収は数千ポンドで貯蓄や資産も極めて少ない。英国階級調査への参加率は極端に低く、この階級は人口の約15%を占めるにもかかわらず、階級調査でプレカリアートと算出されたのは参加者全体の1%に満たなかった。
英国階級調査では、プレカリアートは「行方不明の人たち」である。階級調査に興味を持ち積極的に参加したのは教育レベルの高いエリート層で、プレカリアートはそうではなかった。
これは驚くことではない。文化資本を多く所有する人たちは、自分の文化的知識と自信を示すために英国階級調査を利用していたからだ。プレカリアートは底辺に位置づけられるため、社会の最下層であることの科学的おすみつきを喜ぶ人はいないから、参加率が低いのだと予測された。
現代の階級間の関係を明らかにするためには、この姿が見えない人々の実像を知らなければならない。
エリートは人々の関心の的で、メディアの報道や社会的研究の中心にあるが、プレカリアートの存在は視野から消え、今日の社会的不平等と階級格差の実態をわかりにくくしている。