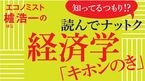「ココイチ」FC加盟店が失敗しづらいカラクリ
「10店のうち1店しか潰れない」秘策の正体
飲食店の生存競争は厳しい。ある調査によると、「開店後2年以内に廃業する」飲食店は、約半数にも達するという。そんな状況の中でも、出店すれば「10店に1店しか潰れない」という「驚異の生存率」を示しているのが「カレーハウスCoCo壱番屋」だ(以下、CoCo壱番屋)。
CoCo壱番屋は、国内で直営店159店、フランチャイズ1108店の合計1267店を展開し、海外店を含めると、全世界で1439店舗(同)に達する。店舗数の増大と歩調を合わせるかのように、メニューも充実。
「手仕込とん勝つカレー」「手仕込ささみカツカレー」はいずれも登場から3カ月で200万食以上を売り上げた。さらにスパイスカレーシリーズも9カ月で約260万食のヒットもあって、業績も堅調に推移。
世界最大のカレーチェーン
CoCo壱番屋を運営する壱番屋の2019年2月期の決算では、売上高が502億1400万円、営業利益が44億4200万円で、営業利益率は約8.8%。ここ10年間の営業利益率は平均で10.2%と、外食産業としては高い水準をキープしている。
ある食品メーカーの調査では、日本人1人につき「年間73杯」もカレーを食べている。単純に計算すると「5日に1杯」。会社員なら、月曜日から金曜日までのランチで「1回はカレー」ということになる。今や日本の国民食ともいえるカレーで、国内最大のチェーン、いやギネス認定の世界最大のカレーチェーンを展開しているのが壱番屋である。