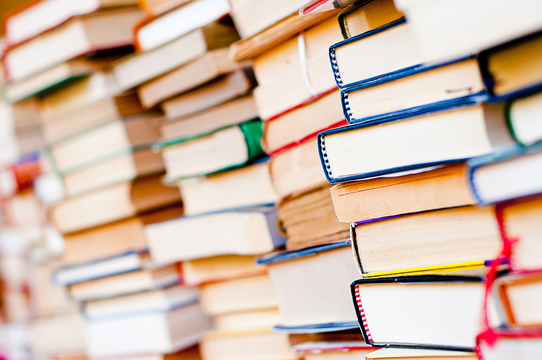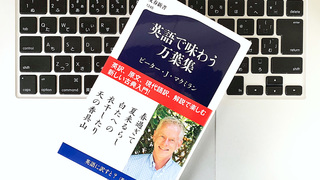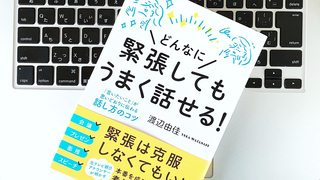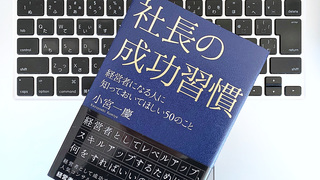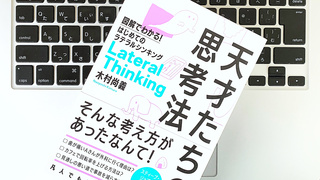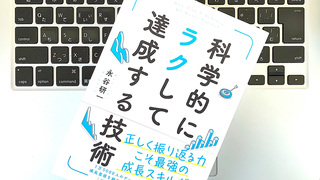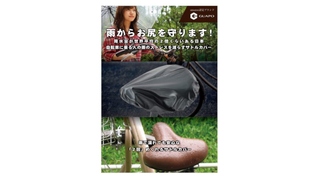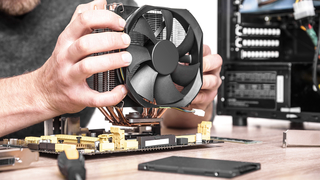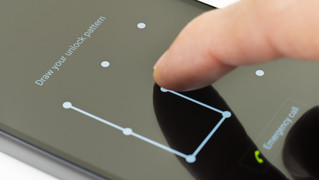「令和」という元号が日本の古典の詩歌から取られたことに、私は大きな喜びを感じた。日本の古典文学の翻訳の仕事を続けていくうえで、大きなエネルギーをもらえたように思えたのだ。
「令和」の由来となった『万葉集』は、新しい時代を象徴する歌集となった。日本最古の文学作品のひとつだが、これから私たちが進んでいく未来についても多くの示唆を与えてくれる。(「はじめに」より)
『英語で味わう万葉集』(ピーター・J・マクミラン 著、文春新書)の著者は、本書の冒頭にこう記しています。
アイルランド出身の学者、翻訳家。20年以上にわたって日本に住み続け、『百人一首』を英訳するなど数々の功績をお持ちです。
最新刊である本書は、タイトルからわかるとおり、日本文学の原点である『万葉集』から選りすぐった百首を英訳した画期的な一冊。
オリジナルの歌とその英訳、現代語訳、解説を見開き2ページで確認できる構成になっています。
一例をピックアップしてみましょう。
東の 野にかぎろひの
(軽皇子(かるのみこ)、安騎(あき)の野に宿る時に、柿本朝臣人麻呂が作る歌)
東(ひむがし)の野にかぎろひの立つ見えて かへり見すれば月傾(かたぶ)きぬ
巻1・48
[現代語訳] (軽皇子が安騎野に宿られた時に、柿本朝臣人麻呂が作った歌) 東の野に曙の光が差しそめるのが見えて、振り返って見ると残月が西の空に傾いている。
柿本人麻呂 かきのもとひとまろ
When I look east—
the light of daybreak
spilling out over the plain.
When I look back—
the moon crossing to the west.
(28~29ページより)
冬の凛とした朝、東に陽光が差しそめる。ぐるりと振り返れば、西に名残の月が傾いていく。
朝と夜が交わる瞬間を見事に切り取っているこの歌は、『万葉集』でも屈指の名歌として有名。
蕪村の名句「菜の花や月は東に日は西に」とも似た視点を持っているものの、人麻呂歌の格調高さにはおよばないと、著者はこれを高く評価しています。
たとえばこのように、『万葉集』に収録されている詩歌をわかりやすく解説しているわけです。
万葉人の生き方を垣間見る
『万葉集』には男女の愛から、家族愛、日常の暮らし、自然との結びつきまで、多種多様なテーマの歌が納められています。
たとえば愛の歌をとってみても、「百歳(ももとせ)に 老い舌出て よよむとも 我(あれ)は厭はじ 恋は増すとも」(あなたが100歳の老女になって、老い舌が出て腰が曲がろうとも、私は決して嫌がったりしないでしょう。恋しさが増すことはあっても)のように、老境に至っても変わらない愛を詠んだ歌がる一方、「相思はぬ 人を思ふは 大寺の 餓鬼の後(しりへ)に 額つくごとし」(私を思ってくれない人を思うのは、大寺の餓鬼に、それも後ろから額づいて拝むようなものです)と報われぬ恋をユーモラスに詠んだ歌も。
またユーモアという点で著者が評価しているのは、大伴旅人のこの歌。
「なかなかに ひととあらずは 酒壺(さかつぼ)に なりにてしかも 酒に染みなむ」(なまじ人としてあるよりは、いっそ酒壺になってしまいたい。そうしたらずっと酒に浸っていられるだろう)(239ページより)
この歌のことを著者は、「滑稽であると同時に、人生への深い省察も込められている」と評しています。
いずれにしても、シンプルで感情を直載的に歌ったものから、とても複雑な表現方法を用いたものまで多様でユニーク。
そこに、古代日本人の心性が表れているということです。(238ページより)
著者は本書の脱稿直前に、南半球のある国の駐日大使から、日本の文学は世界的にはあまり知られていないと指摘されたのだそうです。
「もし日本の文学が素晴らしいものであるなら、なぜもっと注目を集めていないのでしょうか?」と。
この方はいささか極端すぎるのではないかとも思いたくなりますが、少なくとも『万葉集』について、著者は次のように見解を述べています。
『万葉集』の世界的な知名度が低いのは、優れた訳詩がこれまで少なかったからだろうと私は考えている。
私は、この翻訳が『万葉集』のイメージを提示する第一歩となることを望んでいる。
そして『万葉集』が、日本の文学史における宝物というだけでなく、世界的にも重要な文学作品として認知されるようになることを願っている。(「はじめに」より)
しかし現実問題として、日本人の多くもまた、『万葉集』の素晴らしさを理解しているとは言い切れないのではないでしょうか。
海外の方からの認知度の低さを嘆く以前に、私たちがその魅力を知っておくべきだと考えることもできるわけです。
そんななか、本書は『万葉集』を知るために最適なテキストとなってくれるはず。この年末に、ゆっくりとページをめくってみたいものです。
あわせて読みたい
Photo: 印南敦史
Source: 文春新書
印南敦史
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5