内蔵GPUの性能について、ざっくり解説しています。内蔵GPUそのものについては、事前にある程度知っている事を前提としていますので、ご了承ください。
GPUとは?
PCには、演算処理を行うためのプロセッサが搭載されています。このプロセッサは基本的に、特に有名な中央処理装置のCPUに加え、画像処理に特化したGPUと呼ばれる2つが搭載されています。
GPUという言葉はPC初級者の方には馴染みがないかもしれませんが、GPUはPCを使用する上で実質必須のものであり、現在お使いのPCにも必ずGPUが搭載されているはずです。なぜなら、GPUが無いと映像をディスプレイ等の画面に出力できないからです。
このGPUは、大きく分けて「CPUの内蔵GPU(iGPU)」と「単体のGPU(グラフィックボード・ビデオカード)」の2種類があります。本記事で主に取り扱うのは、CPUの内蔵GPU(iGPU)になります。
内蔵GPU:とりあえず使える用
内蔵GPUをざっくり説明すると、高いグラフィック性能を求めない人が、無駄な出費やグラボ用意の手間を掛けないための、とりあえず用として存在するものです。とりあえず用なので、基本的に単体のGPUより性能は著しく低いです。その代わり、設置スペースが必要なく、消費電力も非常に少ないです。詳しくは後述します。
逆に、単体のGPUというのは、グラボ(グラフィックボードの略)とよく呼ばれるPCパーツに搭載されているものです。内蔵GPUとは違い、他パーツとは分離された一つのパーツとして存在しており、内蔵GPUよりも遥かに性能が高いです。3Dのゲームなどをしたいなら、単体のGPUがほぼ必須となります。
ただし、基本的にグラボは高価な上、消費電力や発熱も多く設置スペースも必要となります。高いグラフィック性能を求めない人にとっては、費用が高くなるだけの無用の長物となり兼ねません。そこで、そんな人のためにあるのが内蔵GPUという訳です。
AMDというCPUメーカーのCPUの中には、「APU」と呼ばれるCPUとGPUを統合したプロセッサがあります。詳しくはここでは触れませんが、基本的に通常の内蔵GPUよりもやや高性能です。
グラボとの性能比較
少し具体的に、CPUの内蔵GPUと、いわゆる単体のGPU(グラボ)との性能の差を見ていきます。性能比較表をざっとまとめてみたのでそちらを見ていきましょう。2019年7月時点での新しめの主要GPUを載せています。
| GPU | 3DMarkスコア | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2080 | 27620 | 単体 | ハイエンドGPU |
| GeForce RTX 2070 | 23373 | ハイエンドGPU | |
| GeForce RTX 2060 | 19338 | ハイエンド下位ぐらい | |
| GeForce GTX 1660 Ti | 16024 | ミドルレンジGPU。1060の後継として期待 | |
| GeForce GTX 1060 | 12816 | 2016年中頃~2019年にかけて流行したミドルレンジGPU | |
| 大体のゲームをそれなりに動かせるライン(3DMark 10000程度) | |||
| Radeon RX Vega 11 | 3494 | 内蔵 | Ryzen APUに搭載。一般的な内蔵GPUではトップクラス。 |
| Radeon RX Vega 8 | 2209 | Ryzen APUに搭載。デスクトップ版もある。 | |
| Radeon RX Vega 6 | 2064 | Ryzen APUに搭載。デスクトップ版もある。 | |
| Intel UHD Graphics 630 | 1268 | Intel 第8,9世代CPU(デスクトップ用)に搭載。 | |
| Intel UHD Graphics 620 | 1121 | Intel 第8世代CPU(モバイル用)等に搭載 | |
| Intel HD Graphics 630 | 1067 | Intel 第7世代CPU(デスクトップ用)に搭載。 | |
内蔵GPUの性能は低い
上記の表を見れば一目でわかるかと思いますが、単体のGPUと比較すると、内蔵GPUの性能は圧倒的に低いです。内蔵GPUは、特に性能の優れたものでも、ミドルレンジと呼ばれる中性能帯の単体GPU(グラボ)にすら圧倒的に劣っています。とはいえ、これは元々「内蔵GPU」がPC全体としてのコスト削減を代表的な目的とする「とりあえず用」という位置付けなので仕方はありません。
具体的にどれぐらい性能が低いのか?
一般ユーザーが高性能GPUに求める事は「ゲームを快適にプレイできる」ことです。これを例にして実際の使用感について言及します。
表にも記載した、「GeForce GTX 1060」は、2016年中頃から2019年という長期間に渡って流行した高コスパミドルレンジGPUです。このGTX 1060 であれば、最新の3Dのゲームでも、ほぼ全てのタイトルで60FPS以上は簡単に出す事ができます(設定調整が必要な場合はあるけど)。
要するに、単体GPUならミドルレンジの性能でもぼ全てのゲームをそれなりに快適にプレイできますが、内蔵GPUは、トップクラスの性能のものでも最新の3Dゲームの快適なプレイは「現状不可能」と言って過言ではありません。解像度と、他の全ての設定を「最低」にすれば、動きはするかもしれませんが、FPS(紙芝居の枚数のようなもの)は非常に低く、快適なプレイとは到底言えないかと思います。もっといえば、局所的な高負荷に耐え切れず「ゲームの強制停止(フリーズ)」や「処理落ち」が多発する事は目に見えており、快適どころか、プレイ出来ているとも言えないレベルになるはずです。
元々内蔵GPUは高性能を目指したものではない
記事冒頭でも軽く触れましたが、元々「内蔵GPU」はとりあえず用として使えれば良いという事で登場しました。別途グラフィックボードを用意する費用を削減することを代表的な目的として登場したのです。目的が高性能を目指すためではないので、性能が低いのは仕方のないことです。
とはいえ、現在ではあらゆる端末の小型化が進んでいる上、PCゲームの流行の背景もあり、内蔵GPUの高性能化は非常に注目されています。スマホのグラフィック性能にも関係あるというのも大きいです。
なぜ性能が低い?
内蔵GPUの性能が低い要因、要するに単体GPUと違う点について、ざっくりまとめています。
内蔵GPUの性能が低い主な要因
- 使用メモリーはメインメモリーと共有で、専用のVRAMを持たない
- 利用できるスペースが狭い
専用のVRAMを持たない
VRAMというのはGPU専用のメモリーのことです。グラボ(単体のGPU)ではこのVRAMが搭載されており、それを利用しています。
それに対し、内蔵GPUが利用するのは、CPUと共通のメインメモリーです。メインメモリーの一部を借りるような形での利用となっています。メインメモリーは元々CPUのためのメモリーなので、内蔵GPUに割り当てられるメモリー容量は少ないです。また、メインメモリーは、VRAMよりも基本的に転送速度が遅いです。
要するに、内蔵GPUは「メモリー」において、「容量」「速度」という重要な2点どちらも、単体のGPUより劣っているという訳です。
利用できるスペースが狭い
当然ですが、内蔵GPUは、利用できるスペースが非常に狭いです。利用できるスペースが狭いと、当然プロセッサ自体も小さいものしか使えないので性能は低くなります。また、問題はそれだけではありません。発熱の問題があります。
CPUやGPUといった演算処理装置は、その小さなチップの中で膨大な量のデータ処理を行います。そのため、高負荷時には多量の発熱を伴います。冷却にもそれなりの設備が必要です。
もし内蔵GPUの処理能力が劇的に向上したとしたら、発熱も当然多くなります。CPU自体も発熱が多いのに、密着したような位置関係のGPUの発熱も激増してしまうと、CPU用のファン一つで対応することが難しくなってしまいます。グラボ(単体のGPU)では、それだけで冷却用のファンが1基~3基搭載されているのが一般的です。CPU用のファン一つでは到底対応できないのは目に見えています。
内蔵GPUが単体GPUの性能に追い付くのは、かなり厳しいと言わざる得ません。
まとめ
最後に、要点だけを箇条書きでまとめています。
- 内蔵GPUの性能は、単体のGPU(グラボ)に比べて圧倒的に低い
- 現状では、最新の3Dゲーム等を快適にプレイする事は不可能
記事はここまでになります。ご覧いただきありがとうございました。
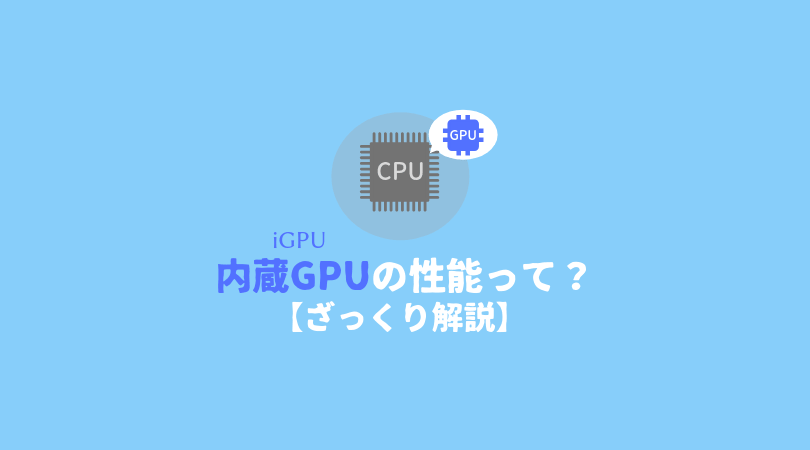


コメントを残す