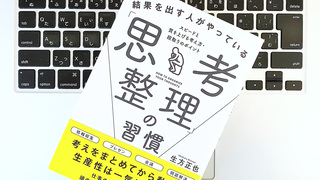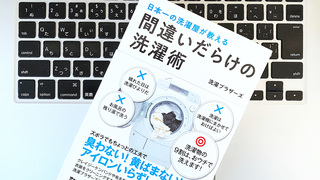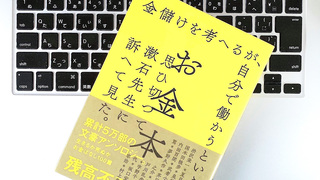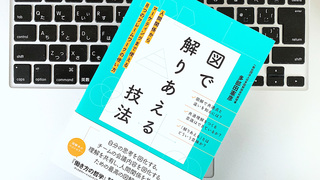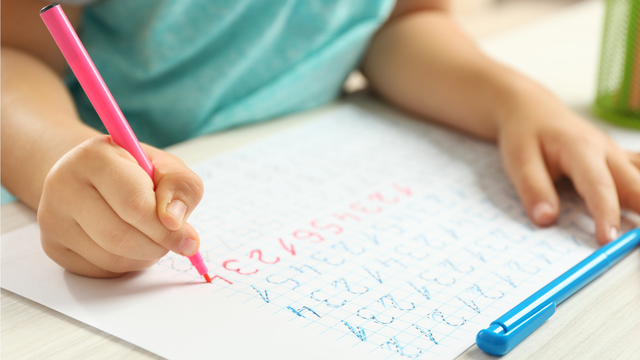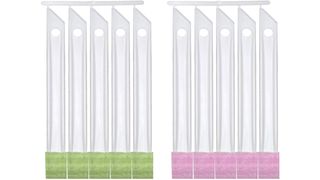さまざまな仕事を生産的にこなすためには、まず頭のなかを整理し、実行に向けた設計図をつくっておくことが大切。
『結果を出す人がやっている「思考整理」の習慣』(生方正也 著、日本実業出版社)の著者は、このように主張しています。
行き当たりばったりの仕事をしていたのでは、結局クオリティも上がらずスピード感にも欠けてしまうことになります。
しかし、「どう進めたらいいか」を考えたうえで実行すれば、仕事を生産的にこなすことができるということです。
とはいえ、「頭のなかの整理法」が多数存在するなか、「どれが自分に最善なのか」を見極めるのは簡単なことではありません。
しかも絶対的な答えはないだけに、「自分に合っているか」「直面している仕事の課題に合っているか」によって選択することが重要であるわけです。
自分に合った仕事の考え方や進め方をするのは、とても大事なことです。適応しようと思っても、自分に合わない考え方・進め方は存在するからです。
そこで無理をする必要はありません。なんといっても、考え方や仕事の進め方の手段はたくさんあるのですから。(「はじめに」より)
そこで本書では、「仕事上のさまざまな場面において、考えや仕事の手順を整理したうえで進めると、結果がどう変わるのか」について解説しているわけです。
きょうはそのなかから、「答え」を求められているときの思考法についての記述に注目してみたいと思います。
「答え」を求められているとき
○ 質を高められる答えを探す
× 間違っていない答えでまとめる
(10ページより)
ビジネスシーンにおいては、どんな立場の人であっても常に判断が求められることになります。
企業のトップなど限られた人だけでなく、上司や先輩の指示どおりに動くことが求められる新入社員にも、「どの仕事から取り組もうか」「お客様からの問い合わせに自分が答えていいか」など、判断を迫られる機会は必ずあるわけです。
つまり「仕事を進める」ということは、いろいろな場面で答えを出して行動することでもあるわけです。
しかしそんなときには、「これで合っているかな…」と不安に感じたりもするものでもあるでしょう。
ただし学校と違い、ビジネスシーンにおいては、「合っているか間違っているか」で判断されることはあまり多くないと著者は指摘しています。
むしろ仕事のレベルが上がるほど、「それで合っているか」で評価できない場面が訪れるものだというのです。
その例として、ここではお客様に自社の商品を提案するシーンが取り上げられています。
自分の提案が首尾よく通ったとしても、それは「正解」を出したということではありません。
また、提案が通らなかったからといって、その提案が「間違い」だったということでもないはずです。
事実、提案が通らなかった理由を探ってみると、「競合の提案のほうが魅力的だった」「提案内容自体は悪くないけど、すでに別の商品での検討が進んでしまっていた」など、“必ずしも間違ってはいないが、結果として通らない”というケースが大半だったりもします。
逆に提案が採用された理由も、「絶対にこれがよかった」というより、他と比較して“相対的によかった”ということが大半。
だとすれば、「答えがあっているか」という観点で自分の仕事を評価するのは危険だということになるでしょう。(10ページより)
目指すべきは「質の高い」答え
では、どんな観点によって自分の仕事を評価すればいいのでしょうか。そのことについて本書では、「質の高い答えを出していたかどうか」が重要なのだと説かれています。
実は、仕事の評価はほとんどがこの観点で見ることができます。
先ほどの提案の例でも、「競合よりも魅力的な提案となっていたか」「顧客の期待を超える提案となっていたか」などがカギとなるのです。(12ページより)
そういわれると、「無理に正解を追求しなくていいなら気が楽だ」と思われるかもしれません。
ところがまったく逆で、むしろ「これは大変なことになった」と考えたほうがいいとすら著者はいいます。
その理由はいたってシンプルです。正解は決められたゴールがあるため、そこに到達すればいいだけのこと。
しかし質の高さを求められるとなると、天井がないということになるわけです。
つまり「提案が採用されたからOK」という発想ではなく、常に「より質の高い答えはないだろうか」ということを追求し続けなければならなくなるということ。
そしてポイントは、この「終わりなき旅」をいかに続けられるかということ。それが結果的には、深く考えることにつながっていくからです。
場合によっては、自信のある答えを再度見なおし、ゼロからつくりなおさなければならない場面も出てくることになるはず。
そんなときは、「いまのままでも十分なのに、どうしてやりなおさなければならないのか」と感じることもあるでしょう。
しかし、そこを乗り越えると、より一層「質の高い答え」に到達できるというわけです。(12ページより)
「間違っていない」で自分に限界をつくらない
正解を求める姿勢は、往々にして「間違っていないからいいか」という姿勢につながっていくものでもあります。
しかしそうすると、結果的には安易な答えで止まってしまうことになりかねません。だからこそ、「質の高い答え」を求め続けるべきだと著者は訴えるのです。
ただし、こうした考え方は、決して「ビジネスで間違いはない」という意味ではないそうです。
先のお客様への提案の例でいえば、「大事なところでデータの取り違えがあった」「違うお客様向けの提案をしてしまった」などは間違いになりますし、そのような提案書は一発でアウト。
とはいっても初心者ならともかく、ある程度の経験を積んだ人であれば、そうした間違いをしてしまうことは滅多にないはず。
いわばそれをクリアできるのは当然の話であり、クリアできたからといって自慢できるものではないということを忘れるべきではないとも著者は記しています。(13ページより)
たとえばこのように、各項目について、まずは適切な姿勢とどうでないものを○×で区分。そしてそのうえで、根拠をわかりやすく解説した内容になっています。
そのため、自分に合った仕事の考え方や進め方を身につけるためにはとても有効。ぜひ、本書を存分に活用したいものです。
あわせて読みたい
Photo: 印南敦史
Source: 日本実業出版社
印南敦史
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5