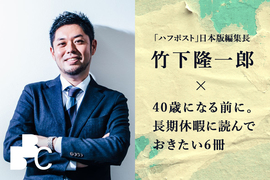「本なんて売れないよ」
そんな周囲からの指摘を浴びながらも、あえてネットメディアである「ハフポスト」が出版社と手を組み、『ハフポストブックス』を創刊したのが今年の春。
本を読む人口そのものが減っているともいわれる時代に、なぜ“紙の本”にこだわったのかと業界内外で話題となりました。
スピード重視のインターネットがスタンダードとなり、大きな曲がり角を迎えた今、「遅いメディア」の代表格である本が担いうる役割とは――。
さまざまなジャンルの第一線で活躍している方に、テーマに基づいてご自身の人生において影響を受けた本をご紹介いただき、それらの本をタイトルも著者の名前も明かさずにお届けする「BLIND BOOK CLUB」。
今回はその答えを「ハフポスト」日本版編集長・竹下隆一郎さんの記述や著書に求めるとともに、選書に定評がある竹下さんに長期休暇に読むべきおすすめの本6冊を挙げていただきました。
ネットメディアがあえて本を出版する理由
「会話を大切にするメディア」を指針にするハフポスト。竹下さんが編集長として目標に掲げているのは、この国の“会話の総量”を増やすことだそうです。
会話は「議論」や「対話」とは違って、良い意味で「話し手を縛るゴールがないものである」と竹下さん。
そして「本」こそが、会話を増やすための“最適なツール”であると語っています。
その理由のひとつとして挙げられるのは、SNSの普及により、読書が「ひとりで静かにふけるもの」から「みんなで話し合う体験」に変わってきているから。
たしかに以前に比べると、読書の経過をSNSでつぶやいたりSNS経由の読書イベントに参加したりして、作品への思いを人と共有できる場が増えていることを実感します。
ハフポストブックスでは、みんなで話し合う体験を提供するために、著者の講演会や書店でのトークショーをはじめ、歌舞伎町のホストクラブで読書会を開くといった試みにも挑戦。
ネットで伝えられることはハフポストで、テーマが複雑なものや長い文章でこそ伝わるメッセージはハフポストブックスで、発信の場を使い分けています。
若い世代こそ見直したい「本」の価値観
ハフポストブックスから出版された本は6冊。その中の1冊に竹下さんの著書『内向的な人のための スタンフォード流 ピンポイント人脈術』があります。
この中で竹下さんは、名刺とSNSを駆使しながら人脈づくりにいそしむ人を「人脈モンスター」と呼び、むしろ彼らよりも内向的な人のほうがビジネスはうまくいく時代だ、と説いています。
人づきあいが苦手でもいい。得体の知れない「人脈」とやらを追いかけるよりも、自分の内面とじっくり向き合い、限られた人と熱量のある“深い関係”を築いていくほうが豊かだということを、誰もが本当は感じているのかもしれません。
インターネット然り、人との関係にしても然り。いともたやすくつながれてしまう時代だからこそ、あらためて見直したい価値観。
まずはインターネットやSNSに慣れ親しむ若い世代こそ、あえてアナログで遅いメディアである「本」の価値を再認識してみるのはどうでしょうか。
読書本来の楽しみを味わう
欲しいと思った本はワンクリックで入手できる時代。その時々に求めている本を手に入れるための道筋はすでに最適化されているといっていいでしょう。
その一方で、購入履歴によるリコメンドからは自分がその時々に求めている(いた)ものにしかリーチできないのは、よくも悪くも「インターネット的」だと言えます。
本屋で装丁に惹かれたハードカバーをジャケ買いしたり、本を求めて書店を訪れて、ふと目に留まった本が妙に気にかかってレジに持っていったりするような。いつもは通らない道でたまたま心を動かされるような光景を目にしたり、どこか心躍る“寄り道”的体験、いわゆる「セレンディピティ」は失われつつあるように思います。
そんな中で、各界で活躍する人の視点を借りて、未知なる本に出会うために始まったのが「BLIND BOOK CLUB」。
本のタイトルも著者も明かさず、紹介するのは選書理由だけ。リコメンドでは届かない「本との偶然の出会い」をオンラインで演出するのが狙いです。
普段、自分では手にしないような思いがけないセレクトが、“会話の総量を増やす”ためのツールとなってくれるはずです。
今回、竹下さんの選書テーマは「40歳になる前に。長期休暇に読んでおきたい6冊」。以下、竹下さんが寄せてくれたメッセージです。
今年秋、私は40歳になる。ひと昔前の感覚だと“いい中年”となるような年齢だが、「人生100年時代」を考えると、あと60年ある。死ぬまで、多くの時間がある。その間には、人工知能がますます発達し、仕事や生活のあり方は一変するだろう。
では、どうしたらいいのか。世界はどう変わるのか。自分は仕事を続けられるのだろうか。不安ばかりが募る。
こういうとき、頼れるのは本だ。学者、経営者、作家、ジャーナリスト。書いた人たちが、人生をかけて身につけたノウハウがつまっている。それを2~3時間で習得できるお得なツールだ。
これから毎年のように出てくるであろう、流行のビジネス書を読むのも良いが、どうせなら一生使える知識や考え方を習得したい。私は長期的スパンで物事を考えるとき、二つのことを大切にしている。
①今がどんな時代なのかを把握すること
②自分のことを表現して、人を動かすことができる国語力を身につけること
このふたつの視点で選んだ6冊である。
竹下さんが若い世代に贈る「セレンディピティ」。40歳までの課題図書に加えてはいかがでしょうか。
竹下 隆一郎(たけした りゅういちろう)
ハフポスト日本版編集長。慶應義塾大学法学部卒業後、朝日新聞社に入社。経済部記者や新規事業開発を担う「メディアラボ」を経て、2014~2015年スタンフォード大学客員研究員。 2016年5月よりハフポスト日本版編集長として「会話が生まれるメディア」をめざす。2019年4月には出版社のディスカヴァー・トゥエンティワンとともに「ハフポストブックス」を創刊し、6月までに自身の著書『内向的な人のための スタンフォード流 ピンポイント人脈術』を含む6冊を出版。
■BLIND BOOK CLUBとは
「BLIND BOOK CLUB」は、様々なジャンルの第一線で活躍している方にテーマに基づいてご自身の人生において影響を受けた本を紹介いただき、それらの本をタイトルも著者の名前も明かさずにお届けすることで、アルゴリズム過多の時代に「本との偶然の出会い」を演出するサービスです。 仕事や暮らしのなかで抱いているもやもやが解消されたり、知的探究心を満たしたり、ストーリーや文章の一節に心が動いたり。選者とテーマの掛け合わせによって受け取る体験もちがうはず。その人がその本を選んだ理由の書かれたメッセージとともに読み進めていただけたらと思います。
あわせて読みたい
Photo: Ryuichiro Suzuki
Image: GettyImages
Source: BLIND BOOK CLUB, ハフポストブックス
大森りえ
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5