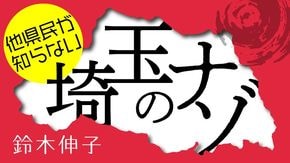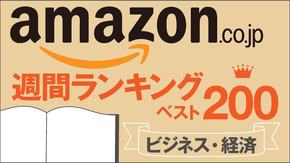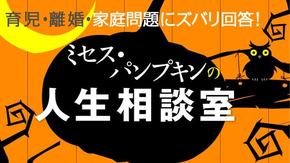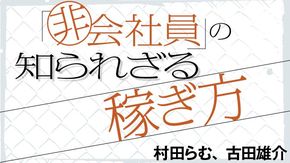治水の5大手法が「簡単だからこそ」難しいワケ
それぞれの河川、時代で最適を選ぶしかない
洪水は自然現象である。自然現象は整然としていない。大きく人間の予測を超えて暴れまくる。その洪水に対峙するとき、人間は洪水の気ままさに振り回されてしまう。振り回されているうちに、議論は拡散し、洪水対策の原則を見失いがちとなる。
気ままで狂暴な洪水に向かう際、不動の原則を持つことが重要である。そして、その原則は簡潔で、明瞭でなければならない。
大原則は「水位を下げる」の1点
「治水の原則」は「洪水の水位を下げる」。この1点である。
洪水の水位を10cm、いや2cmでも1cmでも下げる。それが治水の原則である。
この治水の原則は、簡単で、ぶれがない。簡単でぶれないからこそ、この原則から多様な治水の手法が生まれていく。
ただし、多様な治水の手法には厄介な問題が内在している。
すべての治水の手法は、長所と短所を持っている。絶対的に正しい治水の手法などない。
それぞれの河川で、それぞれの時代で、治水の原則に立ち、よりよい治水の手法を選ぶしかない。
最も原始的な手法は、ある場所であふれさせることである。ある場所で水があふれれば、そこから下流の洪水位は下がる。
この治水効果は絶大である。古い時代から、世界中で用いられていた。日本でもこの手法は多用された。
21世紀の今でも、中国の淮河(ワイガ)ではこの手法を使っている。2003年の洪水時、堤防を爆薬で爆破した。土地利用の低い地域を洪水で起こさせ、土地利用の高い下流地域を守った。
この手法は簡単で、効果は絶大である。しかし、決定的な欠点を持っている。
社会的強者のために社会的弱者が犠牲になる点である。現代の日本社会で、この手法は合意を得られない。