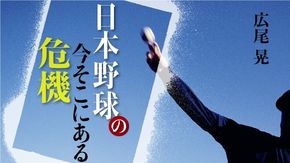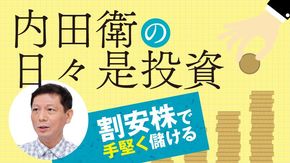「ウザい!」、氷河期世代に見捨てられた労働組合
それでも労組が必要な理由を探る「トラジャ」
JR東日本の遠大な対「革マル」戦術
「あの連中(JR革マル)にはアメ玉を食わせ、時間を十分にかけ、次第に牙がなくなるように対応し、ついには牙がなくなってしまう――というような遠大な計画が、JR東日本の対革マルの戦術だ」
後に会長になる人物がまだ常務だった頃、革マル派が中枢を握っていると見られるJR東労組との抗争の戦術を、こう語っていたという。
アメ玉をしゃぶらせておいて牙がなくなるのを待つ。悠長にみえる話だが、2018年、JR東労組がストライキを通告するなり、それがアダとなって、決壊と呼びたくなるほどの大量の脱退者を生む。なにしろ組合員数・約4万6900人を誇る巨大労組から、3万5000人が脱退したのだ。
革マル派ナンバー2と目される松崎明が、JR東労組を通じてJR東日本そのものを支配する。この実態を2006年から2007年にかけて、西岡研介は『週刊現代』で追及した。それをまとめたのが『マングローブ』(講談社・2007年)である。
それから12年、西岡は上述のようなJR東労組の崩壊にいたる過程と、同じく革マル派の影響下にあるJR北海道の惨状を書く。それが本稿で紹介する『トラジャ』(東洋経済新報社・2019年)だ。