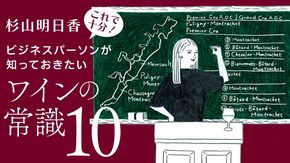生産性向上にコミットする経済政策を「High road capitalism」と言います。「王道」と訳されることもありますが、見方を変えれば「茨の道」とも言えます。当然、その反対は「Low road capitalism」です。こちらは、ある意味で「邪道」とも言えます。
経済の「王道」と「邪道」
簡単に言うと「High road capitalism」は高生産性・高所得の経済モデルです。「High road capitalism」の根本的な哲学は「価値の競争」です。市場を細かく分けて、セグメントごとにカスタマイズされた商品やサービスで競い合うのが競争原理になります。そのため、商品とサービスの種類が多く、価格設定も細かく分かれています。
High road capitalismを志向している企業は、商品をいかに安く作るかよりも、作るものの品質や価値により重きを置く戦略をとります。他社の商品にはない差別化要素であったり、機能面の優位性であったり、とりわけ、いかに効率よく付加価値を創出できるか、これを追求するのが経営の基本になります。
最も安いものではなく、ベストなものを作る。そのスタンスの裏には、顧客は自分のニーズにより合っているものに、プレミアムな価格を払ってくれるという信条が存在します。
High road capitalismを追求するには、もちろん最先端技術が不可欠です。そして、それを使いこなすために、労働者と経営者の高度な教育も必須になります。同時に機敏性の向上も絶対条件です。
「Low road capitalism」は1990年代以降、日本が実行してきた戦略です。規制緩和によって労働者の給料を下げ、下がった人件費分を使って強烈な価格競争を繰り広げてきました。
海外の学会では、Low road capitalismに移行すると、一時的には利益が増えると論じられています。しかし、Low road capitalismによって短期的に利益が増えるのは、技術を普及させるための設備投資が削られ、社員教育も不要になり、研究開発費も削減される、すなわち経費が減っているからにすぎません。Low road capitalismは先行投資を削っているだけなので、当然、明るい将来を迎えるのが難しくなります。まさに今の日本経済そのものです。
実は、「Low road capitalism」でも経済は成長します。しかしそのためには、人口が増加していることが条件になります。人口が減少していると、「Low road capitalism」では経済は成長しません。