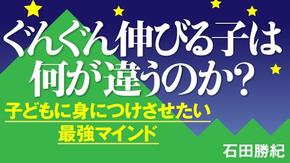SNSが日本の政治に与える無視できない影響
大量の「機械的な投稿」が世論を歪めている
実はドイツでも極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」に関して、SNSには同様の投稿があふれている。現地の報道では有権者への政治的影響を危惧している。
日本を見ると、たとえば、ここ数年で「反日」という言葉が随分ポピュラーになった。シェーファー教授はSNSでの投稿量が増えたことが大きな原因のひとつではないかと指摘する。「反日という言葉は、『A人は反日だ』『B党は反日だ』というように、人によって異なる対象に『反日』をつかっている。それらがボットで増幅され、投稿量がどっと増えた」。
また、人間も深く考えることなく扇動的なフレーズを取り入れてネットに書き込んでいるという問題もある。たとえば、ある人物がネットに「反日」という言葉を何度も書き込み、気に入った投稿に対してほぼ反射的に「いいね」ボタンを押す。「反日」というメッセージが記号的に増幅され、人間がボット化しているといえる。
このように現在はSNS発の「ポピュラーな言葉」が存在する。かつては辞書に掲載されるか否かが「ポピュラーな言葉」の指標だった。「辞書への掲載基準は新聞での掲載実績などが根拠とされます。新聞には『編集』という主体的な行為があり、一種のフィルター機能が働いている。しかし、SNS発の言葉がポピュラー化するにあたってはフィルターがない。ボットはそれに加担している」とシェーファー教授は言う。
SNSがネットの役割を変えた
インターネットは20世紀末に普及がはじまったが、当初は「知識の公共化」とか「国境を越えたコミュニケーション」や「グローバルな公共空間の構築」といった民主主義の進化に役立つものと期待された。
「人間によるコミュニケーションには決まった結果はない。もちろんそのせいで感情的になり、例えば殴り合うといったリスクもある。しかし、人間はコミュニケーションを続けることで学習できる。初期のインターネットではそういう方向でコミュニケーションが深化するのでは、という期待があった」(シェーファー教授)
ところが今世紀に入り、SNSが普及すると状況は変わった。ネット空間は高度なアルゴリズムを伴うSNSのプラットフォームと化した。
「ここでは『いいね!』やリツイートなどを通じて、ユーザー同士がただ『つながっているだけ』 という関係性の比重が高くなりました。そこへボットが特定の情報やフレーズの流通量を増やしてさらに極端な方向性を生む。しかも個人の検索履歴などをもとにその人に合った情報のみが提供されるため、情報や思想が偏り、情報社会の中で孤立する『フィルターバブル』に陥りかねない」とシェーファー教授は警鐘を鳴らす。そしてさらにこう続ける。
「こうした現状を見ると、アイデアが偶然に生まれる可能性が低くなり、人々の考え方も狭めることにつながる。そんなふうに思えてなりません。今日、ネットは現実世界になくてはならないものになっているが、民主主義の健全性という点でいえば憂慮すべきだと思います」