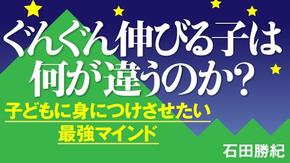分析対象は2014年12月8日から30日にかけて収集した約54万の投稿だ。政党名や政党代表者名、脱原発などキーワードをもとに集めた。大半はオリジナルの投稿をコピーしたものだが、興味深いのは約14万件のツイートだ。
内容は「反安倍政権ブログへの攻撃」、それから意外に思う人もいるかもしれないが、「右寄りの立場からの安倍政権批判」だった。テキストを分析したところ、わずか3700程度のオリジナルの投稿をボットが少し変更して、投稿したものと考えられるという。
「2014年の総選挙では『アベノミクス』継続の是非を巡り、経済政策が争点になっていたが、同時に隠れた民族主義とでも言うものが重要なテーマでした。これが収集したTwitterの投稿にも反映されているように思う」とシェーファー教授は言う。
さらに、「2013年当時は、日本でよりメジャーなSNSはFacebookではなくTwitterだった。また、Twitterに投稿されるテキストの量が世界で2番目に多い言語は日本語だった。ただ、日本語による投稿の多くはボットによるものと推測される」という。
ボットを操るのは見えない人間
ある投稿を100回ツイートしろ、といったことをボットにさせるのは人間だ。だがどんな人物なのかは特定できないし、もちろん安倍政権関係者がボットを利用しているかどうかはわからない。「つまり、われわれは、ボットがどのように働いていたかという現象を事後的に見るしかない」(同氏)。
極端な例をあげると、特定のある内容の投稿で1万回程度を数えるものがあったが、解析するとオリジナルは50ほど。ボットがオリジナルの投稿をそのまま、あるいは少し変更して1万回分リツイートしたわけだ。
こういったボットによる「活動」は近年増えている。たとえばトランプ大統領による頻繁なTwitter投稿はよく知られるところだが、投稿するやいなや、すぐに2万ぐらいの「いいね!」「リツイート」などの反応がある。「しかしボットによるものがかなりあると思う」(同氏)。
さらにシェーファー教授はこう続ける。「ボットの機能は進化もしています。人間はオリジナルの投稿に反応するにしても、ある程度時間差が生じる。たとえば夜中に投稿されたものをリツイートするのは朝起きてからになる。また、人間はリツイートする時に少し文章を変えたり追加したりすることもある。ボットはそういう人間らしさを意図的に取り入れるようにもなっている」。