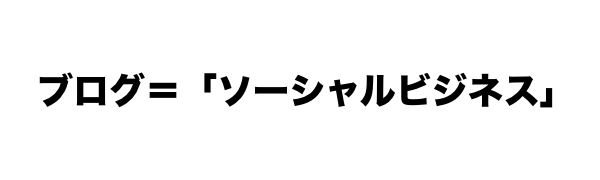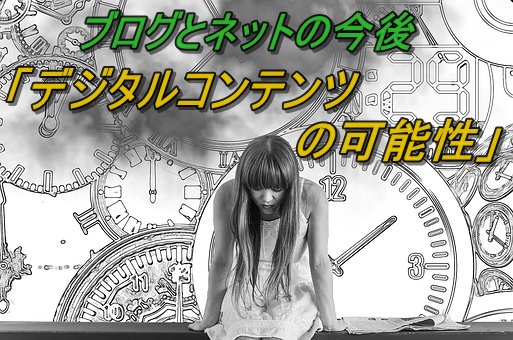肩甲骨に付着する背中の筋肉に、菱形筋群があります。あまり目立たない筋肉ですが、姿勢や肩・背中のこりに大きく関係しています。菱形筋とは何か?また、その筋トレとストレッチの方法についてご紹介します。しっかりと動かすと意外と気持ちよい筋肉ですので、菱形筋の筋トレとストレッチは非常にお勧めです!
目次 [非表示]
「菱形筋」ってなに?
菱形筋は小さい筋肉で、背中にある、広背筋や僧帽筋などの深層に位置するインナーマッスルです。
菱形筋は、肩甲骨の内側縁から起始し、脊柱(小菱形筋は頸椎、大菱形筋は胸椎)の棘突起に停止しています。
菱形筋には
- 大菱形筋
- 小菱形筋
があります。上から順に小菱形筋があり、その下に小菱形筋より少し大きな筋肉、大菱形筋があります。
その名の通り、ひし形をしています。
菱形筋が収縮すると、肩甲骨を内転させる(肩甲骨を背骨(脊椎)に引きつける)働きがあり、さらに、起始している位置を見て頂けると理解できると思いますが、肩甲骨の内側縁下の方(肩甲棘以下)を上に引っ張るので、肩甲骨を下方回旋させる働きもあります。
| ■大菱形筋 |
| 【起始】T1~T4(棘突起) |
| 【停止】肩甲骨(内側縁下部) |
| 【支配神経】肩甲背神経 |
| 【主な機能】肩甲骨の内転、下方回旋 |
| ■小菱形筋 |
| 【起始】C6・C7(棘突起) |
| 【停止】肩甲骨(内側縁上方) |
| 【支配神経】肩甲背神経 |
| 【主な機能】肩甲骨の内転、挙上、下方回旋 |
菱形筋群の機能・役割
菱形筋は純粋に収縮すると、肩甲骨を下方回旋させながら、内転させる働きがあります。
そう言われても、「だから何?どんな効果があるの?日常生活でどんな時に使うの?」と思う方もいらっしゃると思います。
確かにあまり肩甲骨を意識的に動かす機会は日常生活で多くはありません。
菱形筋の実際の機能・効果を以下にご説明していきます。
肩甲骨の安定化に寄与
菱形筋は肩甲骨の安定性に大きく関係しています。
肩甲骨は肩甲胸郭関節により、肋骨の上で結合しています。肩甲胸郭関節は、膝関節や肩関節とは異なり、骨と骨で連結されておらず、安定性は保たれていません。
いわば宙に浮いている状態で固定されていることになります。
これは、肩甲胸郭関節が大変可動性の高い関節であるためです。逆にガチガチに固定されていると、腕を自在に動かすことができなくなってしまい、生活に支障が出てきます。
腕を上げる動作など、上腕骨を動かす時にその土台となるのが肩甲骨です。そして肩甲骨は上腕骨の動きにある一定のリズムで付随して回旋したり、挙上・下制したりします。(これを”肩甲上腕リズム”と言います。)
”宙に浮いている”肩甲骨のポジションや安定性に関係している筋肉として、肩甲骨に付着する筋群、具体的には、この菱形筋を始め、
- 僧帽筋
- 肩甲挙筋
- 前鋸筋
- 小胸筋
があります。
これらの筋が筋力低下を起こすと、肩甲骨のポジションが変化し、不安定性が増大します。
結果、上肢の動きと肩甲骨の動きの連携が上手くいかず、インピンジメント症候群(上腕骨と周囲の組織が衝突する)が出現しやすくなります。
また、菱形筋は、肩甲骨の内側縁で前鋸筋と繋がっており(筋連結)、共同して働くことで肩甲骨を安定させています。
菱形筋と前鋸筋を一緒に鍛えることで肩甲骨はより安定するという報告もあります。
肩甲骨の安定化ではなく、肩関節の安定化に寄与する筋肉群に、”ローテーターカフ”というものもあります。
肩関節の運動を考える上で必須の知識になるので、参考にしてみて下さい。
参考)こう理解すれば簡単!インナーマッスル、ローテーターカフ(回旋筋腱板)の解剖と役割を解説
肩こりにも関係
しつこい肩こりの多くは、肩甲骨の位置が下がっていたり、肩甲骨が前に突出していたり、肩甲骨の位置に根本の問題があることが多いです。
菱形筋は立位姿勢時に常に緊張しており、肩甲骨を適切な位置に保つ働きがありますが、筋力が弱っていたり、機能不全に陥っていると、肩甲骨は外転位となり、僧帽筋に余計な負荷が掛かってしまいます。
結果、僧帽筋などの肩甲骨に付着する他の筋肉に肩こりの症状である、痛みやだるさが出現しやすくなります。
姿勢(猫背・円背)に関係
菱形筋は、肩甲骨を内転位に保つ働きがあります。
この機能が弱り、肩甲骨が外転していると、いわゆる円背(猫背)の姿勢になります。外見的にも老けて見られやすくなってしまいます。
しかし、猫背による菱形筋の変化は、どちらかというと2次的なもので、猫背の直接的な原因になるようなものではありません。
猫背などの、普段その人が取っている姿勢を決定する要素には、”運動連鎖”が大きく関係しています。
- 菱形筋が弱る→猫背になる
という訳ではなく、
- 猫背になる→菱形筋が弱る
というパターンがどちらかというと多いと思います。
そして、上半身よりも、足などの地面に近い関節の変形や異常が姿勢に影響を与えていることも多いです。
例えば、膝関節になにかしらの障害があり、完全に伸ばすことができないと、立っているだけで、自然と猫背の姿勢になります。
そうなると、猫背が普段取っている姿勢となり、結果菱形筋が弱化するなどの変化が表れ始めます。
ハイヒールを履く女性は要注意!
よくある身近な例では、女性でハイヒールを履く人は踵が上がるので、普通の靴を履いている状態よりも過剰な姿勢制御を必要とします。
結果、膝が曲がりやすくなり、猫背になりやすくなります。
以下にその機序を記します。
- ハイヒールを履くことで、踵が上がる。
- 前に倒れないように膝が曲がる。
- 後ろに倒れないよに身体が曲がる。
- バランスを保つために猫背になる。
- 菱形筋などの肩甲骨のポジションを適正に保つ筋肉に異常が出現(筋力低下・過緊張など)
という順序で猫背になり、背中や肩(菱形筋や僧帽筋など)の凝りを感じやすくなります。
猫背解消のためのストレッチと筋トレの方法も別記事にまとめているので、よければ参考にしてみて下さい。
参考)背中が丸まる原因と自分で簡単にできる解消法!円背のストレッチと筋トレで全身調整を!
菱形筋を鍛える効果・目的
菱形筋を鍛えるとどんな効果があるのでしょうか。
代表的なものに、
- 肩の怪我の予防
- 肩こりの解消
- 姿勢矯正
の効果があります。
1.肩の怪我の予防
上述の様に、インピンジメント症候群を予防する目的で菱形筋を鍛えることがあります。
特に投球動作などで肩を酷使する野球のピッチャーなどは、怪我の予防のために菱形筋を鍛えることは必須となります。
2.肩こりの解消
菱形筋を鍛える目的としてはこれが一番多いと思います。
肩甲骨の位置を適正な位置に戻し、その他の肩甲骨に付着する筋肉の血流を良くし、肩こりを解消します。
肩よりも背中が凝っている感じがするという方は、こちらの記事に背中のストレッチと運動の方法をまとめています。
3.姿勢の矯正
菱形筋を鍛えることによって、肩甲骨は適切な位置に整います。
猫背になっていると肩甲骨は重力に引っ張られ、外転位となります。菱形筋は常に引き伸ばされている状態になり、阻血状態になります。
菱形筋を鍛えることで、重力に抗して肩甲骨が保持できるようになり、結果、姿勢の改善に繋がります。
スポンサーリンク
菱形筋の筋力トレーニングの方法 2種類
菱形筋は肩甲骨を内転させる動き(肩甲骨を背骨に近づける動き)で鍛えることができます。
肩甲骨を内転させる運動では、
- 何かを持って後ろに引く(机の引き出しを引き出すような動き)
運動が一番分かりやすいと思います。
この運動は上腕二頭筋や三頭筋などの腕の大きな筋肉、アウターマッスルも必然的に参加します。菱形筋は肩甲骨を保持するために補助的に少し働く程度です。
よって、これを立って、あるいは座ってやるだけでは少し負荷が軽すぎます。
よって、
- ダンベルを使う
- 重力の力を利用する(寝るなど、肩甲骨が内転する時に重力が掛かる肢位を取る)
などで筋肉の負荷を調節し、鍛えていきます。
また、肩甲骨の内転の動きは、体幹と肩関節が90°の角度にある時に最も動きが出やすいです。この角度が変わってしまうと、肩甲骨に回旋の要素が入ってきます。効果的に菱形筋を鍛えたいなら、肩を体幹から90°開いて行うことに注意して下さい。
1.テイクバック

方法:
- うつ伏せで寝て、鍛えたい方の肩を90度に曲げ、腕も直角に曲げます。
- 床から肘を浮かせるように真上に上げていきます。
- 肘を浮かせたまま10秒程度保持します。
注意点:
肩甲骨を内転(背骨に近づける)させる意識で行って下さい。
効果:
この運動をすると、重力に抗して肩甲骨を引き上げるために、菱形筋が強く働きます。肩こりがあり、普段猫背な人は、この運動をやってみると、血行が良くなり、背中の重だるさが解消させるのがすぐに実感できると思いますよ。
姿勢矯正効果を狙うには、肘を浮かせたままで保持し、持続的な収縮の負荷を与えます。
2.ワンハンド ロウイング


方法:
1.何か支えを持ち、反対の手にダンベルや重錘を持ちます。なければ水の入ったペットボトルなどでも結構です。
(適度な重さは、個人によって差があり、この運動が何とか10回できる程度が丁度よいです。)
2.体を前傾姿勢にして、肩関節を90°外転させ、肘を真上に挙げます。
注意点:
体がぶれないように固定して動かさない様に注意して行って下さい。身体を回旋させる動作が入ってしまうと、効果的に菱形筋を鍛えることができません!
また、疲れてくると、どうしても身体の回旋動作が代償動作として入ってくるので、10回程度を目安に一度休憩を入れると、より効果的です。
菱形筋のストレッチの方法 3種類
菱形筋のストレッチの方法を3種類ご紹介します。
ストレッチの定義は、筋肉が伸ばされる状態のことを言いますが、菱形筋の性質上、猫背のため、ずっと張っていて阻血状態になり、肩こりや背中の重だるさになっている場合も多くみられます。
よって、どちらかいうと、ストレッチするよりも、緩める(たるませる)方が気持ち良く感じる方も多いと思います。
なので、厳密にはストレッチではありませんが、番外編として、菱形筋を緩める方法もご紹介しておきます。
1.菱形筋ストレッチ①
方法:
- 立位、または座って、反対側の肩甲骨を触ります。
- 体を少し丸めるようにして、肩甲骨を背骨から引き離すように外転させます。
注意点:
このストレッチも身体の回旋(身体をひねる動作)が入ってくると、菱形筋はストレッチされにくくなります。必ず、体を固定し、回旋させないように注意して下さい。
また、リキんでしまいやすい肢位でもあるので、できるだけ力を抜いて、脱力して行って下さい。
2.菱形筋ストレッチ②

方法:
- 反対側の肘をロックするように写真を参考に持ちます。
- 身体の外側へゆっくりと引っ張ります。
注意点:
これも同じで、体を捻って回旋させてしまわない様に注意して下さいね。
3.菱形筋を緩めるストレッチ③
方法:
- 胸を張り、後ろで手を組みます。
- そのまま、胸を前に突き出すようにしていきます。
注意点:
リキんでしまうと筋肉を緩めることはできませんので、脱力することを心掛けて下さい。
このストレッチは菱形筋の反対の作用を持つ(拮抗筋といいます)大胸筋のストレッチの簡単な方法です。肩甲骨を適切な位置に保つ機能のある筋肉のうち、大胸筋は表面積が大きく、強力な筋肉なので、逆に言うとこわばりやすい性質があります。
日常生活のデスクワークなどで猫背になっている時間が長い人は、ほとんど例外なく、大胸筋がカチカチになっています。
この胸を張る運動は仕事中に座ったままでも簡単にできますので、少し疲れや凝りを感じた時に小まめにやるとリフレッシュできると思います。
まとめ
菱形筋の機能や役割、筋トレとストレッチの方法をご紹介しました。
日常生活の姿勢に大きく関係があり、問題を抱えていることも多い筋肉ですので、是非この記事を参考にリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。