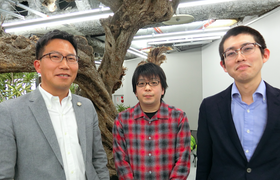優秀な人材獲得は大企業にとっても、ベンチャーにとっても直近の課題。しかし、首都圏での優秀な人材はまさに取り合いだ。
そんななか、「京都」に注目する企業が増えている。
名刺管理サービス大手のSansanは先週、京都におけるAI技術者の新たな活動拠点「Sansan Innovation Lab」(以下、イノベーションラボ)を開設した。イノベーションラボが位置するのは、京都・河原町の観光地、錦市場にほど近い住宅街。元になった町家は繊維業に関係する人物が建てたもので、築100年以上。この町家をリノベーションし、歴史ある町家独特の構造を残したまま、SansanのAI技術者グループDSOC(Data Strategy & Operation Center)のメンバー2名が常勤するオフィススペースと、収容人数20名ほどのイベントスペースをつくった。
常勤メンバーの1人は、世界的なデータサイエンティストコミュニティ「Kaggle」の上位100人ほどしかいないグランドマスターの称号を持つ人物だ。

Sansan取締役で、AI技術者グループ「DSOC」のセンター長を務める常樂諭氏。熱意を持って2年以上、物件を探し続けた。
オープニングイベントに登壇したDSOCセンター長の常樂諭氏によると、こういった京都の中心部にある町家は、そもそも物件自体があまり出て来ない。オフィス利用が可能な改装ができる物件となるとさらに珍しいという。Sansanは2014年から京都に拠点を持っていたが、寺社仏閣のような歴史のある伝統的な建物にイノベーションラボをつくりたいと地道に物件を探し続け、知人の縁でようやく現在の場所に巡り合った。
「京都で働ける」が国内外の人材採用に有利な理由
実は、Sansanのイノベーションラボの近辺には、複数のIT企業やメーカーの拠点がある。
たとえば、はてなの本社・京都オフィスのほか、LINE KYOTOや、パナソニックの家電デザインの拠点・Panasonic Design Kyoto、また人材系ベンチャー・リブセンス(東京・品川区)も小規模ながらこの9月からオフィスを構えた。
「京都オフィス流行り」の背景には、人材獲得競争が過熱の一途をたどる東京以外に目を向け、京都・大阪の優秀な人材に目を付けた企業側の思惑がある。
ヒントは、京都の街の特性と、人材のギャップだ。
京都は京都大学をはじめとする国内トップ級の頭脳を持つ優秀な人材が数多く生活する「優秀な学生の街」だ。しかし事実として、京都近辺には東京ほどIT企業の数がない。
関西の大都市といえば大阪も神戸もある。けれども大阪は「ビジネスの街」としての印象が強いし、神戸はアクセスがやや悪い。その点で京都は、外国人が憧れる「KYOTO」ブランドがあり、大阪からも名古屋からも近い。新幹線の駅もある。学生の質の高さは言うまでもない……そうした複数の要因が絡み合って、「大阪でもなく、名古屋でもなく、どうせなら京都にオフィスを」という企業が増えているようだ。
Sansanの常樂氏は、オープニングイベントに先だったインタビューで
「京都にKaggleのグランドマスターがいる、というのは(Sansanに興味を持ってもらうう意味で)大きい。この地域は京大生の学内スタートアップも多い。ベンチャーもそうだし、学生にも、(社会で活躍するための)もっと良い機会をつくっていきたい。若者たちが世界で戦えるだけの知識や基盤を用意することは、(ベンチャー気質の企業である)Sansanの責務だとも思っています」
とも発言していた。京都は一種の「穴場」であり、ITベンチャーにとっては盛り上げていく面白みがある街ということなのだ。
「京都」はIT企業にとって穴場だった

Sansanの藤倉成太CTO。
エンジニア採用の難しさと、京都の地の特殊性について、オープニングイベントではこんな声も複数聞いた。
京大生をはじめとする優秀な学生は数多くいるのに、IT企業が少ないことで「頭脳を生かしたアルバイトに就きにくい」という話だ。
もちろん、ファミレスやコンビニで働くのは貴重な社会勉強になる。けれども、能力を発揮するための選択肢が少ない、という事実は、関西からSansanやメルカリ級のベンチャーが生まれる機会を減らしていることは確かだろう。
Sansanの藤倉成太CTOは、「エンジニア採用の世界でSansanのプレゼンスを出していきたいのは狙いの一丁目一番地としてある」ものの、京都に拠点をつくることには複合的な意味を感じているようだ。
たとえば、海外からの人材採用にも、京都は有利だという。外国人エンジニアを採用するにあたっては給与以外の待遇も重要だ。そのとき、「歴史と文化の街・KYOTOで働ける」というのは、外国人エンジニアからの反応が良いと語る。外国人採用は、Sansanとしても「今まさにアクセルを踏まんとしているところ」(藤倉氏)で、その意味でも京都の拠点をつくる意味は大きい。
Sansanは、この場を社内のAI研究者の拠点にするのみならず、地域のAI系のベンチャーや京都大をはじめとするアカデミアが集まる、AIコミュニティの交流の場にしていきたいという。まずは京都のAIコミュニティーをさらに盛り上げることで、イノベーションラボの価値が高まり、価値が高まるほどに採用にも有利になり、また地域企業を横串にすることで生まれるイノベーションも起こしやすくなる —— そういった考え方だ。
人材獲得競争が続く東京は、ある意味で「企業が仕掛ける面白いこと」は出尽くした感がある。今から研究拠点をつくっても、数年前ほどの目新しさはない。
エンジニア、特にデータサイエンティストなどの数学系人材の採用では、IT企業は規模の大小にかかわらず、グーグルのような巨人とも互角に戦っていかなければならない。そのなかで、「先鋭感のあるブランディング」と「採用への実利」のある選択が、京都オフィス流行りのトレンドを作り出しているといえそうだ。
(文、写真・伊藤有)