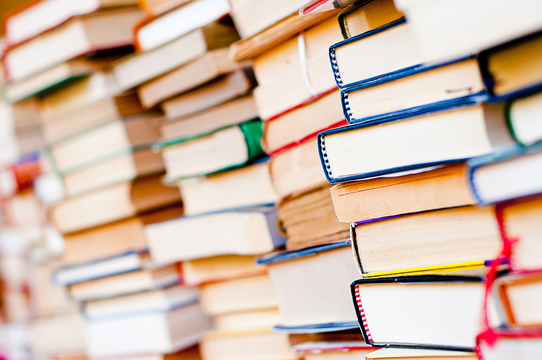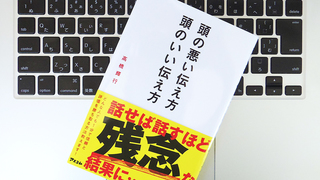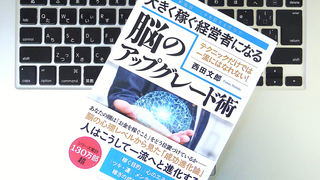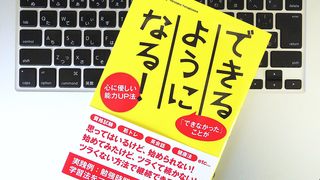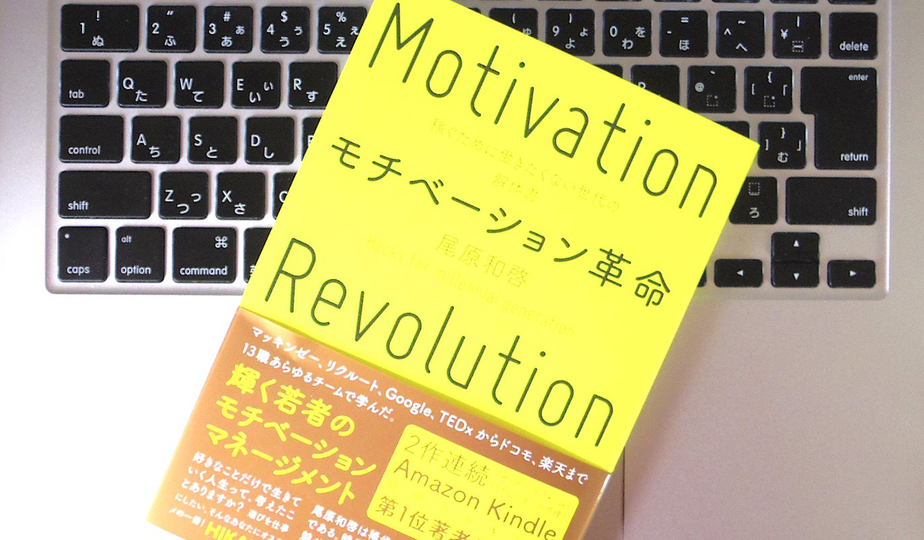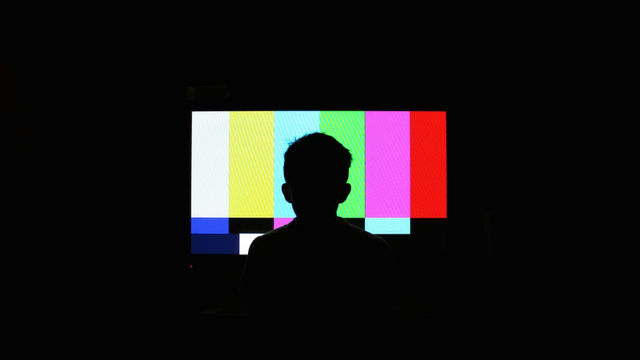世界のトップリーダーたちは、完璧でも聖人君子でもなく、苦手なことや欠落部分も持ち合わせた「普通の人間」。テレビや雑誌を通じて見ると完璧な人のように思えるけれども、会ってみれば、実は人間臭い「ただの人」なのだということに気づかされる。
多くの名だたるトップリーダーと接してきた『世界のトップリーダーに学ぶ 一流の「偏愛」力』(谷本有香著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)の著者は、彼らについてそう記しています。
ただし、そんなトップリーダーたちに共通する条件があるのも事実なのだそうです。
それは、何かしらの「強い思い」をもって生きていること、そしてその思いを、それぞれの手段を使い、社会に還元しているということです。私は本書でこれを、「偏愛力」という言葉で表現させていただきました。(「まえがき」より)
どんな人にも、「大好きなこと」「熱中してしまうこと」「やめろと言われてもやり続けてしまうこと」、あるいは「どうしても意識がそちらに向いてしまうこと」など、エネルギーレベルの高い“なにか”があるものです。
トップリーダーたちはそれらを使い、社会との接点をつくっていくということです。そしてそれは結果的に、多くの人たちの共感を呼び、信頼を集め、その人を時代のリーダーへと押し上げていくのだといいます。
しかも昨今、その傾向はますます強くなっていると著者自身は感じているのだといいます。
そこで本書では、そういった「好き」をベースに時代をリードしていっている人たちの条件や事例などを紹介しているわけです。
きょうは「トップリーダーに共通する『偏愛力』とはなんなのか、そして、それをどう使えばよいのか」について説明した第2章「偏愛+共感=信頼」のなかから、重要なポイントを抜き出してみたいと思います。
個人の「信頼」が世界を動かす時代がやってきた
新時代のリーダーに求められる三本柱は「偏愛」「共感」「信頼」であり、なかでも重要なのが「信頼」であると著者は主張しています。なぜなら、これからの社会にもたらされる最大級の変革は、次のひとことで表されるから。
「通貨は『お金』から『信頼』へと変わる」(86ページより)この前提がある以上、従来の働き方ではなく、より個人の特性が問われるビジネス・アイデンティティを軸とした働き方にシフトしていかないと生き残れないという考え方です。
とくに個人の「信頼の大きさ(信頼指数)」は、これからの社会においてもっとも大きな価値となり、人々が選択する際の基準になるといいます。
つまり今後は製品やサービスの性能そのものよりも、「誰がやったのか」「誰が言っているのか」「どんな人がしているのか」という基準で選ばれるようになるということ。
事実、世界では信頼社会への動きが加速化しており、その一例としてここで挙げているのが、中国版アマゾンといわれる通販サイト「アリババ」を運営するアリババ社が展開する「アリペイ(支付宝)」というオンライン決済サービス。
「ペイパル」に似たサービスではあるものの、店頭やオンライン上での買い物、電気、ガスなどの公共料金、タクシー料金、交通機関のチケット予約、知人への送金など、日常生活で必要なサービスを幅広くカバーしているのだそうです。
注目すべきは、このアリペイの付帯サービスとして飛躍的に普及している「ジーマ信用(芝麻信用、セサミクレジットともいわれる)」。これはアリペイを通じて支払いをした履歴などをもとに、個人の「信用スコア」が次の5つの側面から350~950点の間で点数化される仕組みなのだといいます。
(1)プロフィール:学歴や勤務先などのステータス
(2)支払い能力:過去の支払い能力
(3)過去の信用履歴:クレジットカードなどの支払い履歴
(4)人脈:交友関係
(5)行動:とくに消費行動など
(88ページより)
クレジットカードなどによる「信用の数値化」自体はこれまでにもありましたが、ジーマ信用ではアリババが展開するサービスやアリペイを通したさまざまな利用履歴から「信用スコア」を算出しているわけです。
つまり中国ではすでに、オンライン決済サービスなどを通じ、普段の行動から自分の「信頼指数」がリアルタイムで数値化されているということ。
もちろん、信用スコアが高ければ高いほど、多くのメリットを得られるようになります。いわば、個人の信用によって経済が動く仕組みにシフトしているわけです。
最近では就活や婚活にもジーマ信用が活用される動きがあり、信用によって、その人自身の人生までが決定づけられるようになってきたというのです。
ところで著者は先日、モナコで開催された「EY World Entrepreneur Of The Year」に参加してきたそうです。これは各国で選ばれた起業家代表が全世界から集まり、世界一を決めるという祭典。2018年の優勝者は、住宅建設・不動産会社を経営するブラジル代表に決まったのだといいます。
彼が評価されたのは、これまで家を持てなかった人たちに家を持つ喜びを与えるという理念のもとに活動していること。事実、低所得者向けの住宅建設としては、ブラジルでトップの企業にもなったのだとか。
このイベントで各国の代表の話を聞いていて感じたのは、売上や利益の数字を追い求めることにしか関心がない強欲的なリーダーでは、今の世の中ではもはや誰からも信頼してもらえない、ということです。
顧客はもちろんのこと、従業員やその家族、地域の人たちに受け入れられて、はじめて売上につながるという考え方。今、時代は「信頼」のベースが不可欠になっているのです。(91ページより)
そのため、「この人は信頼に値するだろうか?」という問いに応えられる「信頼度数の高い人」と「信頼度数の低い人」の格差は、急速に拡大していくというのです。(86ページより)
「普遍性」より「偏愛性」
信頼が可視化される時代だからこそ、「好きなことを仕事にする」「好きで好きでたまらなくてこの仕事をやっています」という純粋な偏愛性が共感を得て、お金が集まる(信頼される)対象にもなっているのだといいます。
偏愛とは、自分が「特別に熱中できる度合い」の大きさのことであり、ビジネス・アイデンティティも偏愛の延長線上に存在することがほとんどです。
ロボットに対して偏愛を持つ人は、いつもロボットのことについて考えており、やがてこれまでにないロボットを生み出せるようになります。
時代劇が好きな人であれば、やはり時代劇のことを普段から自然と考察し、いつしか時代劇好きにとってはたまらない作品や商品を生み出せるかもしれません。(97ページより)
ロボットや時代劇が好きな人はたくさんいるでしょう。しかし、それをいつでも考えてしまうほど好きで、仕事にしようとまで考える人となるとごく少数に限られてくるはず。
いってみれば、その極端な情熱こそがまさに「偏愛」だということです。したがって、自分自身の「好きで好きでたまらない」という偏愛から生まれる意思や目標は、ビジネスにおける最大の「自己プロフィール」になるのだということ。(96ページより)
消費者は、価格や品質といった普遍的な価値ではなく、「偏愛」によって生まれる、他にはない「こだわりの品」や「驚きのサービス」に価値をおき、お金を払うもの。
「好きでたまらないことを仕事にしている」 「いつか絶対こんなことをやりたい」 「このこだわりは絶対になくさない」
そういった偏愛性から生まれるものには自然と熱意が加わり、それが他社の心に届くことで共感を生むということ。この偏愛と共感の両面があってはじめて、人はそこに「信頼」を置くわけです。
その証拠に、好きなことを仕事にしたとしても、それが他者にプラスになるレベルの貢献すらできていなかったとしたら共感は生まれません。たとえばどれだけパンが好きだったとしても、焼いたパンが生焼けで味も悪く、体にも悪いパンだったとしたら、その商品に共感など生れようもないわけです。
つまり、単に熱中するだけではビジネス・アイデンティティにはなりえないということ。ビジネス・アイデンティティとして成り立つためには「熱中するほど好きなこと+他者貢献」の両面が必要になるということです。
そういう意味において、ビジネス・アイデンティティを形成する2つの要素である「熱中できるほど好きなこと」「他者貢献」はそれぞれ、「偏愛」「共感」に対応しているといえるそうです。
それは、次のように図式化することが可能。
つまりは、この両面が揃ってはじめて、それはビジネス・アイデンティティとなり、そこに「信頼」という価値が生まれるという考え方。
これからの信頼資本主義社会において重要なのは、いかに自分自身の偏愛性を高め、いかに他者に届けられるかということ。それが、自身の信頼と直結して評価につながるというわけです。(96ページより)
「好き」を妥協なく、とことん突き詰めてこそビジネス・アイデンティティが 生まれるという考え方はとても現代的であり、強い説得力を感じさせます。そして著者が言うように、こうした考え方はこれからの社会を生きていくためには欠かせないものとなるでしょう。
本書を参考にしながら、自分のなかの「偏愛力」を高めていきたいものです。
Image: ライフハッカー[日本版]編集部
Photo: 印南敦史
印南敦史
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5