「内科医 工藤」を名乗る人物が運営する「医師が教える長生きのための食事術」というブログが9月26日までに閉鎖された。この人物は“医師の私が解説”“癌に効く”などとして、健康食品を紹介していた。

現在は閉鎖されている「医師が教える長生きのための食事術」の記事。特定の健康食品を「癌に効く」などとして販売していた。

「内科医 工藤」としてTwitterアカウントも運営、医療・健康情報を発信していた。
しかし、この「内科医 工藤」なる人物は実在しない。26日夜までに、Facebookページおよび同ブログに、謝罪文が掲載され、運営者の男性が自らを医師と偽っていたこと、商品について“効果を過大に説明”していたことを認めた。
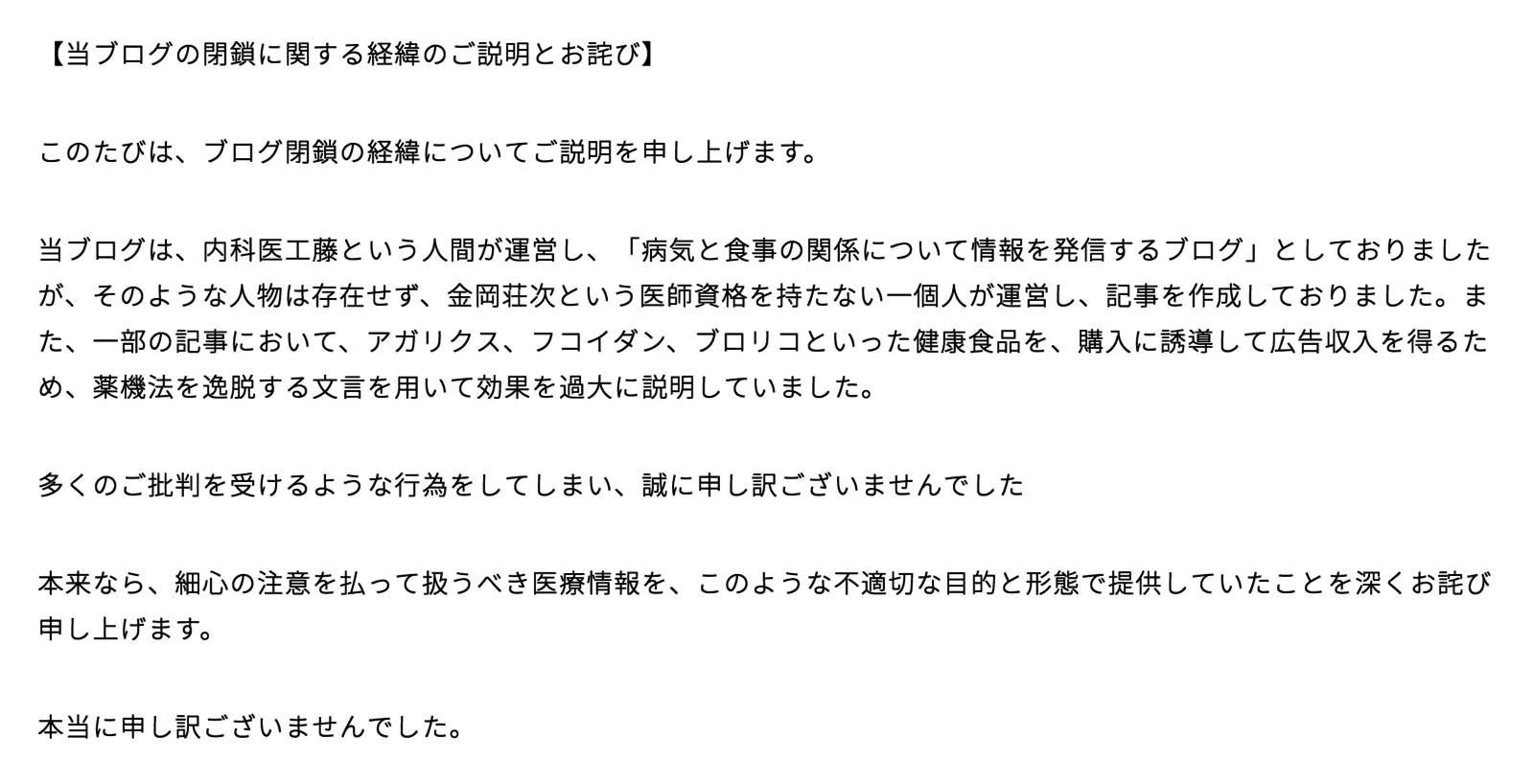
現在、ブログのトップページには謝罪文が掲載されている。
また、BuzzFeed Japan Medicalの調査で、運営者は紹介していたうち一つの健康食品を販売する企業の社員だったこともわかった。
なぜ、このようなことをしたのか。BuzzFeed Japan Medicalの取材に、運営者のA氏が回答した。
目的は「広告収入」、ビジネスチャンスと判断
まず、A氏は一連の行為について「大変不適切なことをしてしまった」「深くお詫びしたい」と述べた。
このブログを開設したのは、A氏によれば「7月ごろ」。目的は「アフィリエイト広告により収入を得るため」、医師と偽ったのは「情報の信頼性を高めるため」だった。
*アフィリエイト広告:インターネット広告の一種。広告主は自社の商品やサービスについてASPと呼ばれる仲介業者に広告出稿を依頼し、ASPは広告主からの依頼内容を複数のウェブサイト運営者に紹介する。サイト運営者はサイト訪問者に商品やサービスを紹介し、そこで購買や登録などの「成果」が発生し、認められると、報酬がASPを介して広告主からウェブサイト運営者に支払われる。
「会社からは十分な給料をもらっていたし、特にお金に困っているということはありませんでした。それでも収入を増やそうとしたのは……。将来への備えというか、お金を稼いでおきたかった、というのが理由です」
一方で、アフィリエイト広告の性質上、成果が認められるまでにある程度、時間がかかるため、現時点での収入はゼロだった。7月の開設から、購買があったのは複数の種類の健康食品で、「おそらく9〜12個ほど」。
金額にして約10万円ほどだが、すでにASPサービスからも退会しているといい、収益として入る見込みはない。
また、A氏は都内の健康食品の販売企業の社員で、自社の商品も取り扱っていた。会社が把握していたかどうかについては「私個人の行動で会社は関係ありません」。自社の商品で、詳しかっただけだという。
この企業は26日付でA氏を解雇。BuzzFeed Japan Medicalの取材に、以下のように回答した。
「このような行為は決して許されるものではなく、大変遺憾に思っております。今後二度と同様の事案が発生しないよう、社員の教育・指導を徹底して参る所存であります」
「景表法」や「刑法」、「薬機法」違反の可能性
このブログには複数の問題があった。1つはA氏が医師であると偽っていたこと、もう1つは取り扱っているのが健康食品であるにもかかわらず、“癌に効果的”などとして、抗がん剤の副作用の軽減、がんの再発防止を謳っていたことだ。
医師であると偽り、健康食品を販売することについては、消費者庁の表示対策課の担当者が、景品表示法上の優良誤認にあたり、同法に抵触する可能性を認めた。
厚生労働省の医政局医事課の担当者は、医師であると偽って医(療)行為をしていたわけではないなら、医師法違反であるとはいえない考えを示した。しかし、詐欺罪など刑法に抵触する可能性があるとした。
健康食品であるにもかかわらず、がんへの効果効能を謳うことについては、厚生労働省の監視指導・麻薬対策課の担当者は、医薬品医療機器等法(薬機法)違反になるとの見解だった。
こららの問題について、A氏は「倫理的に許されることではないと認識していましたが、法令についてはきちんと理解しておりませんでした」という。
では、認識していたという倫理の面については、どうして一線を超えてしまったのか。A氏はこう説明する。
「医師の方が発信する情報は今、受け手の需要が高く、医師の方は栄養の専門家というわけではない。医師が栄養について説明すれば、ビジネス上のチャンスがあると考えました」
「ニーズがあるのに、手つかずになっていたから……」とAさん。そこにビジネスチャンスを見出してしまった。
一部上場企業のDeNAが医療メディア運営において利益追求を優先した結果、不正確な記事を大量生産し、謝罪会見を開いた「WELQ問題」のことは知っていた。自分がやっていることにも問題があるとは感じていたが、歯止めにならなかった。
謝罪文を掲載し、今後はどのように対応するのか。Aさんが所属していた企業には、Aさんから「Aさんのブログを経由して購入した人への説明や補償」を依頼しているという。
「アフィリエイトの仕組みでは、本来、サイト運営者側には購入者の特定ができません。今は会社も解雇されましたし、会社に対応をお願いしているところです」
「その対応が終わったら、警察に出頭します。ただ、今回の件が警察でどう扱われるのかは自分なりに調べてもよくわからず、適切なところに説明に行ければと思います」
ネットの医療・健康情報の信頼性については、法改正もあり、社会的にも厳しい目が向けられています。一方で、その抜け道を探すような動きもあります。収益を目的としたモラルや法令に反する情報発信を見かけたら、Twitter( @amanojerk )またはメール( japan-info@buzzfeed.com )などでご連絡ください。
Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.
