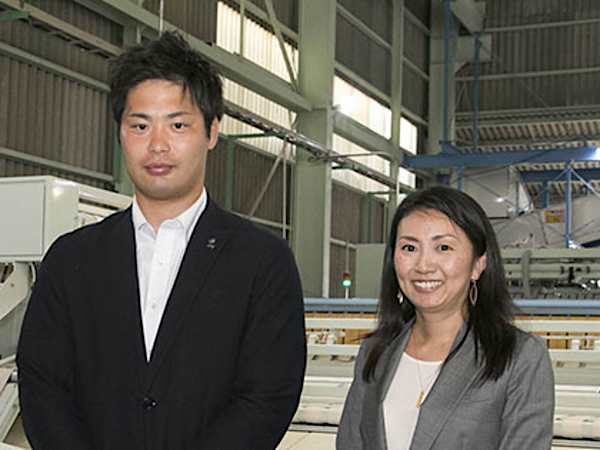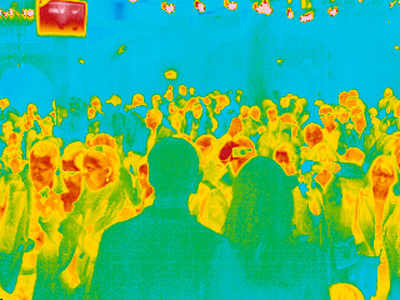9月8日(アメリカ時間)に開催された全米オープン・女子シングルス決勝で第20シードで出場した大坂なおみが、元世界ランキング1位のセリーナ・ウィリアムズにストレート勝ちという快挙を遂げた。
日本国籍の選手では男女を問わず、史上初めてのグランドスラム(四大大会)優勝だったにもかかわらず、表彰式では大坂が、ブーイングの中、涙に濡れた顔で表彰台に立ち、敗者であるセリーナが会場を静めるという異様なものになった。
アメリカでは米メディアはもちろん、普段はテニスに興味のない一般市民までが意見を言い合う事態に発展、試合から1週間近く経った今も続いている。
歴史的な対戦になると見られていた
この決勝戦は、いくつかの意味で歴史的対戦になるという期待をもって見られていた。
大坂のグランドスラム初出場は2016年。2017年の全米 オープンでもめざましい健闘を見せ、今回も注目選手の1人だった。8月末の「ニューヨーク・タイムズ・マガジン」には、大坂がライオンのたてがみのような髪をなびかせながらこちらを見つめる、インパクトある写真とともに、「Naomi Osaka’s Breakthrough Game」というタイトルの力の入った長編記事が掲載された。記事では、彼女の生い立ちや家族関係、人物像に加え、日本社会におけるハーフの扱われ方や、何をもって「日本人」とされるかなどについても突っ込んでいた。
セリーナ・ウィリアムズにとってもまた、この全米オープンには多くのものがかかっていた。母体にも危険を伴うような難産、産休を経て復帰したばかりであることに加え、この全米オープンに優勝すれば24回目のグランドスラム女子シングルス優勝になり、歴代最多優勝者であるマーガレット・コートの記録とタイになるからだ。彼女のスポンサーであるナイキなどは、開幕前から大々的な広告を打ち、期待感を盛り上げていた。
現在36歳のセリーナがグランドスラムに初優勝したのは、弱冠17歳の時だ。歴史的に白人が支配してきたテニス界で、黒人としては(アリシア・ギブソンに続く)たった2人目の女性チャンピオンだった。以来、約20年にわたり女子テニス界のトップに君臨してきた彼女が、今度は、日本人とハイチ人のハーフである20歳の選手の挑戦を受けた。
すべてはコーチのサインから始まった
すべてはセリーナのコーチが、観客席から手でサインを送った、「コーチング」と呼ばれる行為が発端だった。グランドスラムではコーチングは禁じられている。セリーナは主審から警告を受けると、「私はズルはしない。ズルをして勝つくらいなら負けた方がまし」と直訴。
ちなみにコーチングは、選手がそれを見ていたかどうかにかかわらず、グランドスラムでは警告の対象となり、セリーナのコーチは、コーチングをしていたことを(「しょっちゅう行われていること」と言いつつも)認めている。
2度目の警告はラケットを壊したことに対して出され、セリーナはポイントを失う。この直後、セリーナは再び主審に苦情を言いにいったが、その際、「あなたは私に謝罪するべきよ。私は悪いことはしていない」「あなたは私のポイントを盗んだ。泥棒だ」と言ったことが「暴言」と判断され、それが3度目の警告。今度はゲームペナルティを受け、大坂に1ゲームが加算された。
上記の3つの行為に対し、全米テニス協会は後日、セリーナに罰金US1万7000ドルを科すと発表している。
大坂はコートの中でも外でも素晴らしかった
アメリカの新聞はじめ主要メディアには今回の件でさまざまな意見が噴出しているのだが、大多数が同意していると言えるポイントは、下記3点だろう。
- 主審とセリーナの間のドラマのせいで試合の焦点がすり替わり、肝心の、大坂のグランドスラム初優勝という、彼女にとって一生に一度の祝福の時が台無しになってしまった。これは取り返しのつかないことだ。
- 表彰式での観衆のブーイングは、テニス史上、前代未聞の恥ずべき出来事で、それがたとえ大坂ではなく、主審に対するものでも許されるものではない。ニューヨーク・ポストなどは、「これほどまでにスポーツマン精神に反した出来事は、思い出そうとしてもなかなか思い出せるものではない」と強く批判している。
- 大坂の安定したプレイは文句がつけようもない。彼女は勝つべくして勝った。彼女はコートの中でも外でも素晴らしかった。
セリーナへの差別はあったのか
では、試合から1週間経った今でも人々が議論し続けているのはなぜか。議論のポイントは、大きく2つある。
- セリーナに対する審判の扱いはフェアだったか。彼女が言うように、「女だから差別的な扱いを受けた」のか?
- 仮に差別があったとして、試合中・試合後のセリーナの行動、態度は妥当だったか。
まず、「セリーナに対する主審の扱いはフェアだったか」という問題。
主審批判派の主流意見は、「審判は試合中、選手のテンションが高くなってきたときに、それをうまく抑えるのが仕事だ。ラモス主審は自分の権威を乱用して、むしろテンションをエスカレートさせ、結果的に試合を台無しにした」というものだ。アトランティック誌なども、ラモスのやり方を「悪意を感じる」と批判、CNNやワシントン・ポストも似たようなコメントを出した。
彼女の発言がペナルティを受けるべき「暴言」と言えるのどうかは意見が分かれる。だが、今回の最大のポイントは、「主審の判断に、性的差別があったと言えるか」という点だ。つまり、セリーナの言うように、女性だから厳しいジャッジを受けたのか、ということだ。
セリーナは主審に、「男子選手なら、この程度のことを言っても罰せられなかったはずだ」「もっとひどいことを言っても罰せられていない男性選手をいっぱい見てきた」「私が女だからって。そんなの正しくない」とコート横で食い下がった。
マッケンローなら最後まで試合ができなかっただろう
男女差別はタイムリーな話題でもある。
ちょうど前週、同じく全米オープンでアリゼ・コルネが着ているシャツが逆さまであることに気づき、試合中コート脇で着直したところ、主審から警告を受けた。これに対し、「男性選手なら誰でもやっていること。なんで女だと罰せられるんだ」という批判が殺到、翌日、全米テニス協会は、「適切な判断ではありませんでした」と認め、謝罪した。
試合中に審判に暴言を投げつけるテニス選手の姿は珍しくない。でも、私たちが今まで見てきたそれらの大多数は白人男性だ。
ニューヨーカーは過去に暴言を吐いてきた男性選手たちの例を挙げ、
「ラモスがこのたびセリーナに適用したような規準を用いるなら、ジョン・マッケンローは一試合も最後までやり遂げることなどできなかっただろう」
と述べている。ワシントン・ポストは、試合直後の記事で、
「ラモス主審は、女がギャーギャーわめくのに我慢がならなかったからセリーナを罰したのだ。これまで何人もの男性選手たちが大声で口汚い言葉を口にしたり、ラケットを投げつけたりしてきたではないか。でも彼らは、今回セリーナが罰されたような厳しさでは罰されてこなかった」
と述べ、いちはやくセリーナ擁護に回った。
女性は「ヒステリー」、男性は「意見をはっきり言う」
実際、この点については、多くのテニス関係者たちが、男女差別の存在を認めるコメントを出している。グランドスラムで数多くの記録を打ち立てた伝説の女性選手ビリー・ジーン・キングも、この試合終了直後に自らのツイッターで、
「女性が感情的になると『ヒステリー』と呼ばれ、罰を受ける。男性が同じことをしても『意見をはっきり言う』とみなされるだけで、なんの懲罰も受けないのに」と述べている。
9月11日に「CBS This Morning」に出演した全米テニス協会CEOのカトリーナ・アダムスも、
「ダブルスタンダードは今も存在すると私は思います。おそらくずっとあったんです。女性だからといって、何かをするたびに、男性なら背負わなくていい余計なものを背負わされるというのはおかしいですよね」
と発言している。
一方、主審のラモスは、口うるさいという評判の審判で、ジョコビッチやナダルはじめ男性の選手とももめた過去があり、「彼は男女問わず、厳しい審判だ」という意見もある。
差別され続けてきた人間は敏感になって当たり前
ただ、セリーナは女性であると同時に黒人でもある。テニスという白人中心の世界で、マイノリティとして戦ってきた。いくつかの有力紙は、人種というこのもう一つの要因に注目した議論を展開している。
例えば「ニューヨーカー」は、セリーナがこれまで繰り返し、性別、人種、そしてアグレッシブな性格ゆえに、あからさまに差別的な批判に晒されてきたことを指摘し、今回のことを彼女が、「私が私であるがゆえの差別的扱いだ」と感じたとしても驚きではないだろうと述べている。同じことを言われても全ての耳に同じように聞こえる訳ではない。差別され続けてきた人が差別に敏感になったとしても、当たり前ではないか?と。
「男がやっていいことなら女もやっていい」のか?
数多くの意見を読んで、その中で一番まっとうだと思ったのが、1980年代に活躍し、ウィンブルドンはじめ数々の記録をうちたてた名選手、マルチナ・ナブラチロワのものだ。
9月10日の「ニューヨーク・タイムズ」で彼女は、
「セリーナは、部分的には正しい。女性と男性が違う基準で罰されるということは、もちろんある。私だってそう思う。そしてそれはテニスにおいてだけではない」
と指摘した。その一方で、だからといって、男がやって許されることなら女もやっていいという考え方は賛成できるものではない、と指摘している。いつも選手が自らに問うべきなのは、
「テニスというスポーツ、そして自分の対戦相手に対し、敬意をもって接するためには、今どういう行動を取るのが正しいだろう」
ということなのだ、と。ナブラチロワ自身、試合中に頭にきて、ラケットを粉々にしたいと思ったことは何度もあるそうだ。でも、そのたび、「私の姿を子どもたちが見ている。私は、ロールモデルとして振舞わなくてはいけない」と思って我慢したと言う。
セリーナの行動・態度は妥当だった?
主審とのもめごと云々以前に、セリーナは、試合が思うように進まないことに苛立ち、感情的になり、結局のところ精神的に追い込まれて単に自滅したように見えた。試合を見ながら、「自分が負けそうになったから、審判に八つ当たりしただけでしょうが!」と思った人も少なくなかったと思う。
表彰式でのセリーナの行動や態度についても、評価が分かれる。セリーナは、ブーイングする観衆たちに、「彼女(大坂)は、いいプレイをしました。そしてこれが彼女の初めてのグランドスラムです」と切り出したあと、「今この時をできる限りいい時間にしましょう。ブーイングはやめましょう。私たちは今日あったことを乗りこえるんです。ポジティブになりましょう。なおみ、おめでとう」と言って大坂の肩を抱いた。
これについて、セリーナを「立派だった」「あれでこそ真の女王」などと言って称賛するメディアは数多かった。例えば、ニューヨーカーでは、
「これまで、セリーナは私たちにたくさんの素晴らしいものを見せてくれた。でも、彼女が長く素晴らしいキャリアの中で見せてくれた多くの勝利と同じくらいの強さで、この時の彼女は私を感動させてくれた。相手に寄り添う心のシンプルな表現によって。これは、胸が痛くなるようなものでもあり、インスパイアされるものでもあった」
というように。
大坂が涙をサンバイザーで隠そうとしたとき、セリーナが彼女に何か囁いている様子がカメラに捉えられたが、そこで何と言ったのかは映像からはわからず、報道もされていなかった。
9月12日、人気テレビ番組「エレン」に出演した大坂に、司会のエレン・デジェネレスが「あの時、セリーナは何て囁いたの?」と尋ねると、大坂は「何て言ったと思う?」と嬉しそうに笑い、
「セリーナは、『あなたのことを誇らしく思うわ』って言ってくれました。そして、『観衆たちは、あなたに向かってブーイングをしているのではないのよ』って言ってくれたんです。それを聞いて、嬉しかったし、少し気持ちが楽になりました」
と答えた。
「ものすごく日本人的よね」
セリーナの言動が論じられる中、大坂の言動もこの全米オープンを通じて、いろいろと話題になった。アメリカ在住40年になる日本人の友人は、「アメリカにいる私たちの目から見ると、大坂選手はものすごく日本人的に見えるよね」と言った。確かにそうなのだ。
彼女の振る舞い(ちょこんと頭を下げるジェスチャーとか)、喋り方、シャイな感じ、質問への受け答えの仕方(直線的でない答え方をする)などは、アメリカ人のコミュニケーションスタイルに慣れている目には「日本人的」に映る。
3歳で渡米した彼女は、もちろん流暢な英語を喋る。でも、発声方法や言葉の選び方などが非常に日本的に聞こえる。例えば、一つのセンテンスに「Um…(と口ごもる)」「I mean」「like」「a little bit」といった単語を頻繁に挟む。無意識なクセだとしても、遠慮がちに聞こえる。ボディランゲージも控えめだ。
彼女が表彰式で言った「I’m sorry it had to end like this」という言葉をどう訳すかについても、さまざまな解釈が飛び交っている。一部日本の報道で「勝ってごめんなさい」と訳されていたのを見た時、私は反射的に誤訳だと思った。彼女には何も非はないし、試合に出る以上、勝つことを目指すのは当然なのだから。むしろ「こんな終わり方になってしまったことを残念に思います」と訳した方が適切ではなかったか。
「自分より両親に何か買ってあげたい」
どんな意図で言ったのかは、結局のところ本人にしかわからない。大坂は試合の2日後、テレビ番組 Today’s Show に出演した際、まさにこの点について尋ねられ、「ただあの場では感情に圧倒されてしまって。謝らなければいけない気がしたんです」と述べている。
続いて、表彰式でのブーイングについてどう感じたか尋ねられると、こう答えた。
「少し悲しく感じました。彼らが私に対してブーイングしているのか、それとも自分たちが求めていた結果が得られなかったことに対して怒っているのかがわからなかったから。
それに、私も彼らの気持ちはわかるなと思ったんです。私も今までずっとセリーナのファンだったから。観衆の皆さんがどんなに彼女に勝ってほしいと思っていたか、私にもよくわかるから」
前出のテレビ番組「エレン」に出演した時、エレンから「賞金の US$3.8ミリオンで何を買うの?何か欲しいものあるでしょ?車でも買ったら?」と言われると、彼女は「うーん… でも何か買うなら、自分よりも両親に買ってあげたいです」と答え、スタジオの観客たちから感嘆の声がもれた。
試合では強靭な身体能力と精神力を見せながらも、コートから離れると、別人のように物腰が柔らかく、頼りないほど優しげで、恥ずかしがり屋で、おっとりしている。そのギャップが彼女の魅力だ。大坂は、これから多くの大会で勝利を収め、何度も私たちに笑顔を見せてくれるだろう。「あんなこともあったね」と笑える日がくるかもしれないし、そうだといいなと思う。今回のことをくぐり抜けて、彼女は一層強くなったはずから。 (敬称略)
渡邊裕子(わたなべ・ゆうこ):ニューヨーク在住。ハーバード大学ケネディ・スクール大学院修了。ニューヨークのジャパン・ソサエティーで各種シンポジウム、人物交流などを企画運営。地政学リスク分析の米コンサルティング会社ユーラシア・グループで日本担当ディレクターを務める。2017年7月退社、現在は約1年間の自主休業(サバティカル)中。