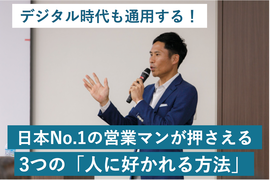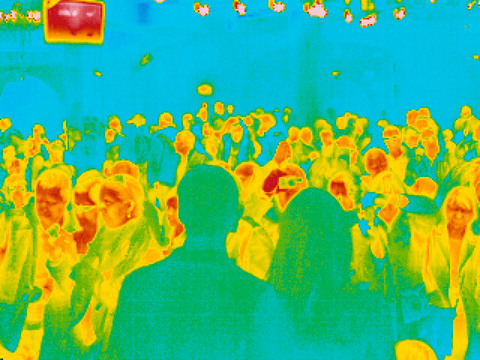スマートフォンアプリやIoTホステルを手掛ける「and factory」が6日、東証マザーズに上場する。
「スマホを軸にしたサービスを生み出す」ことを目指して2014年9月16日に創業した同社は、「手堅さ」と「スピード感」を両立し、VCから資金調達を受けず4年弱という異例のスピードで上場を実現した。
「黒字化見えていた」、VCから調達せず

社員の平均年齢は31歳。オフィス内でのイベントも頻繁に開く。
and factoryの創業者、小原崇幹(たかまさ)社長(34)は、「上場は創業時からの一つの目標でした」と話し始めた。
「and factory創業メンバーの多くが既婚者だったこともあり、彼らに前職を辞めて参画してもらう以上、できるだけ早く事業を安定させようと思っていました。金融市場にアクセスしやすく、倒産リスクを下げられる上場は、長期的な安定を目指す上で、自然な目標です」
失敗の可能性が低く、早めに利益を産めるアプリ事業から始め、1年目からEBITDA(営業利益と減価償却費の和)ベースで黒字化を達成した。IT企業のイグニスから創業資金として6000万円強の出資を受けたが、その後VCからの出資の打診は全て断り、自前で事業を育て、利益を伸ばしてきた。
「創業時点でスペシャリストを確保し、どういう段階でどこから黒字化できるかが見えていたので、VCの資金は必要ありませんでした」
成功できそうな事業をどこよりも早く事業化
小原社長がスマホを軸にしたビジネスを考え出したのは、2010年ごろだ。ウェブ広告代理店で勤務していたとき、スマホの広告が増えていくのを見て、大きな可能性を感じた。
「スマホという画期的なデバイスを中心に据え、その可能性を最大限に生かし、多角的な事業を展開する」構想を実現するため、それまでに知り合った中から、優秀だと思った10人をメンバーに加えた。
「単一事業だと市場の変化に流されやすく、安定性に劣るため、最初から多角化を念頭に、各分野で専門性を持つ知人友人に声を掛けました。アプリのスペシャリストで、マンガアプリをやりたいと思っていた人、家業が不動産で、不動産企業に勤めていた人……今手掛けている事業の枠は、創業段階である程度固まっていたとも言えます」
小原社長は自社の強みを、「ビジネスの構築力と実現力、その前提となる人材、そしてベンチャーの本質であるスピード感」と説明する。
誰も思いつかないアイデアや大きなビジョンで勝負するというより、成功の可能性の高い事業をどこよりも早く形にする。その一例が、創業事業のゲーム攻略掲示板アプリだ。
スマホゲームの市場が拡大してる時期だったが、「ゲーム事業そのものは投資がかさみ、かつ当たりはずれが大きい。人気ゲームの攻略掲示板なら、少ないリスクでシェアを取れると判断しました」
攻略掲示板アプリの広告収入で早期に黒字化し、経営基盤を整えた上で、2016年8月にホステル、2017年1月に漫画アプリ事業に参入した。
企業が持つコンテンツの活用をITで支援

2016年8月に参入したホステル事業。現在は東京と福岡で6施設を運営する。
and factory提供
漫画アプリでは、 スクウェア・エニックス を皮切りに、白泉社、集英社、ビーグリーといった大手出版社と協業し、漫画作品を配信する。
紙メディアが衰退を続ける中、デジタルを新たな収益源と捉える出版社に、and factoryが提供するのはコンテンツ配信の場だけではない。膨大な読書履歴データを分析し、それぞれの読者の傾向に合わせたお勧めコンテンツを表示するほか、読まれるコンテンツの共通点を分析し、ヒットにつながるヒントも提供している。
スマホのアプリから、空調や照明を好みに応じて操作できるIoTルームを設置したホステル事業でも、温度や明るさなどユーザーの好みを分析。いずれはチェックインと同時に、ユーザーに最適化した環境を提供することを視野に入れる。2018年7月には、H.I.S.ホテルホールディングスと業務提携し、同社が運営する「変なホテル」に、IoTルームと旅情報を配信する客室用タブレット端末を設置した。
人手不足が深刻化するホテル・ホステル業界向けに、宿泊予約管理システムもリリース。and factory 広報の佐藤裕美さんは、「出版社もホテルも、長年かけてコンテンツを蓄積してきた産業だが、その分、人間の経験で培われた“勘”に頼る部分も多く、市場の変化に対応する上での課題になっている。当社はITやデータによって、企業が持つコンテンツを最大限に活用するお手伝いができる」と語る。小原社長も、「大企業が規模を拡大する中で失ったスピード感を、補完する存在になりたい」と話した。
働く環境に投資し、離職率1.5%
小原社長は取材中、「成長の源泉は人」「全ては人に尽きる」と強調した。
その言葉を裏付けるように、この1年の社員の離職率は1.5%にとどまる。
オフィスに社長の席はない。小原社長は一人一人の評価面談に同席し、社員と一緒に昼食をとり、昼休みにはゲームで遊ぶ。
「大きい企業で働いているとき、社長が何をしているか、何を考えているか分からずに、自分はそうありたくないと思っていました。スピード感を持って物事を進めていくには、メンバーの距離の近さは必要だと思います」
社員には昼食を無料で提供し、金曜日の午後は、人気店のコーヒーバリスタに来てもらって、コーヒーを振る舞う。
働きやすい環境の構築に投資することで、優秀な人材がずっと働いてくれるなら、結果的に採用コストの抑制につながっていると思うからだ。
上場を機に、成長に対する責任も増す。68人(8月末時点)の社員も、現在の採用計画では近く100人を超す見込み。
「これからも新規事業を創出していくことを考えると、社員は数百人までは増えるでしょう。けど、それくらいまでなら、今のやり方を続けられると思います」
(文・浦上早苗、撮影・今村拓馬)