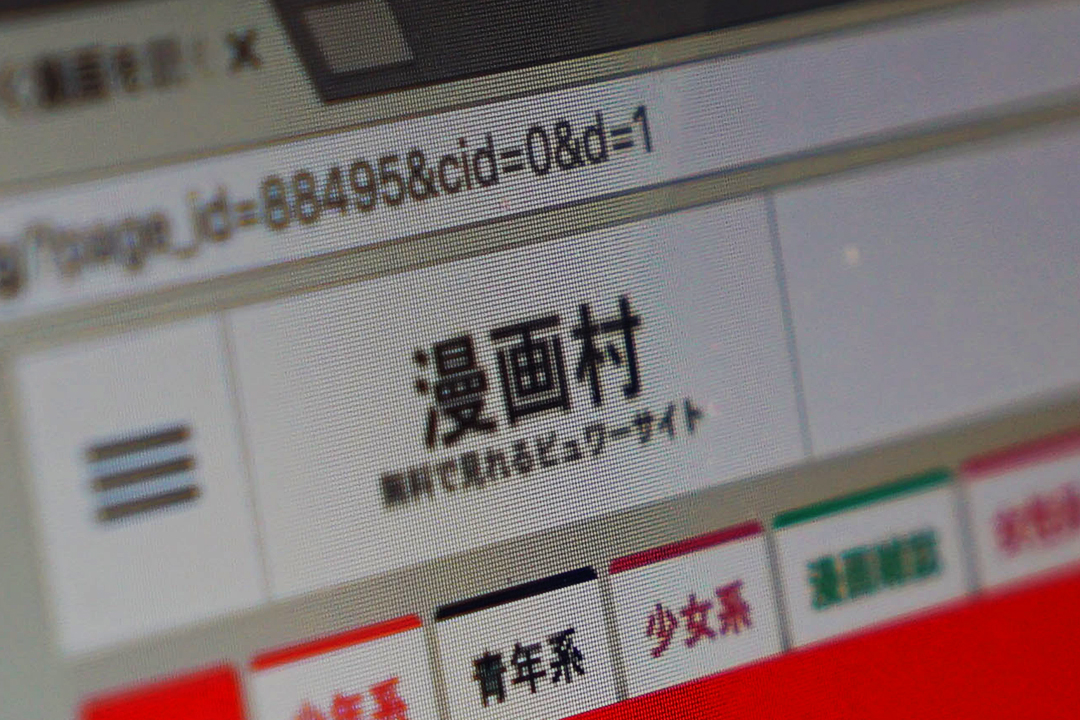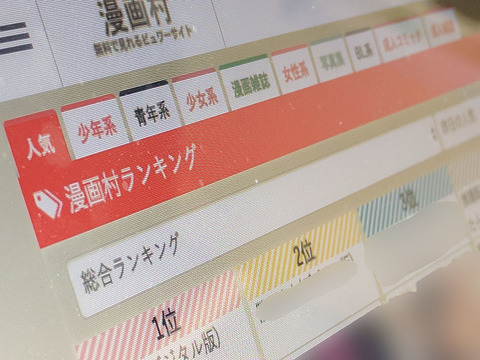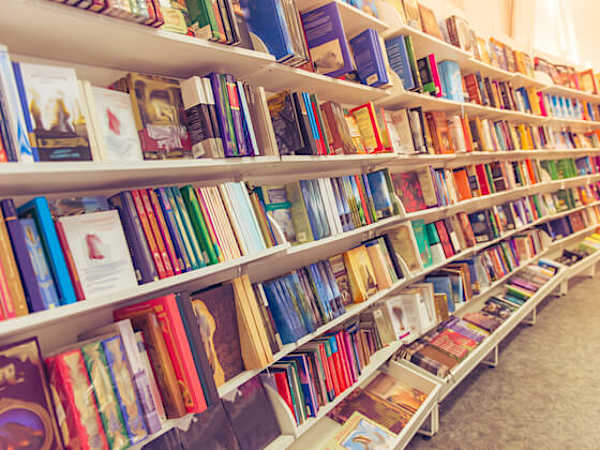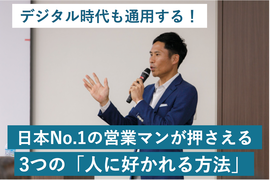2018年4月に政府の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議が「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」を発表したことを受け、「漫画村」などの海賊版サイトを対象にブロッキング(接続遮断)を実施するとしていたNTTグループは、事実上同サイトの閲覧ができなくなっていることから、ブロッキングを取りやめる方針を打ち出した。
その一方で、知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)では、ブロッキングを法制化すべきかどうかについて例外的なスピードで議論が進み、8月30日には事務局が中間とりまとめ案を提出。「ブロッキングありき」の議論ではないかと多方面から批判を呼んでいる。
憲法が保障する「通信の秘密」を侵害する可能性もあるブロッキングは、3000億円もの損害を被ったとされる漫画出版社が強引に導入を進めようとしているとの見方もある中で、事実関係を整理し、当事者による議論を深化させるため、情報法制研究所(JILIS)が9月1日、漫画出版社や漫画家を招き「著作権侵害サイトによる海賊版被害対策に関するシンポジウム」を開催した。
「出版社の対応が精密でない」は侮辱だ
知財本部タスクフォースの一員としてブロッキングの必要性を強く訴えてきたドワンゴ取締役最高技術責任者(CTO)の川上量生氏は、ブロッキングには慎重であるべきと主張する識者も数多く参加した同シンポジウムで、次のように発言した。
「通信に関わる人たちが、ブロッキングには『効果は限定的だ』『効果はあるが副作用はある』と言うなら分かるが、『効果がない』と言うのはおかしい。それでは議論が進まない」
「本当に(出版社に)被害はあったのか、ズルをしているのではないか、と疑う意見がネット上だけでなく有識者の方々からも出ている。(コンテンツ海外流通促進機構[CODA]が示した)3000億円という被害額は大きすぎるとの声もある。確かに、比較的年齢の高い方が読む漫画はさほど被害を受けていないが、漫画村の被害は10代を中心とする低年齢層のファンが多い漫画に集中している」
「出版社は何万件も削除を要請してきたが、何度繰り返しても返答すらない違法サイトも多い。その場合は諦めざるをえない。それなのに、効果がないと分かっていながらそれでも全部(削除要請を)やれと言われる。出版社はITの専門家ではないから、まだ思いついていない方法も当然ある。それを精密な対応ではないと批判するのは、侮辱だと思う」
「インターネットが生まれた当初は、国境がなくなる、治外法権のユートピアになると言われていたように、ネットにはもともと治外法権的な空間であるという思想が含まれていた。しかし、今はそうじゃない。違法行為をどこまで許すのかという議論があるべきではないのか。(そういう意味で)海賊版サイトの問題は、単なる著作権の問題ではない。ネットの自由、治外法権的なあり方を国のルールとどう折り合いをつけるのかを考えなくてはならない」
漫画村ブームが1年続いていたら破産していた
漫画市場は講談社、集英社、小学館、KADOKAWAの大手4社で売り上げの8割を占めるとされるが、今回のシンポジウムには、そうした大手とは立場の異なる中小の漫画出版社から、業界10位前後の位置にいる竹書房の竹村響執行役員も登壇。生々しい現実を語った。
「漫画村問題がビジネスに与えた影響は(大手との規模の差を考えると)少なかった。逆に言えば、我々が努力して漫画村などからすべての自社コンテンツを削除することに成功していたとしても、向こうには大してダメージがなかったというのが現実だと思う」
「とはいえ、2017年秋から18年春にかけて竹書房の漫画の売り上げは2割は減った。閉鎖後に急回復し、中には100〜120%の売り上げを記録したものもある。2007年に電子書籍の販売に着手して以来、こんなことは初めてだ。2割減というのは我々中小出版社にとって死活問題で、もし1年続いていたら破産していただろう」
「竹書房は創業以来47年間、ミリオンセラーを出したことがない。それでもやってこられた。つまり、それだけたくさんの漫画家さんと、多岐にわたる細かい仕事を積み重ねてきたわけだ。そういうビジネスをやっている中で我々がこだわってきたのは、漫画家さんに月20万円は原稿料を支払おうということ。それができなくなったら、漫画家さんが生きていけなくなる」
「我々の収益が2割減れば、(単純計算では)原稿料も16万円になる。漫画家さんたちは廃業だ。どんな可能性のある人でも、描けなくなったらすべては終わり。我々の売り上げは大手に比べたら微々たるものだが、多様性という意味で漫画文化に与える影響は小さくないのではないか」
ブロッキングの議論に漫画家は呼ばれなかった
漫画家を会員とする唯一の公益財団法人である日本漫画家協会の常任理事を務める、漫画家の赤松健氏も参加した。「(出版社に漫画を提供する側の)僕が『ブロッキング、ダメでしょ』と言ったら議論が終わってしまうだろうな」と会場の笑いを誘った上で、次のように主張した。
「(知財本部で)ブロッキングが議論されていた場に、当事者である漫画家は呼ばれなかった。呼ばれていれば、漫画村と組むとか、漫画村に代わる正規版提供サイトを出版社とつくるとか、建設的な提案ができたのではないか」
「いままでエロだ、暴力だと迫害されてきた漫画を、政府や有識者の方々が守ってくれると言い出したことには感謝したいが、議論の場から出てきた手法には不安があるというのが、漫画家側の率直な感想だ」
出版社は協力関係づくりの努力が足りない
海賊版サイトによる被害を被った側である出版社や漫画家の見解に対し、登壇したIT業界の団体や各界の専門家たちから、支持や反論、さまざまな意見が出た。
セーファーインターネット協会会長の別所直哉氏は、出版界のあり方を厳しく批判した。
「海賊版対策は、出版社だけでもISP(インターネットサービスプロバイダ)だけでもできない。みんなの協力が必要だ。通常国会は年に1回だから、法律制定には時間がかかる。しかもテクノロジーの変化は早く、それに対応する万全な法律などないので、常に後手に回って追いかけないといけない。だからこそ、民間による自主的な取り組みで素早く対応する必要がある」
「出版社が努力していないとは誰も思っていないが、協力関係をつくっていくという点では、あまり動いていないと感じる」
「なぜなら、(海賊版への対応を早くから議論し、時間をかけて協力体制を築いてきた)インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会(CIPP)の知財侵害に関する議論に参加するのは、音楽や映像の関係者ばかり。プロバイダ責任制限法の著作権関係ガイドラインに基づき、権利侵害情報に対応する著作権関係信頼性確認団体にも、出版関係の団体はゼロという現状があるからだ」
官邸は本来やるべきことをやっていない
国際大学GLOCOM客員研究員の楠正憲氏は、ドワンゴの川上氏から出版社の対応や現状について誤解を広めた張本人と皮肉られながらも、次のように持論を述べた。
「川上さんの指摘に共感するのは、この問題の本質がサイバー空間におけるロー・エンフォースメント(法執行)をどう考えていくのかであって、ブロッキングがどうこう言っている官邸のレベルが低すぎる」
「本来、(著作権法違反の)運営者を逮捕し、海賊版サイトをテイクダウンすべきなのに、それができていないことについて国は何も説明していない。サーバーを提供するクラウドフレアを呼び出し、電気通信事業法の届出義務違反で罰金を課すことはできる。やるべきことをまったくやっていない。出版社が裁判を起こす前にできることはいくらでもあるはずだ」
「出版社が3000億円の損害を受けたという主張がウソだと批判したことはない。私が批判したのは、それを鵜呑みにした(ブロッキングを実施する環境を整える必要があるとした)官邸だ。官邸による緊急対策はやり直しがきかないから、もっと慎重に動かねばならなかった」
アップルやアマゾンの協力も得て、出版界は前進している
出版社33社から成るデジタルコミック協議会の法務委員会委員長を務める村瀬拓男弁護士(用賀法律事務所)は、海賊版対策に関する情報収集や出版社間の調整に長く携わってきた経験から、苦境に置かれた出版社の現状を擁護し、著作権侵害への対策が進んでいることを明らかにした。
「出版社は雑誌を除けば、著作権の権利者ではない。一方、映画は自らが権利者で、音楽は日本音楽著作権協会(JASRAC)が主に代理し、それ以外は隣接権としてほぼ同様の権利を持っている。出版にはそうした代理団体もない。(著作権侵害について)出版各社の対応にズレが出ているのは、そうした業界のあり方の違いにもよる」
「大きな問題として、出版界が自らの権利の行使・管理についてまったく状況を把握していないという事実がある。しかし、日本レコード協会が導入した『エルマーク』と同様に、正規版の配信サイトであることを示す認定マークを、出版界もこの秋から導入することになった。ほとんどの電子書店はもちろん、アップル、アマゾン、グーグルも参加する。ライセンスを受けた配信が行われている状況を、出版社や著作権者が把握できる体制が今年中に整う」
シンポジウムでは他にも、海賊版対策の技術や法制度などさまざまなテーマで議論が行われたが、何より権利者である出版社や漫画家と、関係団体や法律家などの専門家が率直な意見を述べる場が民間の手で初めてつくられたことは、今後の道のりはまだまだ長く困難であるにせよ、評価すべきではないだろうか。
(文・川村力)