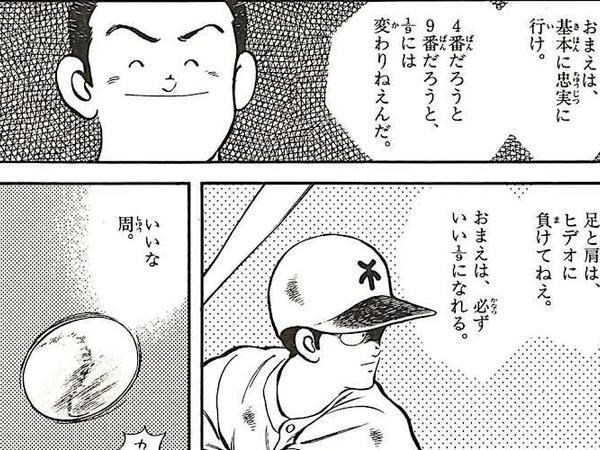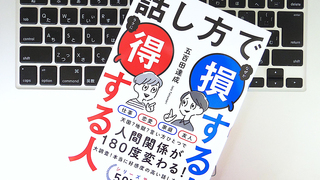小さな子どもに「何か質問はある?」と聞いてはいけない
- カテゴリー:
- SKILL

2歳から4歳の子どもは、まさに質問のかたまりです。止まりません。
就学前の幼児は、1日に平均100個の質問を両親に投げかけるそうです。
<私も娘から、学校まで車で送る間に質問攻めにあっています。車はどうして線のところで止まるの? 信号の色は誰が変えているの? どうして自転車がひかれないように壁をつくらないの? どうしてオートバイはいつも私たちの前にくるの? 娘はいま交通関係のことが知りたくてたまらないようです>
「止まらない質問」が成長によって消えてしまうワケ
ところが、子どもが成長するにつれて、こうした質問はどこかへ消えてしまいます。
学校の授業では教師が児童に「なにか質問はありませんか?」とよく尋ねますが、これは、単に形式的なものであり、子どもたちをより深い探求へと導く役割を果たしてはいません。なぜそうなっているのか?
TEDカンファレンスの創設者であるRichard Saul Wurman氏は教育システムに問題があると言っています。
「学校は、よい質問をすることではなく、正解を答えることで報酬が得られる仕組みになっている」
これは悲しむべきこと。
質問をすることで人類は、新しいことを学び、発展し、それまで存在しなかったものを生み出してきたのですから。
何か?ではなく、どんな質問がある?
しかし、朗報もあります。教育者の間で変化のきざしが見られることです。
ルイジアナ州で数学の教師をしているAndre Sasserさんがツイッターで、少し聞き方を変えたことで、大きな成果があったと報告していました。
「何か質問はありますか?」と尋ねるかわりに、Sasserさんは「どんな質問がありますか?」と尋ねることにしたのです。
これは効果がありました。
彼女はそこからさらに進めて「2つ質問をしてください」と尋ねてみたところ。
さらに大きな効果が見られました。
これなら、教師も親も同じことを試せ、子どもの好奇心を呼び覚ます独自の方法を考えることもできそうです。
安心して質問できる環境を作ることで思考力を伸ばす
『A More Beautiful Question』の著者Warren Berger氏が、子どもたちを優れた質問者、優れた思考者に変える素晴らしいヒントを教えてくれています。
第1のガイドラインは、安心して質問できる、質問が歓迎される環境を作り出すことです。
同氏は、非営利団体「Right Question Institute」のサイトが参考になると言っています。このサイトでは、質問が生まれやすいグループ演習を行うためのヒントがいくつも紹介されています。
たとえば、まず「環境汚染は問題である」のような命題を掲げます。そして子どもたちに、10分以内に10個の質問をするようにと指示します。
このとき、答えや意見を述べたり、疑義を差し挟むことは禁止されます。また、その質問は初歩的すぎるとか、稚拙すぎるといったコメントも許されません。
「正解の出し方を知っていれば学校では役に立ちます。一方、質問の仕方を知っていれば、人生を通して助けになるのです」とBerger氏は語っています。
どんな質問があるのかな?で子どもは変わる
娘が先週から幼稚園に通い始めました。
素晴らしい幼稚園なのですが、帰ってきて娘が話してくれることの中に、いくつか気になる点がありました。
たとえば昨日、娘は誇らしげに「スーパースター」の称号をもらったのだと報告してくれましたが、それは、幼稚園で静かにしていられたからだそう。
このことをどう考えればいいか、まだよくわかっていません。
私はただ、娘に、思うがままに(もちろん礼儀は正しく)質問や意見、アイデアを言える、子どもらしさを失って欲しくないと思うのです。
朝の7時25分に、娘が車や信号なんかについて絶え間なく質問を浴びせてくるとき、彼女が質問をもっと深められるように最大限の努力をしています。
「ほかにどんな質問があるのかな?」と尋ねるようにしているのです。
Image: Caiaimage/Sam Edwards (Getty Images)
Michelle Woo - Lifehacker US[原文]
訳:伊藤貴之
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
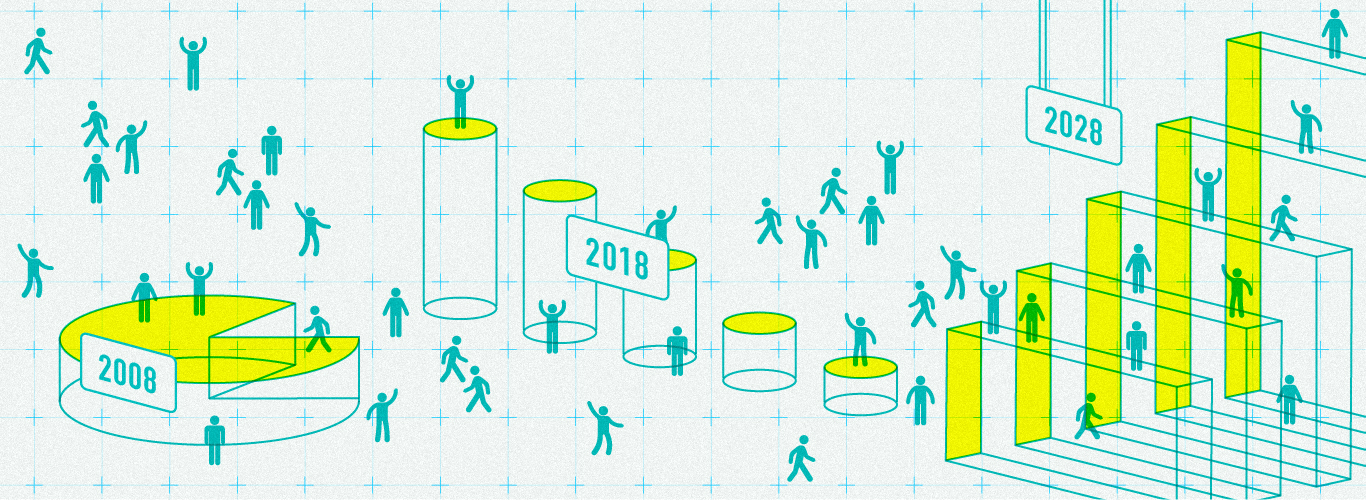


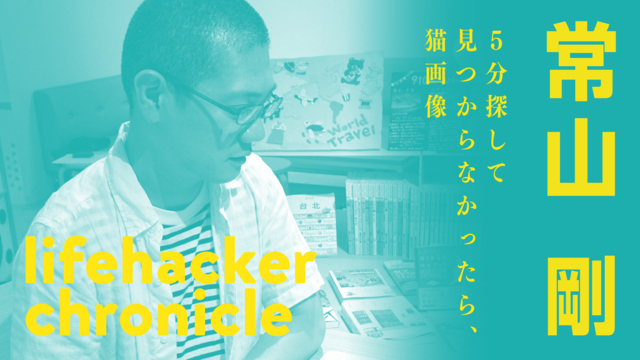


![「2000年問題」から10年、 ライフハッカー[日本版]はテック濃度高めに。BACK TO 2010](https://assets.media-platform.com/lifehacker/dist/images/2018/08/29/2010top-w640.jpg)