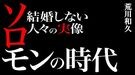「お墓の問題」に悩む人が勿体なさすぎる理由
時代に合わない伝統に縛られなくてもいい
この夏、お盆で故郷に帰った方も多いだろう。現代では、生まれ育った場所とは別の土地で暮らす人が多い。しかし、先祖からのお墓は生まれ育った土地にある。そして、日本全国で高齢化が進んでいる。いま、故郷で暮らす親や親族が亡くなったあと、「先祖代々の墓をどうするのか?」という問題に直面するケースが増えている。
だがしかし、そのお墓は本当に先祖代々からなのか? いやそれどころか、われわれはいったいいつからお墓参りをしているのか?
実は現在、われわれが行っている「骨壺が埋まる石のお墓にお参りする」という伝統は、せいぜいさかのぼって100年そこそこ。「先祖代々の墓」といっても、その「代々」はそんなに古くないのだ。だいたい、庶民が「○○家」という名字を名乗るのは明治以降だし。
フェイクニュースで広まった「お布施」や「戒名」
インド生まれの仏教が中国、朝鮮半島を経由して日本に伝わってきたのは、6世紀中頃だ。
そこから一気に飛んで、江戸時代に入る。幕府はキリシタンを禁止。すると、島原の乱(1637年)前後から、寺請制度・檀家制度が整えられていく。これは要するに、各地域の寺が「この住民は我が寺の信者であり、キリシタンではない」と証明すること。証明してもらわなければ住民はキリシタンの疑いを持たれるわけで、生死にかかわる。なので、すべての人はどこかのお寺(檀那寺)の檀家にならざるをえない、という仕組みだ。
こうして寺は行政の末端として戸籍係の役割と、キリシタン監視の役割も兼ねた。その代わりに、葬式・法要の独占権を得た。
やがて元禄の頃(1700年頃)、『宗門檀那請合之掟(しゅうもんだんなうけあいのおきて)』という文書が現れる。内容は、住民に対し「葬式、法要などを檀那寺で行え」「寺の改築・新築費を負担しろ」「お布施を払え、戒名を付けろ」「檀那寺を変えるな」……などと、やたらお寺側に有利なことが並んでいる。それもそのはず、これは偽書なのであった。今でいう“フェイクニュース”だ。