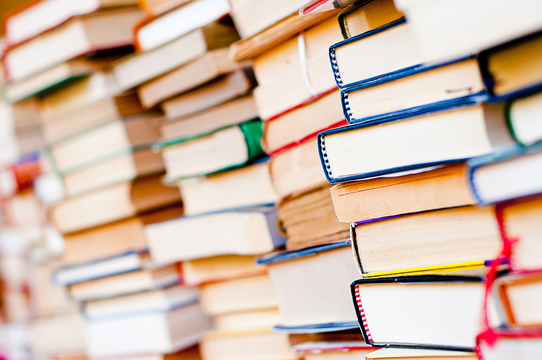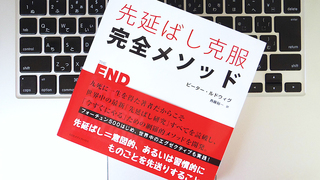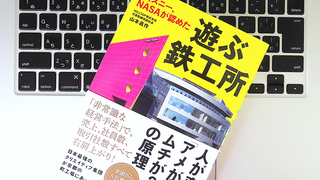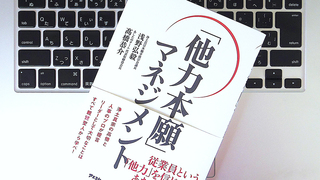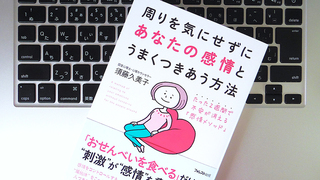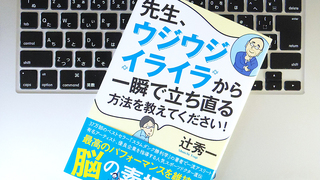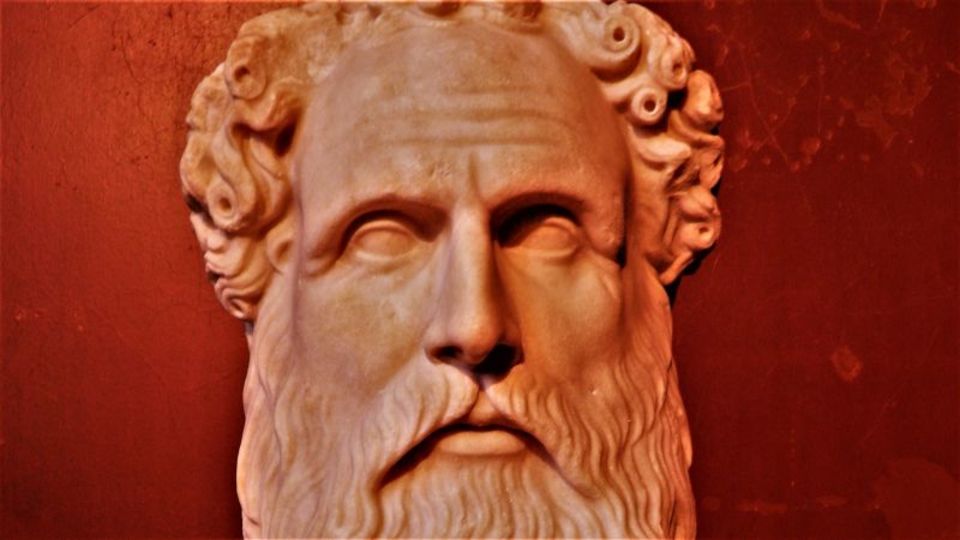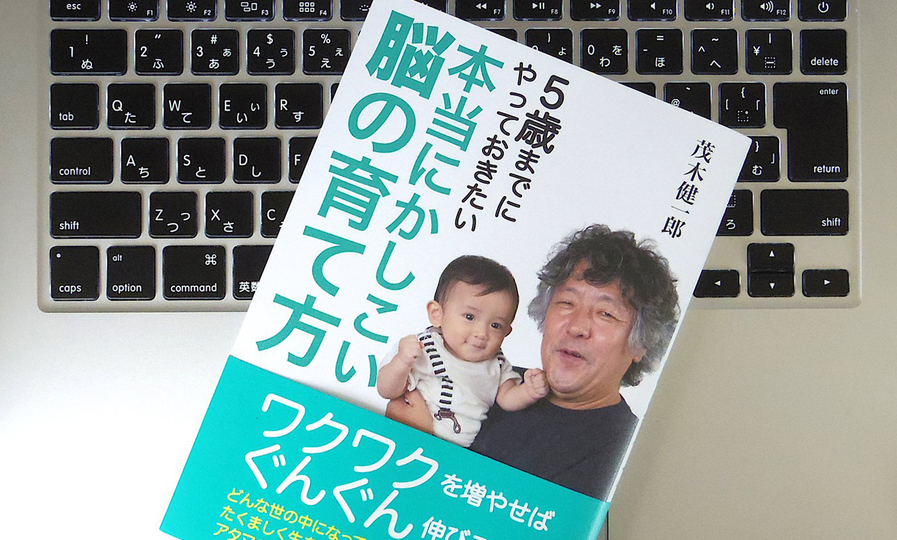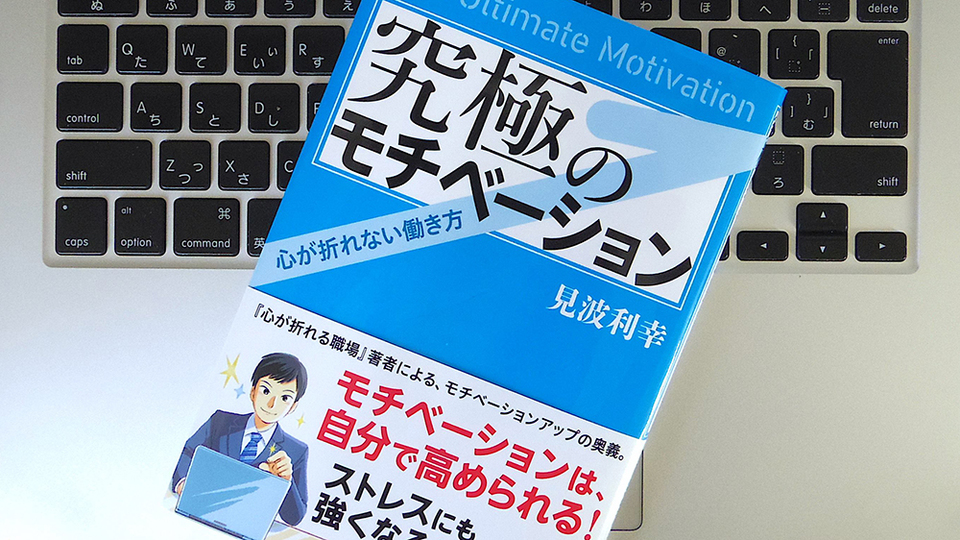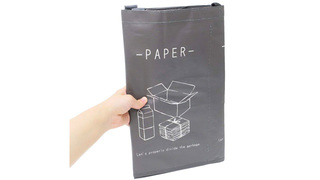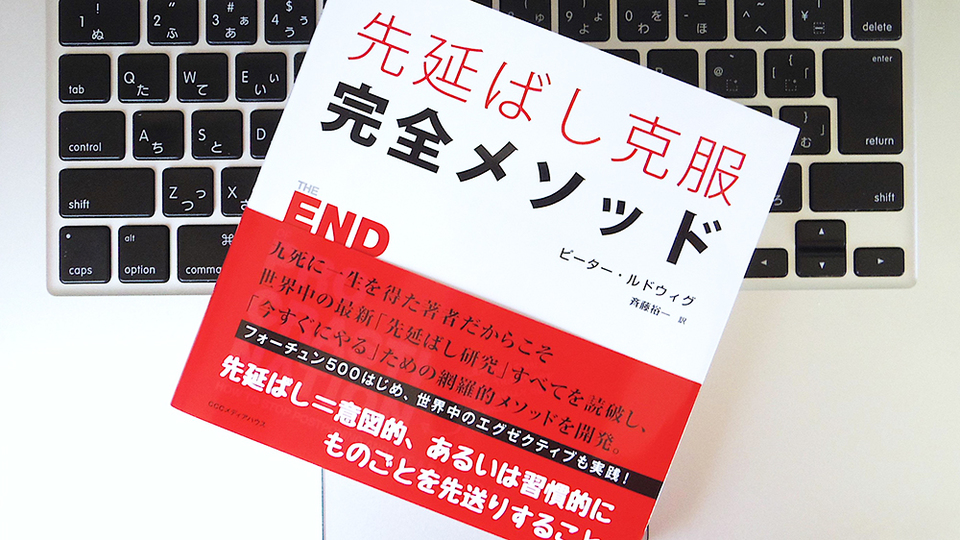
私は10年ほど前、これで人生は終わりだと覚悟した。体の半分をつかさどる脳の部位の活動が止まってしまったのだ。(中略)徐々に、自分はもう死ぬのだという現実と向き合うようになっていた。 しかし幸いにも、数日後から少しずつ正常な状態へ戻りはじめ、幸運にも 後遺症も残らなかった。生死の境を切り抜けたことは生涯で最も強烈な体験だった。しばらくしてから、あの瞬間のことを忘れないように、私はこんなふうにメモに書き込んだ。
精一杯に生きたと納得して死にたい。
この誓いを実行に移そうとしたが、それには大きな強敵に勝たなければならないことを思い知る。「先延ばし」という敵だ。(「はじめに」より)
こう振り返るのは、『先延ばし克服完全メソッド』(ピーター・ルドウィグ著、斉藤裕一訳、CCCメディアハウス)の著者。チェコ出身の科学コミュニケーター、起業家ですが、つまりは事故による瀕死状態をきっかけとして、「つい先延ばししてしまう自分」と対峙することになったわけです。
そこで著者は何人かの友人とともに、「私たちはなぜ物事を先延ばしするのか、なぜこれほど優柔不断で無能なのか」、その本質的な原因を突き止めようとしたのだそうです。そして、その研究結果を踏まえ、先延ばしと戦うための実用的なツールをまとめ上げたというのです。
つまり、そのツールを紹介したのが本書だということ。きょうは「モチベーション ーー モチベーションを高め、それを維持するには?」のなかから、いくつかのポイントを抜き出してみることにしましょう。
外からのモチベーション ―― アメとムチ
自分にとって意味のないことをしなければならないとき、どんな気持ちでしょうか。やりたくないのに、義務でしなければならないことに時間を使う際の気持ちは?
著者によれば、最近の研究から、無意味な活動は強い不快感を引き起こし、マイナスの動機づけになることが明らかになっているのだそうです。学校で詩を暗記させられるとか、目的が見えない宿題をさせられるといった作業は、嫌気しか生み出さないことになりがちということ。だとすれば、先延ばししたくなるのも当然です。
そして、ここで著者が注目しているのは「外からのモチベーション ―― 褒美と罰、アメとムチ ――」。というのもそれは、人々にこの種のことをやらせるのに使われてきたから。
「外からのモチベーション」には、いくつかの大きな欠点があるといいます。自分がしたくないことをすると、幸福感に悪影響が及び、脳内でドーパミンの分泌が減るというのです。ドーパミンは、幸福感のみならず想像力や記憶、学習能力にも影響を及ぼすため、その分泌が減るのだとしたら、たしかに問題です。
もうひとつの欠点は、外からのモチベーションが引き起こす幸福感の低下が周囲にも広がること。不満を募らせている人は、まわりの人に悪影響を与えるわけです。
封建時代の農奴は外からの動機づけで働かされていた。古代ローマのガレー船を漕いだ奴隷や、産業革命初期に工場で働いた人々もそうだった。これらの仕事に創造性はほぼ不要だったが、現代の仕事は創造性を必要とするものがほとんどだ。問題について深く考えて新しい方法で対応したり、これまでとは違う解決策を見つけ出さなければならないのだ。(48ページより)
思考や想像力をさほど必要としない仕事においても、外からのモチベーションは成果の低下を引き起こすもの。そして、モチベーションがアメとムチでも、それは変わらないのだとか。期待していた報酬が得られない場合も、罰せられるのと同様の心理的影響をもたらすのだといいます。
もちろん、ムチによって動かされると、その仕事が嫌いになることも考えられるでしょう。借り入れた住宅購入資金の返済があるから嫌でも会社を辞められないとか、上司が理由を説明せずに仕事を割り振ってくるというようなこともムチの一形態。外からの刺激に対して反感を覚えるのは自然な反応で、先延ばしの悪化にもなりうるということです。
外からのモチベーションに慣れてしまうと、主体的に働くことができなくなってしまうもの。学校の評価点がそのいい例で、卒業すると勉強するのをやめてしまうことが多いものです。ムチが消えると、自分を動機づけできなくなるのです。外からのモチベーションは主体性を封じ込め、ムチがないとなにもできないような状態にしてしまうということ。(47ページより)
内なる旅に基づくモチベーション ―― 「いま」の幸福
一方、自分がしていること、特に自分がやりたいと思ってしていることに意義を見出せるとき、最も強力な形態のモチベーションが生まれるそうです。著者いわく、それが「内なる旅に基づくモチベーション」。
このモチベーションは、自分のビジョンを持つことから生まれるもの。目標を追うことが快楽適応に影響されてしまうのに対し、ビジョンは永続的なものを表すというわけです。自分のビジョンは、「人生で最も時間を捧げたいものはなにか」という問いの答えになるものであるはず。その焦点は結果ではなく行動、目的地ではなく旅にあるということ。
そして、「内なる旅に基づくモチベーション」の最大のメリットは、それが「いま」の幸福感につながること。幸福感を得るのに、目的地までたどり着く必要はなし。外からのモチベーションというムチがもたらすネガティブな感情を味わわされる必要もなし。なぜなら自分のビジョンを基準にすることで、「いま」の幸福感 ―― 自分の現状に対する満足感 ―― が得られやすくなるから。
自分のビジョンと重なることをすると、すべてがあるべき状態にあるという感覚が生まれるというのです。しかし、それはその場所にとどまることを意味しないのだとか。なぜなら自分のビジョンと、それによるモチベーションが、自分自身を前に進ませるから。
いってみれば、自分のビジョンの実現につながる行動は、自分自身が望む行動であるということ。したがって幸福感が高まり、脳の働きも記憶力もよくなって学習能力が向上することに。そうなると、自分のビジョンの実現につながる仕事に必要なスキルが大幅に高まるわけです。
向上が向上を呼ぶこの好循環は、人の熟達を助けるものだと著者は言います。ビジョンに動機づけられている人たちが、ムチや目標では達成できないことを成し遂げられるのは、それが理由だというのです。
一流のアスリートや科学者、芸術家、実業家に関する研究は、彼らに共通する要素があることを示している。それは、行動が「フロー(流れ)の状態」になっていることだ。このフローは何かに挑戦しているときに生まれ、自分の強みとスキルが発揮されるようになる。自分がしていることに完全に没頭し、時間が止まったような感覚になる。目的を達成した後のつかの間の喜びの感情とは違い、フロー状態に達するとドーパミンの分泌が長く続くようになる。(61ページより)
フローと快楽適応に関する研究が示すのは、物質的な目標や状態から長期的な幸福感は得られないということ。長期的な幸福感は、自分にとって意義のあることをしながらビジョンの実現に向かって進む旅のなかでこそ得られるという考え方です。
なお、このアプローチは、昔から言われている「幸せは結果についてくる」という考え方とは正反対。実際には、まず初めに幸福を見つける必要があり、その幸福感のおかげで結果が得られるということです。
1952年にノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュバイツァーがこう言っている。 「成功は幸福のカギではない。幸福が成功のカギなのだ。自分がしていることを愛せれば、成功できる」(63ページより)
ところで私たちが人生においてする活動は、2種類に大別できるそうです。ひとつは、もっぱら自分のためだけにすること。たとえばそれは、生きていくための基本的ニーズを満たすための行動。著者はこれを「自己1.0」の活動と呼んでいます。
そしてもうひとつは、無私の活動。自分ではなく、他者のために真剣にする活動で、著者が「自己2.0」の活動と呼んでいるもの。これが強い感情、すなわち「意義の感情」をもたらし、「喜びの感情」と「フロー状態」とは別の第3のタイプの幸福感につながるというのです。つまり自分のビジョンに「無私」の要素と、「自己2.0」の活動を組み入れるべきだということです。(58ページより)
本書の最大の目的は、先延ばしが起こる仕組みを読者に理解してもらうこと。そのために理論的モデルを示し、先延ばしに決定的な勝利を収めるためのシンプルな実用的ツールについて説明しているのだそうです。
そして、そんな本書を、読み終えてからも折に触れて見返すようにしてほしいと著者は記しています。再度読みなおす必要はなく、ざっとページをめくってポイントを振り返るだけでいいというのです。そういう意味では、とても実用的な1冊であると言えそうです。
Photo: 印南敦史
印南敦史
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5