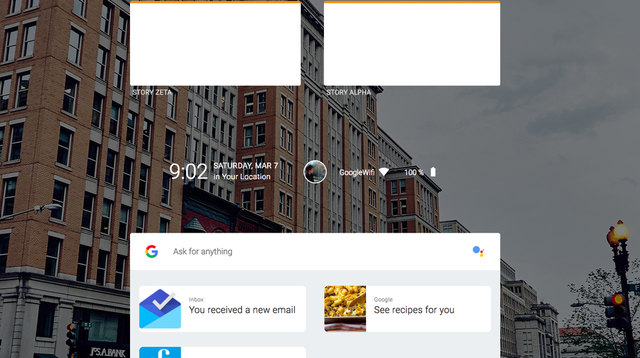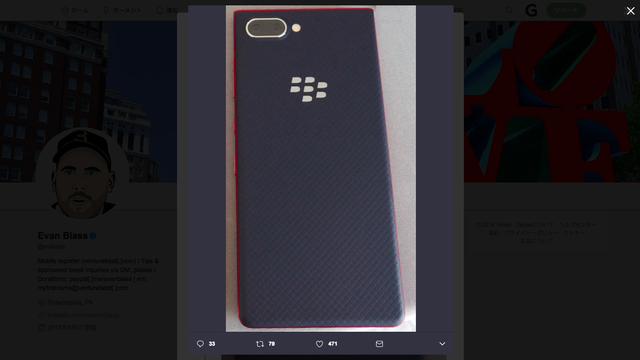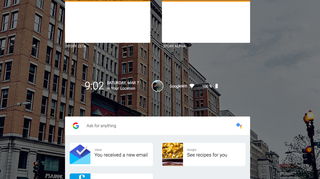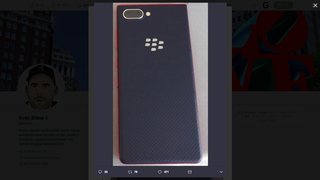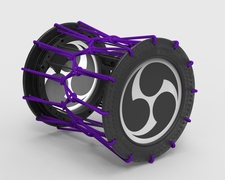いや〜、現代の子が大きくなった時が楽しみです!
ギズモードでは、これまで、さまざまなレゴ作品・レゴ文化を紹介していますが、そのたびにレゴのポテンシャルの高さに驚かされます。
最近のレゴはさらにユニークで、たとえば「レゴ® WeDo2.0」キットは、組み上げたレゴをプログラミングにより動かすことができるんです。
レゴで「プログラミング」とか、もう可能性の塊のようなキーワードですけど、例えばどんなことができるのか?というとこんな感じ。

レゴ® WeDo2.0のキットで作った救助ヘリです。モーターを制御して、ロープを上下させています。こうして動きを自分でプログラミングできちゃうなんて、レゴって本当にすごい…。
しかも…です。このレゴキットが、小学生向けの学習教材として、通信教育のZ会のプログラミング講座で受講できるんですよ。
そもそもZ会のレゴ講座ってなに?

フタを開けて、こんなに心躍る教材がいままであったでしょうか。
レゴを使った学習教材の正式名称は「Z会プログラミング講座 with LEGO® Education」。教材って聞くと問題集のようなイメージを持つかもしれませんけど、上の写真のとおり、レゴパーツが付属していて、レゴを組み立てながら「プログラミング的思考」を身につけることができます。

レゴと一緒に使うiPadアプリ「WeDo2.0」には、レゴの組み立て方や、センサー、モーターの使い方までを学ぶ「プロジェクトの入門」、それを応用して、実目的を持ってプログラミングで動かす「基礎プロジェクト」「発展プロジェクト」が用意されています。

学習には、レゴとiPadアプリ以外にも、毎月送られてくる紙教材「ワークブック」を使います。
ワークブックでは毎月2つのテーマに沿って、レゴを組み上げていきます。プログラミングの内容についての「予想」と「結果」をそれぞれ書き込んだり、プログラムを変えた結果どうなったのか?を記入したりします。正解、不正解だけではなく、実験を通じて問題を見つけ、解決へ取り組むための思考を育てます。
ということで最先端の作って学ぶ学習スタイルを体験してみましたよ。結論からいうと、むちゃくちゃハマりました。これ、かなりすごいです。
レゴを動かす基礎プロジェクトをトライ

いや〜、レゴは最高ですね!
と、パチパチとブロックを組み合わせて、ガイドに従ってまずはマシーンを組み立ててみました。作り方はiPadのアプリで確認できます。この作り方が本当にわかりやすいんです!

言葉が無く、ただイラストで「ここに入れる」的な指示が書いてあるだけ。でも、それだけでわかるんです。
実はレゴの箱を開けたときは、ワクワク感と共に若干の「骨が折れそうだな」という思いもあったんです。でも、その時の感想は大間違い。ガイドを見ながらとは言え、「なるほど!こう組むと、あの部分と連結して丈夫になるのか!」とか、「こう力が加わっていくんだな!」とか、関心と閃きの連続。簡単に楽しみながら制作できて、思わず熱中してしまいます。
大人だって「ほぉ〜!」とうなるんですから、好奇心の塊たる子どもならなおさらなんじゃないかな。

レゴが組み上がったら、モーター制御などのプログラミングもiPadで行ないます。これも簡単。モーターを動かす、モーターを右回転させる、など各役割がアイコン化されているので、ドラッグ&ドロップで並べていくだけ。プログラミングって聞くと身構えちゃいますけど、ビジュアルを付けると身近に感じられて面白いですね。さぁ、では動かしますよ!

どう!? 僕のマシン!
プログラミングしたとおりに、距離センサーでスタートを切って、障害物があればちゃんと止まるんです。うっひょ〜!楽しい〜!
その後年甲斐もなく、廊下をサーキットにしてロングコースを走らせて遊んでしまいました。いやぁ〜、作って楽しんで(学んで)、制御して楽しんで(学んで)。と、ハードとソフトの両面から、理解力を高められるのがいいところですね!
わかったぞ!これが「プログラミング的思考」か!
続いてはこの通信教育のテーマである「プログラミング的思考」を主題とした学習を受講してみました。
今回選んだのは、「月面基地はどうやって設置されるのか?」といった問い掛けに対し、ロボットを制作して、自分の思うようにプログラムする学習です。

月面基地(テーブル)に散らばった「素材A」「素材B」を回収して、スタート地点に戻ってくるというミッションです。課題の主題はプログラムを自分で改良して、ロボットを思い通りに動かすというもの。

このような感じで、矢印アイコンでモーターの回転方向を、メーターアイコンでモーターの出力レベル、そして砂時計アイコンで、モーターを指定した時間、動かす指示をだします。
無事に月面基地が完成できるかは、若干不安そうな眼差しでこちらを見つめるロボット君の活躍(と、主に僕のプログラミング)にかかっています。さて、結果は…?

ありゃ、ロボットおまえ…?
と、最初に組んだプログラムでは、「素材A」に到達できないわ、「素材B」はどこかへ持っていくわと、問題だらけ。
最初の「素材A」に届かなかったので、「モーターの出力を上げてもっと前に進めよう」とか、「素材B」を回収したら「モーターを右回転させてスタート地点に方向転換しよう」など、調整を加えて再度試します。そうか、この流れがまさにプログラミング的思考なんですね!
ということで改善した結果…。


ミッション・コンプリート! これより帰還する!
試行錯誤と改良したプログラムのおかげで、見事月面(テーブル)に残された基地素材を回収することができました。上手くいったときは思わずガッツポーズですよ!
こうして一度プログラムできると、「あれもできそう!」「これもできるかな?」「ならデザインはこうアレンジすれば…」と、頭のなかで、アイデアが連鎖的に発展していくのは、なんとも言えないワクワク感がありますね〜。失敗したときのトライ・アンド・エラーですら楽しく感じます。
学習の概念を打ち壊すZ会のレゴ講座

レゴでプログラミング教育。
たしかに、すごい楽しいです。大人の僕がリアルにまる1日没頭するほどなので、子どもならなおさらでしょう。
でも、「Z会プログラミング講座 with LEGO® Education」の凄いところは、ただ「楽しい!」だけではなく、ちゃんと「学び」が生まれて、その「成果」が実感できる構造です。
レゴとプログラムを自分で組む。上手く動かなければ、その理由を考えて対策する。この構造は本当にスマートで、「プログラミング的思考」を楽しみながら育める、素晴らしくイノベーティブなアプローチだと思います。
こうした課題解決の取り組み方は、すべての教育の基礎となるところです。プログラミング的思考が身についていれば、他の学習にも応用できて、大きなアドバンテージになるんじゃないかなぁ〜って思うんですよね。
そしてもうひとつ。「Z会プログラミング講座 with LEGO® Education」のメリットは、自宅でできる通信教育であること。教室に通う必要もなく、子どもたちが好きな時間で、好きな場所で、レゴという親しみ深いオモチャを使って学習できます。このスタイルなら、きょうだいや保護者も一緒に参加して、みんなで楽しめるに違いありません。
国語・理科・社会・英語とはまた違った、「プログラミング教育」。子どもたちには勉強とはまたちがう、ひとつの「スキル」として、楽しみながら身につけてもらえたら嬉しいですね! あと、時間があれば保護者のみなさんも、ぜひ一緒に遊んで…いや、一緒に学んでみてください。
現代的な教育ツール・プログラミング的思考は、きっと思考を良い方向へ刺激してくれます。
Z会プログラミング講座 with LEGO® Education の資料請求はこちら。
Photo: 小暮ひさのり
Source: Z会
(小暮ひさのり)