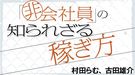ある一定の年齢になった子どもを同じ場所に集めて、単位時間を区切って同じ教科を学ばせるという、私たちが慣れ親しんでいる教育システムは、明治時代の富国強兵政策のもとに、大量の子どもに工場のように教育を施すために編み出されたシステムです。人類は誕生以来、ずっと子どもの教育をやってきたわけですから、その歴史は数万年の長さにわたります。現在の教育システムというのは、この長い歴史の中における極めて短い期間に採用されているだけの、言ってみれば例外的なシステムなんですね。
では明治維新以前はどういう教育システムだったかというと、これはいわゆる寺子屋ということになります。この寺子屋のシステムを振り返ってみると、年齢もバラバラ、学ぶ教科もバラバラということで、現在、世界で進めようとしている教育システムの方向性に近い。
つまり、近代の教育システムに慣れ親しんでいる私たちから見ると、大変「新しい」ように見えるものが、実は長い時間軸で考えてみると、「古い」ものだということです。ただし「古いもの」が「古い」まま復活したのでは、単なる後退ということになってしまいます。この時、古いシステムは、なんらかの発展的要素を含んで回帰してくる。教育システムの場合、この「発展的要素」はICTということになるわけですが、ここでは教育システムの発展についての解説にこれ以上の紙幅を割くことは止めたいと思います。
この教育システムの話は一例ですが、この動きを「過去のシステムの発展的な回帰だ」として洞察できるかどうかは、弁証法というコンセプトを知っているかどうかによって大きく変わってきます。
哲学は「クリティカルシンキング」の教科書
ビジネスパーソンが哲学を学ぶもう1つのメリットが、「批判的思考のツボを学ぶ」という点です。
哲学の歴史というのは、そのまま、それまでに世の中で言われてきたことに対する批判的考察の歴史だと言うことができます。
過去の哲学者が向き合ってきた問いは、「世界はどのように成り立っているのか」という「Whatの問い」と、「その中で私たちはどのように生きるべきなのか」という「Howの問い」の2つに整理することができます。古代ギリシア以来、ほとんどの哲学者が向き合った「問い」がすべてこの2つに収れんするにもかかわらず、これほどまでに多くの哲学者の論考が存在するということは、つまりこれらの問いに対する「決定打」と言える回答が、未だに示されていない、ということの証左でもあります。
哲学者が問いに向き合う。そして彼なりの「こうじゃないかな」という答えを打ち出す。その答えが、説得力を持つと思われれば、しばらくのあいだはその答えが世の中の「定番」として普及します。しかしそのうち、現実が変化し、定番となった回答にも粗(あら)が見えてくる……つまり、その回答では現実をうまく説明できていなかったり、現実にうまく対処できなかったりするようになるわけです。すると新しい哲学者が、「その答えって、もしかしたらダメなんじゃないの?」と批判し、別の回答を提案する。哲学の歴史はそのような「提案→批判→再提案」という流れの連続で出来上がっているわけです。