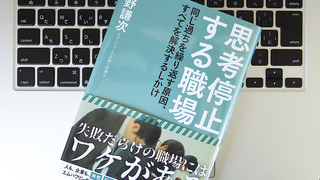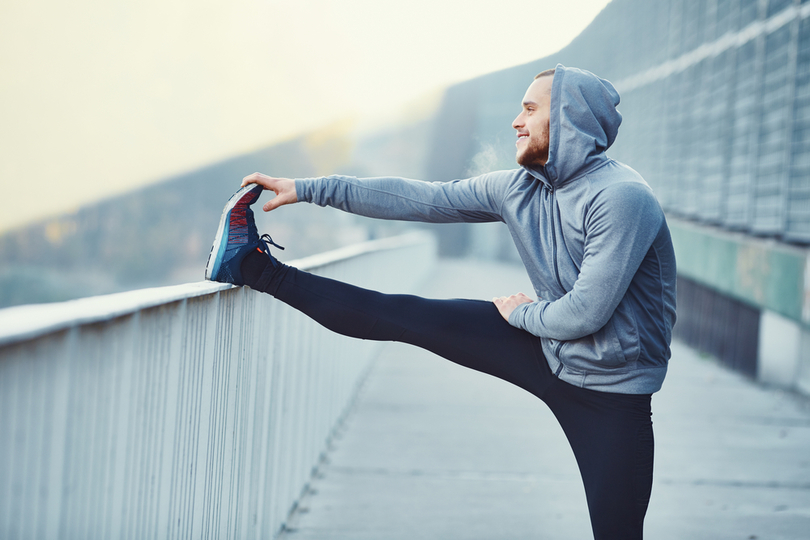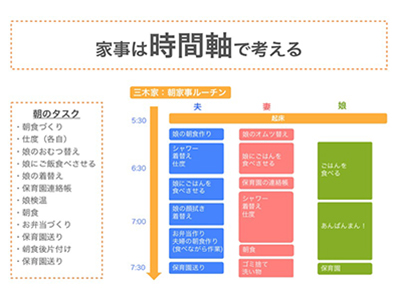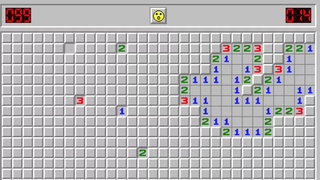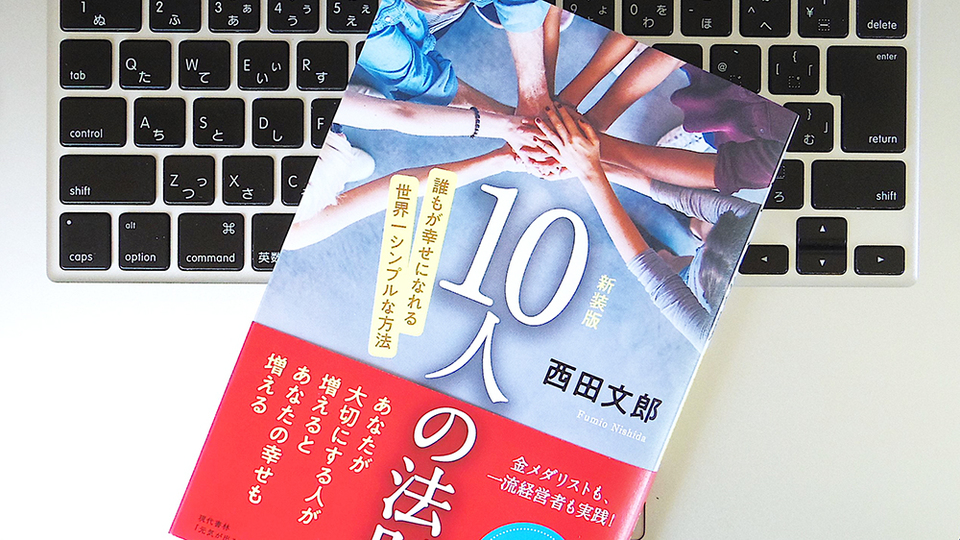
『新装版 10人の法則』(西田文郎著、現代書林)は、2008年に刊行されてロングセラーとなった同名書籍に加筆・修正した新装版。日本におけるイメージトレーニング研究・指導の先駆者的存在である著者は、「まえがき」の部分で当時のことを振り返っています。
この本がはじめて書店の棚に並んだのは2008年でした。北京オリンピックが開催された年で、日本女子ソフトボールが大方の予想を裏切って、強敵アメリカを激闘の末に下すという奇跡を実現し、日本中を感動させた年のことです。 当時、私は日本女子ソフトボールの選手たちのメンタル指導にあたっていました。優勝の瞬間、上野由岐子選手の立つマウンドに駆けよるナイン全員が、片手を空に築き上げてつくった「ナンバー1ポーズ」。 今やすっかりポピュラーになりましたが、もとはといえば、指導の中で教えた“心をひとつにするボディランゲージ”です。(中略) そのオリンピック直前、これから困難な戦いにのぞもうとしている彼女たちに、私が最後に伝えたこと。それが「10人の法則」だったのです。(「まえがき」より)
なお、「10人の法則」がどのようなものなのかについて、著者は次のように説明しています。
成功したいと思うなら、いちばん必要なのは、他人を蹴落としたり、打ち負かしたりするような強さではない。なぜなら個人の力が世の中を引っ張っていた時代とは違い、いまは人と人とのつながりが社会を動かし、変えていく時代だから。いまや成功にいちばん近いのは強さ=競争力ではなく、意識の高さや優秀な頭脳でもなく、「感謝力」。
人に感謝すると不思議な「力」がわいてくるというのですが、それはオカルトや宗教の話とは違うのだとか。家族や恋人、仲間に心からの「ありがとう」を伝えたとき、心や体に温かな力があふれてくることがありますが、それこそが自分を支えてくれる力、自分を信じる力、いわば本当の「力」だというのです。
――ウソだと思うなら、ためしに10人の恩人を訪ねて感謝してみよう。それは必ずあなた自身をこれまでのあなたから脱皮させるし、新たな力をわき出させるはずだ。(「まえがき」より)
つまりはこの考え方が、「10人の法則」だということ。きょうは第1章「成功者は孤独ではない」『10人の法則』導入編」から、「調子に乗る」ことについての考え方を引き出してみましょう。
調子に乗るか、図に乗るか
上り調子になったとき、人間は2つのタイプに分かれるものだと著者は指摘しています。いよいよ調子に乗る人と、調子には乗らず、図に乗ってしまう人がいるというのです。「調子に乗る」と「図に乗る」はほとんど同じ意味で使われることが多いようですが、厳密にいうと両者はまったく違うのだそうです。
調子に乗るとは、「勢いづく」ことで、図に乗るとは、「いい気になってつけあがる」こと。いい気になって思い上がり、のぼせ上がり、増長しているのが図に乗った人間だというわけです。
ちょっと調子がよくなると、ほとんどの人が「自分は優秀だ」と誤解しはじめるもの。しかし「自分はデキる」と思っている人間に、本当にデキる人はいないし、「自分は優秀だ」と考えている人間に、本当に優秀な人がいたためしはないといいます。
自己満足は、未来へ進む力を奪います。 スポーツメンタルの指導経験から、はっきり断言できますが、本当にデキる人間、本当に優秀な人間は、間違いなく「自分はまだまだである」と思っています。謙虚だからではありません。いつも未来の目標に目が向いていて、それと現在の自分を比べているので、「まだまだ」としか思えないのです。(19ページより)
ちょっと調子が上向いていい気になり、「俺はデキる」「俺は優秀だ」などと思うのは、逆に優秀でない証拠。そんなことを思いはじめたら、能力は間違いなくそこで止まると著者は断言しています。そこが自分の限界になってしまうからこそ、志は高く持たなければならないということ。
調子に乗り、勢いづいている人のところへは、人が寄ってくるもの。人は勢いのあるものが好きで、未来へ向かって勢いよく流れているものに魅力を感じ、本能的にそこに集まるというのです。
人が集まるということは、チャンスや才能が集まるということであり、イヤでもツキが寄ってくるということ。ただし、ひとりでは絶対に勢いには乗れないもの。調子に乗って勢いづくには、未来のイメージを分かち合い、支えてくれる仲間が必要だということです。
一方、図に乗る人はひとりでも十分。というよりも、ひとりでなければ図には乗れないもの。そのうえ図に乗っていると、まわりの反感を買い、嫌われ、だんだんひとりぼっちになっていくものでもあります。ところが、孤独ほど人の運勢を悪くするものはないと著者はいいます。「孤独なのにツいている」「ひとりぼっちなのに運がある」という人はいないということです。(16ページより)
ツキも運も錯覚に過ぎない
調子に乗るとは、「勢いづく」こと。 図に乗るとは、「いい気になってつけあがること」。
さきほど、そう確認しました。ただ、この2つには共通点があるのだそうです。どういうわけかどちらも、「自分は運がいい」「ツイている」と思い込んでいるというのです。
「運やツキなどは存在しない」「そんなものは非科学的なものだ」「運もツキも単なる偶然に過ぎない」、それは唯物論者の考え方。しかしその一方には、人生は意思と努力で切り開くものであり、「運だ」「ツキだ」と騒ぐのは前近代的で、依存的な自我のなせる技だと考える見方もあるといいます。
しかし著者はこの点について、この世には間違いなく運もツキもないと断言しています。「運がいい」とか「運が悪い」というのは単なる錯覚であり、我々の脳のなかにしか存在しない幻想だというのです。
でも重要なのは、その錯覚が非常に大きな力を持っているということ。この幻想が脳にあるかどうかによって、脳の働きが全然違ってくるというのです。
大成功者と呼ばれる人が、例外なく自分のことを「運がいい」「運のある人間だ」と錯覚していることがその証拠。たとえば経営の神様と呼ばれた松下幸之助さんが常々、「自分は運の強い人間だ」と語っていたのは有名な話。
火鉢屋の丁稚奉公から身を起こし、松下電器(現・パナソニック)という世界的大企業を一代で築いた人だからこそ、そう考えるのは当然かもしれません。しかし実際には、大成功したから「自分には運がある」と思ったわけではないというのです。逆に「運がある」と思っていたからこそ、成功できたということ。
松下さん自身、そのことをよく知っていたため、入社試験の面接では「あなたは自分のことを運が強い人間だと思いますか?」と必ず尋ねたのだそうです。その理由は、「自分は運がいい」という錯覚が脳のなかにあるかどうかで、その人の脳の働きがまるで違ってくることを知っていたから。
「自分は運のある人間だ」という錯覚があると、
・ 自分に自信が持てる
・ 自分のすることにも自信が出てくる
・ 脳が肯定的になり、最高のプラス思考になれる
・ 能力を制限しているマイナス思考のブロックがはずれ、脳全体が活発に働き出す
・ 成功、幸せがらくらくイメージできて、努力が苦労でなくなる
・ だから困難にぶつかっても、あきらめなくなる
(45ページより)
つまり、ここには人が成功するために必要なものがすべてあるというのです。世間には多くの能力開発や成功哲学が存在しますが、それらが目指しているものが、ここに集約されているということ。いいかえれば、松下幸之助さんのように「自分は運がある人間だ」と錯覚することさえできれば、能力開発も成功哲学も必要ないと著者はいうのです。(42ページより)
成功者は本当に孤独?
多くの人が、「成功者は孤独である」と誤解している。著者はそう指摘しています。厳しい競争を勝ち抜くには、クールでなければならず、ときには非常に徹する必要も。自分の道を信じて、どこまでも突き進もうとしたら、孤独を覚悟しなければならないというわけです。
しかし、それは逆さまだというのです。人は孤独になると、自分の道が信じられなくなるもの。つまり自分を信じるには、人に信じてもらう必要があるということ。
たしかにトップは、重大な決断をひとりで下す必要があるでしょう。まわりに気を遣っていたら、的確な判断を迅速に下せなくなるわけです。また、非情さを余儀なくされることもあるはず。重い責任がずしっとかかっているのです。けれども、ひとりで責任を負うことと、ひとりぼっちは違うもの。
大成功者の自伝や伝記の類をひも解いてみるとよくわかりますが、世間で思われているのとはまったく違って、大のつく成功者に孤独な人はまずいません。 逆に、心の通じ合った腹心の友が必ずいます。うらやましいぐらい、仕事でも仕事以外のプライベートでも、信頼できる友人をたくさん持っていて、温かくみのある人間関係を築いているのです。(54ページより)
著者は、孤独なのはむしろ会社や上司の悪口で意気投合し、愚痴をこぼしあう人たちだと指摘しています。なぜなら不平不満で盛り上がっている人たちの脳は、完全にマイナス感情に支配されているから。
脳にマイナス感情(怒りや恐れ、不安、不満、嫌悪、悲しみなどの感情)が生まれるのは、自分で自分を守ろうとするときだということ。これは、意識しておいたほうがいいことかもしれません。(53ページより)
もし人生がいろいろな意味で戦いであるなら、本書は「戦いの手引き」だといえると著者は記しています。メンタルコーチとしてさまざまな実績を積み上げてきた人物の言葉だからこそ、そこには重みを感じることができます。ここから、自分なりの戦い方を見つけてみてはいかがでしょうか。
Photo: 印南敦史
印南敦史