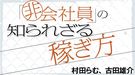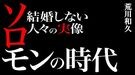なぜドイツ人は平気で長期休暇をとれるのか
法制度以上に国民性がバカンスを支えている
長期の休暇がごく普通のドイツから見ると、ゴールデンウイークの「黄金」もそれほど輝いていないかもしれない。そんなドイツの休暇事情は日本の経済に力があった頃から、「働きすぎる日本人」に対して、理想のモデルとして紹介されることがあった。
だが、当時の日本では長時間労働を気にするよりも、年功序列や終身雇用といった日本型経営の優位性を評価する声のほうが目立っていた。時代は変わって、昨今は過労死などの「ブラック」な実情が浮き彫りになり、「働き方改革」が急務となっている。
日本人がうらやむドイツの休暇事情は法律や制度など、さまざまな角度から説明されてきたが、単にシステムが優れているという理解では十分ではないだろう。ドイツの長期休暇は多岐にわたる要素との連関のなかで成り立っているためだ。今回は休暇の権利が成立してきた歴史に着目しつつ、仕事と休暇を並列に考える発想がどのように出てきたかに焦点を当てて考えてみたい。
長期休暇の法律は1963年から
今日の長期休暇を規定しているのは、1963年に施行された連邦休暇法だ。最低限24日の年休を設定することになっていて、多くの企業は30日の有給休暇を規定している。ちなみにEU加盟国に対して達成を求める「EU指令」では4週間の年次有給休暇が明記されている(EU労働時間指令、1993年)。
一方、日本では労働基準法により継続勤務年数が6.5年以上の者に対しては20日付与することが義務づけられている(6.5年未満は継続勤務年数により変動)。ただ、厚生労働省「平成 29 年就労条件総合調査の概況」によると、日本の全業種での取得率平均は49.4%で、年間10日弱しか有休を取っていないことになる。
休暇は働く側の「権利」だが、それ以上になくてはならないものだ。たとえば2006年に年金制度等の危機を受け、「バカンスを控えて老後のために貯蓄をしてみては」という趣旨の発言をした政治家がいた。が、反発が大きかったのは言うまでもない。