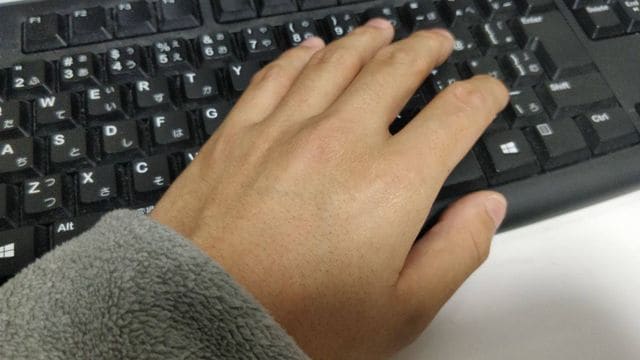特に、雇用率達成に向けて真摯に取り組んでいる企業にとっては、急速に法定雇用率の大幅な引き上げとなれば取り組み意欲が減退し、納付金を支払えばよいというあきらめの風潮を助長しかねない。
「このままだと行政指導の対象になるくらいの労働者の不足数になってしまう。企業側が徐々に増やすなんていうことをしていたら、法定雇用率が上昇していく中で、間に合わないと思いました。そのため、会社は専門に担当する場所を作って、障害者雇用にきっちりと取り組むという判断をしたのです。前からこの障害者雇用の仕事にとても興味があったので、担当ができた時、誰からも声があがらないので、私が挙手してやることになりました」
そう語るのは、同社業務運営部で担当部長を務める岡本孝伸さん(46)。2009年から、障害がある人の活用について考えてきた。発達障害の学会に所属し、発達障害の大学のゼミに参加し、障害のある社員の働く力の向上をテーマに学んでいる。
コミュニケーションを密にする
いったいどうすれば、障害者の方々に継続的に力を発揮してもらえるだろうか。
「まず発達障害の人たちと信頼関係を築くためには、コミュニケーションを密にしなければなりません。よく行っているのは、精神障害の人も発達障害の人も、1日の中で何回か面談みたいなものを入れながら聞き取りを繰り返すことです。そうすれば問題が起こった際、何が原因なのか、落ち着いて共有し誤解のないように確認することが可能になります。やはりコミュニケーションがキーになると思います」(岡本氏)
小児精神神経科医の宮尾益知氏によると、発達障害などがある人の頭の中は、さまざまな考え方がバラバラに渦巻いている状態だとのこと。そのため、仕事の際には与えたいテーマを順序立てて、事前に予告するように話すことが必要だとのことだ。
「知的障害のある人もアスペルガー症候群の人も同じですが、予告することはすごく重要です。特にいつもと違うことをするときは、あらかじめ伝えておくだけで、落ち着きが大きく変わってきます。『明日はこういうお客さんが来ます。そのとき、こういう立場の人が後ろにいますよ』とか、『今日は会議なので、ちょっといつもと違う話をしたいんだよ』ということを話しておくと、落ち着きが得られやすいのです」(岡本氏)
では、逆に障害者側は、仕事をするうえでどのようなことを懸念しているのだろうか。