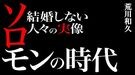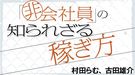全国の高校で導入中、活動記録サイトの正体
学校行事など「学力以外」が受験の判断材料に
「ポートフォリオ」という言葉からみなさんは何を連想するだろうか。元々は「書類入れ」を意味する言葉だが、転じて「アーティストが自己紹介用にまとめた作品集」や「投資家の資産構成」といった意味で用いられている。さらに最近では、学校現場や教育分野でも「ポートフォリオ」という言葉が頻繁に使われるようになった。
「JAPAN e-Portfolio」というwebサイトが2017年10月にオープンしたことがきっかけだ。文部科学省の委託事業として始まったこのサイトでは、高校生が学校内外の活動を記録し、それらを高校の先生が確認することができる。
学力以外の能力をデータ化
生徒の記録は、「探究活動」「生徒会・委員会」「学校行事」「部活動」「学校以外の活動」「留学・海外経験」「表彰・顕彰」「資格・検定」という項目に分けられる。各項目には「振り返り」を記入するスペースが設けられ、それらの活動から何を学んだのか、そして今後どんな展望を描いているのか、言語化するよう設計されている。
このe-Portfolioを、2018年2月1日現在で約1200の高校が利用。全国の高校の数は5000校なので、約4分の1が利用している計算になる。また、2018年8月から記録が大学に提供され、出願基準到達者の抽出や主体性の評価などに用いられる見通しだ。現状、導入を決めているのは78の大学(短大含む)で、早稲田や法政、明治、立教といった私立上位校、あるいは大阪大や東京医科歯科、東京外語大など国立大学が名を連ねる。
大学受験で無視できない存在になった「ポートフォリオ」が、高校の教員や高校教育の関係者の間でホットワードとなり、さまざまな研究会やメディアでこの言葉が使われているのだ。
また就職活動においても、昨今ポートフォリオに似た取り組みが広がっている。2017年度に厚生労働省と文科省が協同で開始した「キャリア・パスポート(仮称)」という事業で、「児童生徒が自らの学習活動等の学びのプロセスを記述し振り返ることができるポートフォリオ的な教材」のことだ。2018年度の文科省予算でも、このキャリア・パスポートの普及定着に予算が確保されている。
「JAPAN e-Portfolio」と「キャリア・パスポート」に共通する思想は、これまで十分に記述、記録してこなかったような学びや成長の記録を一貫して記録、蓄積し、それを大学入試や就職活動といった、次のステップへ踏み出すタイミングで生かそうということである。なぜ今、こうした取り組みが教育現場で積極的に始まっているのだろうか。