繰り返された「WELQ問題」
質の低い医療情報を組織的に大量生産していたことが社会問題になり、一部上場企業であるDeNAが健康情報サイト『WELQ』を閉鎖したのが2016年の12月。
2017年以降もネットでは『ヘルスケア大学』などのウェブサイトで、不正確な医療情報の問題が続いた。2018年3月末には大手情報サイト『マイナビウーマン』が同様の指摘を受け、「医師監修」を謳う記事など一部を非公開としている。

他方、書籍や雑誌、テレビなどでは、このような問題自体が提起されず、ウソや不正確な情報が無反省に発信され続けている事例もある。
記者(朽木)はWELQ問題をきっかけに医療記者になり、WELQ問題に端を発するネット時代の医療情報との付き合い方を取材した内容をまとめた書籍『健康を食い物にするメディアたち』を3月25日に出版したばかりだった。
しかし、このような問題が繰り返されれば「いたちごっこ」「もぐらたたき」という指摘を免れ得ないだろう。
ネット上に限らず、メディア全体に存在する、医療についてのウソや不正確な情報、医療デマ。生活者は、あるいはメディアは、これとどうやって向き合い、是正していくべきなのか。
かねてから情報発信における科学的根拠(エビデンス)の重要性を指摘する、医療政策学者でカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)内科学助教授(医師)の津川友介氏に話を聞いた。
医療デマの原因の一つは「市場の歪み」

東北大学医学部卒、ハーバード大学で修士号(MPH)および博士号(PhD)を取得。聖路加国際病院、世界銀行、ハーバード大学勤務を経て、2017年から現職。著書に『「原因と結果」の経済学:データから真実を見抜く思考法』(ダイヤモンド社、中室牧子氏と共著)、後述する『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』(東洋経済新報社)。ブログ「医療政策学×医療経済学」で医療に関する最新情報を発信している。
ーーWELQ的な手法ではウソや不正確な情報が生み出されてしまうことは、すでにヘルスケア大学などの問題で示されていたはずでした。その結果を受けて、Googleは信頼できるサイトを評価する方針に切り替えた。しかし、「信頼できる」と評価されたサイトからも、質の低い記事が出てしまいました。
これからも同じことは起きるでしょう。Googleが大きな決断をしたとはいえ、そもそもの“市場の歪み”が直ったわけではないからです。
――“市場の歪み”とは?
日本では、健康に対してお金がたくさん使われています。決して、健康への意識が低いわけでも、お金自体がないわけでもありません。健康食品やサプリメントの市場規模は約1.5兆円とも推定されています。しかし、そのお金が正しい健康情報に流れず、正しくない健康情報に流れてしまっているのです。
――だから、歪んでいる、というわけですね。
あれだけWELQが問題になっても、根本的には解決していないのです。WELQ的な手法が一番PVを稼ぐことができ、企業としては収益が上がる。この構造が変わらない限り、企業にとって同様の手法をとるインセンティブ(動機)が残り続ける。
意識的か無意識的かはともかく、このままでは問題は繰り返されるでしょう。歪んだ市場においては「社会にとって良いことをしたら収益が上がる」ように市場の仕組みを変えることが必要です。具体的には、主にメディアへのアプローチと、生活者へのアプローチの2つがあるでしょう。
メディアが持つべき矜持
――まず、メディアには何が必要ですか?
あらためてウソや不正確な情報を発信しないという矜持を持ってもらう必要があります。今の日本には、大手メディアであっても、おかしなことが起きていると私は感じます。
例えば「がんを治す奇跡の水」という効果の極めて疑わしい商品があったとして、薬機法(医薬品医療機器等法)などの法律に触れるおそれがあるため、そのような広告はできません。
しかし、「奇跡の水でがんが治った」というような本は、表現の自由の名のもとに、実際に発売されています。そしてこのような本は他メディアでも紹介され、場合によっては「本の広告」という形で、堂々と新聞やテレビに登場することがあります。
――私がウソや不正確な情報を検証できるのは「表現の自由」があるからです。一方で、この表現の自由が、ウソや不正確な情報の隠れみのになってしまう、という悩ましい状況があります。
もちろん、表現の自由は尊重されるべきですが、広告という形で提示されたら問題になり得る情報が、堂々とマスメディアに掲載されているという状況は、何らかの対策を検討する余地があるのではないでしょうか。
――たしかに、問題提起がなされないと、問題が問題として認識されないことはありそうです。
もしかしたらメディアの方の間でも、濃いグレーだと思われていることかもしれませんが、やはり問題があるのでは、という意見が集まれば、自浄作用の機運も高まるでしょう。あらためて、影響力の大きなメディアには、その社会的責任の大きさも今一度、考え直してもらいたいのです。
――ご指摘のあったような健康本についての取材をしていると、「正しいことを取り上げても売れない」という声も聞かれます。例えば「健康になりたければ野菜を食べなさい」では当たり前すぎる、と。
出版社はデザインや編集で本を売るプロともいえます。過激さや意外さを求めた本でなければ売れないという姿勢ではなく、その技術を正しい内容の本を売るために使ってほしいです。
――津川さんは4月13日に書籍『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』(東洋経済新報社)を出版予定ですが、発売前にも関わらず注目を集めています。
この書籍では、正しいことを取り上げてなお手に取ってもらえるように、工夫をしたつもりです。タイトルはキャッチーですが、内容はエビデンスに基づき、現時点でもっとも確からしい食事に関しての情報をまとめています。
入口は他の「健康本」に似せ、中では食事と健康にまつわるウソや不正確な情報をしっかり検証する。このような本がスタンダードになっていけば、いい加減な情報を淘汰することもできるのではないかと私は思っています。
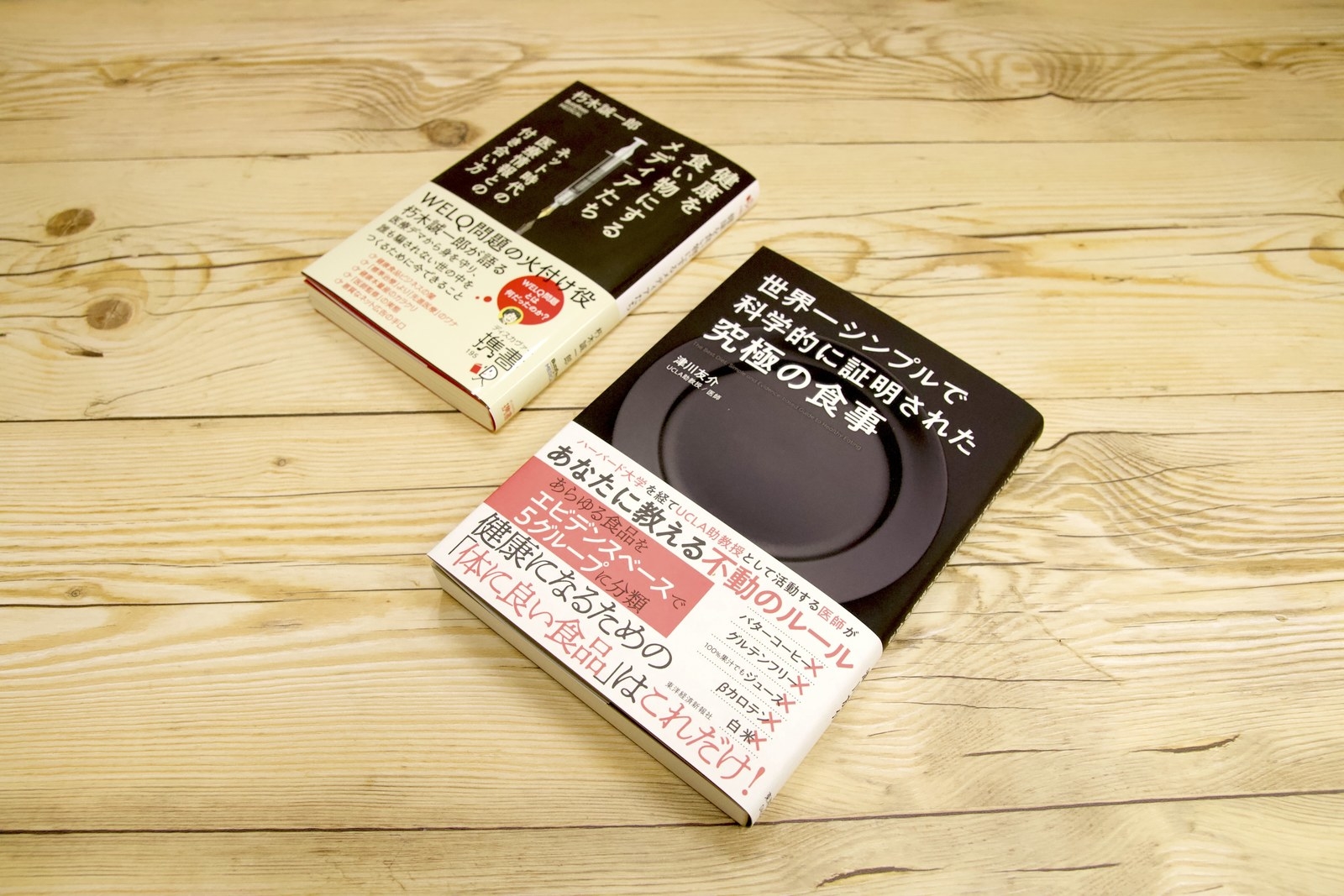
同時期に発売された二冊。
また、矜持という意味では、メディアだけでなく、医療関係者の一部に、それこそ「がんを治す水」のようなエビデンスに乏しい情報発信に加担する医療者がいるのも、残念ながら事実です。
私自身も医療関係者の一人として申し訳なく思うとともに、やはり、私たちもプロフェッショナルとしての矜持を持って、情報発信をしなければならないでしょう。
医療デマに加担しないために
――そして、生活者には何が必要ですか?
いい加減な情報を選択しないということです。いい加減な情報を観る、読む、話のタネにするというのは、ある意味では、民主主義における投票行動と同じだともいえます。
流行しているから、話題だからというだけで、吟味せずに情報を選択すると、知らないうちにウソや不正確な医療情報、医療デマを増やすことに加担してしまっている可能性があります。
なかなか意識しにくいことではありますが、情報をきちんと吟味してから話題にするということを心がけるだけで、メディア側に正しい情報を提供するインセンティブを与えることになります。
――健康は万人の関心事のため、気軽に情報を消費してしまう傾向もありそうです。
あらためて、医療情報は命に関わることもある、ということは、理解しておくべきではないでしょうか。気軽なSNSのシェアが、誰かの生き死にを左右することもあるのです。
このことについては、情報化した社会だからこそ、ある誤解が生まれているのではないか、と私は思っています。
――誤解とはどのようなものでしょうか。
「情報はあればあるほどいい」というものです。しかしもちろん、そんなことはありません。情報が100個あっても、そのうち99個が正しくなかったら、ほとんどはただのノイズ。その中から正しい情報を選べる確率は、むしろ下がってしまいます。
意志をしっかり持って、あやしい医療情報は観ない、読まない、話題にしない、周りの人に薦めないという選択をすることが、正しい情報を生み出す環境を育みます。
――とはいえ、情報を取捨選択するのも、簡単ではありません。
朽木さんが本の中で紹介した「5W2H」は有効でしょう。What(何の情報か)・Who(誰からの情報か)・Where(どこにある情報か)・When(いつの情報か)・How much(いくらか、数字のトリックはないか)・Why(何のための情報か)・How(どのように発信された情報か)を検証するというものでしたよね。
特にWhatについては、因果関係の有無、「つまりAだからBと言えるのか」「BだからAなのではないか」あるいは「AだからCで、CだからBなのではないか」を判断できる力が身につくと、騙されにくくなるはずです。
とはいえ、一般の生活者の方々が医療情報を細部までつぶさに検証するというのは、現実的ではない場合もあるでしょう。
そこで、信頼できる組織や人を複数、候補にしておき、比較しながらそこから発信される情報のみを参考にするという方法もおすすめしています。それでもわからないことは、病院で医師に質問するというのが、一番だと私は思います。
正しい情報を望む人が、それぞれの持ち場で
――医療情報の問題は、メディアと生活者の両方にアプローチが必要、ということですね。
はい。他にも、例えば本を売る書店であれば、いい加減な本は置かないという選択もできるはずですよね。あるいは、検索エンジンであるGoogleは、いい加減な情報を掲載するウェブサイトを目につくところから外す、という選択をしたわけです。
それぞれが自分の立場で、社会に害をなすようなことをしないと決めて行動する。そうすれば、市場の歪みは直すことができます。
そのときのポイントは、どれか一つだけでは、効果に乏しいということ。アプローチを組み合わせて、生活者は自衛をしながら、メディアに自浄作用を促すことが今、必要です。
津川友介氏の『世界一シンプルで科学的に証明された最高の食事』はこちらから。
BuzzFeed Japanの『健康を食い物にするメディアたち』はこちらから。
Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.
