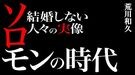中央線「立川まで複々線」はなぜできないのか
グリーン車はできるが線路は増えないまま?
東京都心から放射状に伸びるJRの路線網は、多くの区間で複々線化されている。東海道線方面では京浜東北線・東海道本線・横須賀線と3つの路線が大船までそれぞれ役割を分担する「3複線」となっており、東北方面も同様に宇都宮線(東北本線)・京浜東北線の複々線に加え、埼京線も合わせれば3路線が大宮まで多くの人を運んでいる。常磐線も取手まで複々線であり、総武線も千葉までが複々線だ。
複々線は、優等列車と各駅停車の走る線路を分けることで長距離利用者を速く都心へと運ぶとともに、短距離利用者向けの緩行線も頻繁に運転することができる。そのために、通勤ラッシュの時間帯であっても、遠方からの乗客と近距離の乗客を同時に都心に送り込むことができ、多くの通勤需要をまかなっている。
三鷹から先は複線のまま
しかし、利用者が多いにもかかわらず複々線区間が短い路線がある。中央線だ。中央線で複々線化されているのは、御茶ノ水―三鷹間の21.5km。特に混み合う郊外から新宿までの区間で考えれば13.8kmで、前記のJR各線と比べて複々線区間が特に短い。なぜ中央線の複々線は短いのだろうか。
高度成長期、国鉄各線の通勤ラッシュは年々激化し、列車ダイヤの過密化も深刻化していた。そこで、抜本的な輸送力の改善を迫られた国鉄が行ったのが「通勤五方面作戦」と呼ばれるプロジェクトである。東京都心から放射状に伸びる東海道、中央、東北、常磐、総武の5路線の通勤輸送力増強を図ることからこの名で呼ばれるプロジェクトは、1964年にその実施が国鉄常務会で承認され、以降各線で線路の増設などが実施されることとなった。