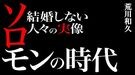都内30駅「大地震で危険度が高い」ランキング
火災や建物倒壊の危険、道路の幅にも注意
もしあなたが出先の不慣れな駅やその周辺にいるとき、大地震が起きたらどうすればいいだろうか。また自宅や会社最寄りの駅でも、駅付近はどのくらい安全なのだろうか。
南関東では今後30年以内にマグニチュード7程度の大地震の発生する確率は70%もあるとされている。大地震にともない広域火災、多数の家屋倒壊の発生も指摘されている。
大地震は突然やってくる。そこで、都内のJRと私鉄、地下鉄の全駅を対象に駅(及び駅付近)の危険度をランキングしてみた(都電、モノレール、ゆりかもめなどのAGT<新交通システム>は除く)。
5177の町丁目から算出
元データとして活用したのは、東京都都市整備局が2月に発表した「地震に関する地域危険度測定調査 第8回」である。おおむね5年ごとに調査しているもので、今回は都内の市街化区域5177カ所の町丁目について大地震の際の危険度を定量化して発表している。同じ町内でも1丁目と2丁目などすべて丁目ごとに分けて調査しているので、精度が高い。
火災危険度、建物倒壊危険度、災害時活動困難度、以上3つを考慮した総合危険度に関して5177の町丁目をそれぞれ危険の度合いによって順位付けも行っている。
火災危険度は、町丁目ごとに耐火性の低い木造建造物の密集度合いなどにより、その地域内での出火の危険性と延焼の危険性。建物倒壊危険度は、地盤の揺れやすさや建物の種類、密集度による地域内の建物全倒壊数予測(駅舎や駅施設の倒壊危険度ではない)。活動困難度は、道路の幅や広い道路までの到達困難度による危険性などにより判定されている。
わかりやすいようにワーストの1位から85位の85地域の町丁目を危険度ランク5とし、最も危険度が少ないランク1まで全5177町丁目に対して5段階のランク分けも行っている。一部の全国紙では大きく報道されたのでご存じの方も多いと思うが、総合危険度が高い順に3地区を挙げれば、
2位 足立区千住柳町
3位 荒川区荒川6丁目
となっている。都内にあなたの自宅や会社、大切な方の学校や住まい等があれば、その町丁目がどのランクにあるのか調べてみることをおすすめしたい。一帯が火災で危険なのか、家屋倒壊で危険なのかなどもわかる。