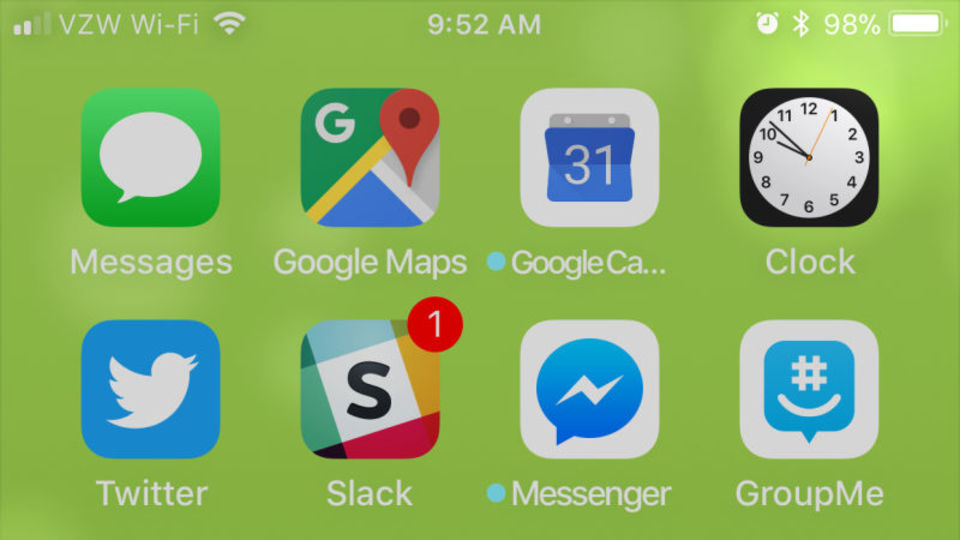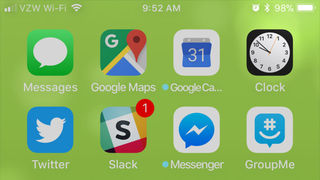賞与と昇給、どっちがメリットある?
- カテゴリー:
- JOB/BUSINESS

Appleやアメリカン航空、Home Depot(アメリカの住宅リフォーム・資材の小売チェーン)を含む米国企業は、最近米議会を通過した減税を評価し、従業員に1回の賞与を与えるという前向きなニュースを出しています(法人税率は35%から21%に引き下げられた)。The New York Timesによると、問題は昇給の代わりに賞与を出されていることです。
この傾向は1990年代にはじまりましたが、不景気が完全に回復していない間に、実際に広がっていったとThe New York Timesは報告しています。
たとえば1991年、サラリーマンの昇給が5%なのに対し、一時的な賞与やボーナス(変動する支払いとして知られているもの)に対する支出は、総報酬予算の平均3.1%を占めていました。
2017年には、一回だけの支払い(賞与やボーナス)は総報酬予算の12.7%で、昇給は2.9%でした。
企業がこのようなことをするのは賞与のほうが安上がりだからです。昇給は、従業員に毎年より多くの報酬を支払うので、時間が経つにつれてさらに増加することになります。賞与のほうがコストが少なく、与えるのが簡単ですぐに効果があります。大幅な法人税の減税というニュースのあとで、(賞与を出すという)優良企業のかたちを正しく作り出しています。
The New York TimesでPatricia Cohenは次のように書いています。
不景気が長引いていることで、経営者は固定費を増やさないようにし、従業員の配置や報酬に関しては、できるだけ柔軟な状態を求めるようになりました。かつては社内で管理されていた仕事を外注する傾向も、このような背景による経費の節約の1つです。
大事なのは、賞与の増加は賃金停滞には役に立たなかったということです。
Cohenは「インフレ調整後のフルタイムで働く男性の平均収入は、2016年のほうが1973年よりも低かったのです。給与、賃金、賞与、自社株などを含む生涯賃金は、1973年以降ほとんど下落しています」と書いています。
賃金が上がらなかった理由は賞与だけではありません。労働組合の衰退、グローバリゼーション、(インフレ調整後の)1968年当時のほうが現在よりも高い最低賃金などを含む、たくさんの要因があります。
AT&T(アメリカの大手電話会社)やウォルマートのように、一部の従業員を解雇する一方で、選ばれた従業員に賞与を与えている会社もあります。
賞与は出るけれど、昇給をしない会社に勤めている場合は、明らかに下り坂ではありませんが、やってみたほうがいいことがいくつかあります。
- 論理的に自分が昇給するべき理由を説明する(これは一時しのぎであり、賃金停滞の根本的な問題解決にはなりませんが、考えるべきことです)。
- 給与交渉ができるような社内の組合に参加する。もしくは組合をつくる(米国労働省労働統計局によると、2017年のフルタイムの賃金・給与労働者の中で、組合員の平均収入は週1,041ドルで、非組合員の平均収入は週829ドル)。
つまり、賞与自体は何も悪くありませんが、二者択一の場合は、従業員にとっては昇給のほうがいいということです。
Image: fizkes/Shutterstock.com, Federal Reserve Bank of Atlanta
Source: The New York Times, Census, The National Bureau of Economic Research, United States Department of Labor
Alicia Adamczyk - Lifehacker US[原文]
訳:的野裕子



![ライフハッカー[日本版]編集部の新生活ウィッシュリスト【キッチンツール編】](https://assets.media-platform.com/lifehacker/dist/images/2018/03/12/widhlist_top-w640.jpg)