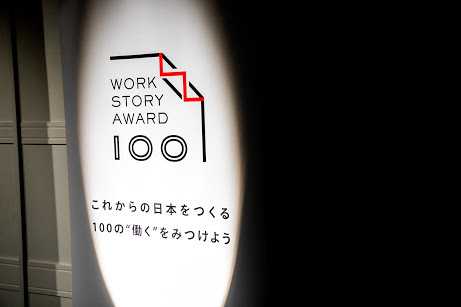富士通に学ぶ「副業社員」と企業が良好な関係を築くために必要なこと
個人的な社外活動を会社での本業に変えてしまう、という新しい働き方に富士通でチャレンジしているのはグラフィックカタリスト・ビオトープの中心人物タムラカイ氏と、タムラ氏のよき理解者であり立役者でもある上司の内田弘樹氏だ。従業員の副業を容認する企業が増えつつあるいま、副業社員と企業が双方にメリットがあるよう良好な関係を築くためのヒントを伺った。
いま「副業」に注目が集まっている
2017年11月に厚生労働省が、「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」と規定を新設したこともあり、従業員の副業を容認する企業の動きは加速している。
これを機に本格的な副業時代へと突入するとの声がある一方で、勤めながら副業することには、社員も企業も、戸惑いがあるのが現状だ。
右:サービスインテグレーション・デザイングループ 部長 内田弘樹氏 左:同グループ所属 グラフィックカタリスト/ラクガキコーチ タムラカイ氏
これからの副業の在り方を考えるために取材を申し込んだのは、富士通のグループ会社である富士通デザイン所属のタムラカイ氏。ミーティングや議論の内容をイラスト使って記録するグラフィックレコーディングを提供するクリエーター集団「グラフィックカタリスト・ビオトープ」の中心人物だ。今回は、タムラ氏の新しい働き方の"立役者"である上司の内田弘樹氏にも同席いただき、お話を伺った。
グラフィックカタリスト・ビオトープとは
グラフィックカタリスト・ビオトープは、さまざまなシンポジウムや会議、ワークショップから引く手あまたのグラフィックレコーディングを行うクリエーター集団で、富士通グループのさまざまな部署の社員が集まって活動している。
実は、会社主導で始まった活動ではなく、富士通デザインに勤めるタムラ氏の個人的な社外活動が起点となって、共感するメンバーが集まり、結果として会社の活動になったのだという。
グラフィックレコーディングは、文字での議事録とは異なり絵を描くことで、その場にいた人の想いや願いまで可視化できる。コミュニケーションが活性化する手法として注目されている。しかし、ビオトープの活動はレコーディングだけにはとどまらない。
グラフィックを活用して参加者の対話を促進するグラフィックファシリテーション、描いて考えを伝える対話手法「エモグラフィ・ダイアログ」のワークショップ開催など幅広く、2017年12月、一般社団法人at Will Workが主催したアワードプログラム「Work Story Award」では、審査員特別賞「これぞ本質だ賞」を受賞した。
個人的な社外活動が会社での「本業」に、新しい副業の在り方
タムラ氏は2003年に富士通デザインに入社し、webデザインの制作に携わっていた。ところがジョブローテーションで別分野のデザインを担当する部署へ異動することとなった。やりたいことと業務内容が一致しない。サラリーマンなら誰もが抱えたことがあるだろう悩みだ。
タムラ氏も例外ではなかったが、社外の個人的な活動にやりがいを見出した。「人生の楽しみ方をデザインする」をテーマとしたブログを書き始めたのだ。少しずつ、富士通以外の人たちとのネットワークを築いて、2014年には絵を描くことの楽しさを伝える「ラクガキ講座」を開催した。
「異動はショックなものでしたが、正直、家族もいたので会社を辞めることは考えませんでした。活動のことは『バレて問題になるよりは』と思い、あらかじめ上司には報告していましたが、個人的なことなので黙認してくれていました。そんなとき、『本を出しませんか?』という声がかかったんです」(タムラ氏)
こうして生まれたのが2015年に刊行した、「グラフィックレコーディング」を解説した『ラクガキノート術』(エイ出版社)だ。活躍の場も人脈も着実に増えた。しかし独立は考えなかったという。
「友達は、『会社を辞めて独立すれば』と言い出しましたが、僕は天邪鬼なところがあって、『独立するのは簡単だけど、会社を使うということをやってみてもいいんじゃないか』と思ったんです」(タムラ氏)
本を刊行した2015年、富士通での仕事人生にも新たな転機が訪れた。タムラ氏が入社した2003年当時からのよき先輩で理解者であった内田弘樹氏が部長をつとめる、サービスインテグレーション・デザイングループへの異動だ。
「共創のために『描くこと』を活かすためのノウハウを持っているから、これを会社で活用しませんか?」
タムラ氏は上司となった内田氏に提案を持ちかけた。個人的な社外活動を会社での本業としてやりたいという前例のない提案だった。
世の中に必要とされていることをやっている
十数年来の交流で互いに信頼関係があったからこそできた提案かもしれない。お客さまからの質問にもすぐに回答できる、物事を本質的に捉えている、などタムラ氏の頭の"良さ"に魅力を感じていたという内田氏は悩みながらも了承した。
「タムラは会社に捕らわれず、世の中に必要とされていることをやっている。そこに何かヒントがある、と感じました。いままで“デザイン”は言われたものを作る仕事でしたが、大切なのは、今の世の中をどのように“デザイン”するか? ということ。時代の本質を見つけなければいけない、思考を変えていかなければいけない、という時代に、タムラのやり方はマッチしている、と思いました」(内田氏)
タムラ氏は内田氏マネージメントのもと、「グラフィックカタリスト/ラクガキコーチ」としてグラフィックレコーディングのワークショップ開催やセミナーの講師を務めることになった。従来の”デザイン”の仕事はほとんどしていない。
これまで社外で名乗っていた肩書きを富士通デザインでのポジションに変えたのだ。「富士通の名刺もブログ名と同じ『タムラカイ』とカタカナ表記にしたい」という要望も内田氏が会社を説得して承認した。もちろん前代未聞だった。
「ただし、会社のなかで君の立場は悪くなるよ」
個人的な社外活動や副業が会社での本業に変わるという新しい働き方。社外からは注目され評価もされている。翻って社内においてはあくまで独自のポジションだ。同僚からは「何をやっているのか、よくわからない人」という眼で見られることも少なくない。
内田氏は上司としてタムラ氏の新たな働き方サポートする一方で、「ただし、会社のなかで君の立場は悪くなるよ」と正直に伝えたという。
個人的な社外活動を社内に持ち込むこと自体に対して嫌悪感を抱く人だっているだろう。就業規則も整っているわけではない。既存の人事考課制度で評価しきれないところも多分にあるはずだ。
しかしタムラ氏は「リスクも取らないといけませんよね」と笑う。
「前例のない自由なことをさせてもらうのだから、企業人としてはリスクも取らないといけませんよね。それは承知の上です。また、会社にとってのメリットやデメリットを考えて行動しなければならないと思っています。」(タムラ氏)
新しい働き方を始めるために、会社の中での評価や昇進などの枠の中におさまらない代償として、枠に守られないリスクも十分に意識しているのだ。しかしそれをサポートすることで、上司も立場を悪くするのではないか。
幹部が変わらなければならない時代
組織を維持するために、幹部は売上目標を立て、その目標に向かって社員に働いてもらわなければならない。しかしタムラ氏はほかの社員とは違う、新しいものを生み出そうとしている。
それを評価しながらも、実際問題として金銭的な意味での売上にほとんど貢献していない。タムラ氏の新しい働き方に価値を感じながらも、どういった立ち位置でタムラ氏を見守りプロデュースして行くべきか。いまも内田氏の悩みは尽きないという。
しかし内田氏は、「企業からみた活用メリットは大きい」と断言する。
「タムラは社外でやっている活動を、会社に取り入れている。そのため、タムラがセミナーの講師をやると、『富士通はこうです』という話ではなく、『一般的にはこうです』と、相手の身になった話をすることができる。話を聞く相手はとても聞きやすいんです」(内田氏)
ソリューション提案やコンサルティングにおいて、自社製品やサービスの特長を訴求するだけのセールストークでは顧客の心はつかめない。「社外のことを知らなさすぎる」という嘆きは、大手企業に共通する悩みではないだろうか。
タムラ氏のように社外で得た知見を自社の資産として活かせることができれば、企業にとっても「社員個人の社外活動や副業」はメリットとなる。社外における知名度やコミュニティでの人脈もある、タムラ氏のようなスタープレイヤーならなおさらだ。
「よく、企業は昔から『社内にスタープレイヤーが必要』というでしょ。でも、企業にはよくも悪くも枠がある。新しい挑戦が生まれたとしても、いつのまにかその枠の中におさめようという引力が働いて、スタープレイヤーはなかなか出てこないんですよ。でも、タムラは『スタープレイヤー』そのもの。タムラを利用することで、新しいエコシステムができる可能性があります」(内田氏)
実際、タムラ氏が中心となって立ち上げたグラフィックカタリスト・ビオトープは、富士通グループ内の新しいエコシステムとして有機的に機能し始めている。
「今後は、タムラのような社外で活躍している社員とよい関係を築くことが、経営戦略としても重要になるのではないでしょうか。そうした優秀な人たちと連携して新しいものを作っていかなければ、企業は成長できないという危機感もあります。1年前のことは否定して生きていくくらいのつもりで、決裁権を持つ幹部こそいろいろと実験して進化しないと」(内田氏)
「実はその実験としてタムラを利用しているだけ」と、内田氏は笑う。
人件費ではなく「研究開発費用」という考え方
新しい取り組みは売上に直接計上できないことも多い。売上に寄与する場合も、部門における数字的インパクトの小ささゆえ、採算が問題視されることもあるだろう。しかし内田氏は「新しい仕組みを作るための研究開発」だと割り切っている。
「組織を今後も存続させるためには、投資をしなければいけません。確かにタムラの活動は従来の売上金額という指標では利益になっていないかもしれませんが、新しい仕組みを作り出すために投資する価値があると考えています」(内田氏)
要は「研究開発」と同じ考え方だ。研究開発を重ねたからといってすべてが成功するわけではない。しかし、研究開発をしなければ新しいものは何も生まれない。部のなかでタムラ氏は研究開発を担っているのだ。
「私自身が他の事業部からも分かりやすく認められるアウトプットを出し、信頼を得たうえで、『タムラも役に立つんです』と言い続ければ上手くいくと思っています。『タムラはこういう活動をやっていますよ』『クライアントは喜んでいました』と、わかりやすい言葉で伝えて広めるようにしています」(内田氏)
内田氏は会社にタムラ氏を認めさせるためにも、まずは自分の業務で結果を出すことにこだわっているという。
新しい働き方をデザインしよう
タムラ氏と内田氏はいま、自分たちがやっている仕事を「働き方をデザインしている」という。
「ほかのメンバーからも、趣味とか得意なことを『会社の仕事としてやりたい』と言われたときに、『こんな道があるよ』と提示できるような会社にしたいんです。もちろん、それには面倒なこともあります。でも、それを投げだしては何も開けはしません」(内田氏)
確かに、新しい働き方には既存の制度で対応できないことが頻出する。労災や税金、権利関係まで、諸制度を変えていかなければならない。
「就業規則や人事考課についても、すでにあるルールを自分のケースに転用できないか調べて具体案を持って相談するようにしています。僕より下の世代にも新しい働き方を提示できて、彼らにとって少しでもプラスに働くなら嬉しいです」(タムラ氏)
タムラ氏がよい前例となり制度が整えば、それに続きたいと願う次世代は自社へのエンゲージメントがぐんと高まるはずだ。採用や離職率にも寄与するだろう。決して自己実現だけをわがままに考えているのではない、企業価値向上に対するタムラ氏のひたむきな想いがひしひしと伝わってくる。
内田氏は静かに語る。「この先の見えない時代では過去の成功パターンややり方に囚われず進化しないと、これからは組織がなりたたないのではないでしょうか」
働き方改革、副業、多様性と叫ばれる昨今だが、ベンチャーやスタートアップとは違って大企業では、既存の規定が邪魔をすることが少なくない。
いま企業に求められているのは、タムラ氏と内田氏のように、企業と個人の関係性と働き方をデザインし、多様な人材を容認する組織へと企業をリードしていく推進力なのではないだろうか。