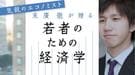「大雪時の間引き運転は不要」元運転士が激白
鉄道の大雪対策に必要な投資は進んでいる
首都圏での1月22日の大雪時、鉄道各事業者は「間引き運転」により輸送力を減らしたため、満員電車を生み出し、駅を混雑させ、むしろ混乱を拡大させた。
問題の解決に向け、筆者の長年の現場経験に基づき、雪による運行不能の要因をあぶり出すことで、間引き運転によらない対処策を提案する。
「間引き運転」はいつから広まった?
首都圏の鉄道が降雪時に間引き運転を本格的に行うようになったのは、1998年1月8日の大雪時の混乱の教訓からだ。各線で停電やパンタグラフ破損による運行停止が続出し、多数の列車が駅間で立ち往生して長時間停車となった。
特に東海道線の下りは、品川から戸塚にかけて14本もの列車が駅間で1時間以上立ち往生し、多数の乗客が車内に缶詰めとなった。川崎駅で駅員が尻押しして詰め込んだ超満員の電車が横浜駅の手前で4時間も缶詰めとなったものもあり、大きな社会問題となった。
駅間の長時間停車の原因は、計画的に間引き運転をしなかったこととされ、この直後から間引き運転が積極的に実施されるようになった。
しかし、そこに問題がある。この日の混乱のそもそもの要因を検証することなく(検証されたのかもしれないが、その報道はなかった)、起こった結果への対症療法で決着を図ったことである。さらに問題なのは、年を経るごとに、この時の対症療法的取り扱いが「教科書」となってしまい、各鉄道事業者の間で定着してしまったことだ。
事の発端を知らない鉄道事業者は、「大雪=間引き運転」という安直な対応をあたかも最初にとるべき行動と勘違いしてしまっている。これについて、これまで異を唱える者がいなかったことが非常に残念だ。
鉄道利用者は、一部の例外を除き鉄道事業者を選べない。その意味で、鉄道事業者は独占企業である。
多くの鉄道事業者がそのホームページ上で、公共交通の重要性やそれを遂行するための意気込みを記している。しかし、雪の日の間引き運転は、「安全確保」の旗印の下、本来やるべきことを怠っている行為であり、鉄道事業者が公共交通機関の重要性を認識しているとは、とうてい思えない。