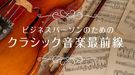AIが「偏差値65」を超えられない根本理由
「真の意味でのAI」は現時点では不可能だ
書店で、テレビで、ツイッターで、AIの二文字が踊っている。創造性あふれる小説の執筆や複雑なビジネスオペレーションの効率化など、これまで人間にしかできないと思われていた知的活動を、最新のAIが軽々と成し遂げたことを伝えるニュースは引きも切らない。
そもそもAIとは何なのか
特に、将棋や囲碁のトッププロをAIが打ち破ったニュースは驚きとともに世界に伝えられた。
ウサイン・ボルトより早く走る車やそろばん名人を凌駕する計算能力を示すコンピュータは当たり前のものとなったけれど、将棋や囲碁のように複雑でクリエイティビティが要求されるゲームは、大きな脳を持つホモ・サピエンスの専売特許のはずだった。そんな得意分野における人類最高峰がAIに敗れてしまったのだ。
AIブームは過熱するばかり。今後もAIは成長を続けることで人間の知能を追い越すというシンギュラリティ理論や、AIが人間に牙をむくことになるというAI脅威論も広まっている。果たして、AIはどこまで進化し続けるのか、現時点そして近い未来に人類に何をもたらすのか、そもそもAIとは何なのか。
本書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』は、未曽有のAIブームの中で浮かび上がる疑問符に、実際に著者が率いたプロジェクトの過程と結果をベースとして答えを出していく。数理論理学を専門とする著者は、AIが持つ原理的な限界も丁寧に解説しながら、わたしたちがAIの何を恐れるべきかを的確に示してくれる。何より興味を惹かれるのは、AIについての研究を進めていく中で、わたしたち人間の知られざる弱点が明らかになっていく過程だ。人間の外側を見つめることで、人間の輪郭がよりはっきりと浮かび上がってくる。
2011年に始まった「ロボットは東大に入れるか」という人工知能プロジェクト(通称「東ロボくん」)と、それに並行して行った日本人の読解力についての大規模調査・分析を行った経験から著者はAIをめぐる未来を以下のように要約する。