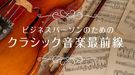川崎-熊谷を縦断!JR唯一「石炭列車」の全貌
石炭を鉄道でセメント工場に運ぶ深いワケ
神奈川、東京、埼玉と首都圏を縦断するルートで、石炭を運ぶ貨物列車が1日1本だけ走っている。じつは全国のJRでも石炭列車は今やこの1本だけという鉄道遺産的な列車である。
昭和の戦後まで、旧国鉄では数多くの石炭列車(運炭列車ともいった)が走っていた。かつては全国で数多く走っていながら今はほとんど走らなくなった列車として、旅客列車でいえばブルートレインや夜行寝台列車、機関車でいえばSLのような歴史的価値ある存在といえる。
その石炭運搬列車(以後石炭列車と表記)は、鶴見線の扇町駅(神奈川県川崎市)を出発し武蔵野線、高崎線などを経由して秩父鉄道三ヶ尻貨物駅(埼玉県熊谷市)まで走っている。三ヶ尻貨物駅に隣接して太平洋セメント熊谷工場があり、この工場へ石炭を運び込む。
この鉄道遺産的列車の実態と共に、なぜ1本だけ残ったのか、運んだ石炭が何に使われているのか、なぜトラックではなく鉄道で運んでいるのかにも迫ってみたい。すると、この1本の列車が現代の資源リサイクル問題まで関連してくるのが分かってきた。
石炭が輸送品目トップの時代もあった
1960年代、国内にエネルギー革命が起き燃料の主役が、それまでの石炭から石油や天然ガスへと大転換した。それ以前、太平洋戦争の終戦後も、石炭の需要は産業の発展と共に増え続けていた。ピークの1960年に国鉄は4063万トンの石炭を輸送している(戦前のピークは1940年の4199万トン)。数字が大きすぎてピンときにくいが、石炭を500トン満載した貨物列車が毎日200本以上運行された計算となる。
北海道の石狩炭田(空知、夕張)や釧路炭田、九州の筑豊炭田や三池炭鉱、福島県・茨城県の常磐炭田、山口県の宇部炭田や大嶺炭田など各地の炭鉱で採掘された石炭は、専用列車で港湾、工業地帯、各都市へと運ばれた。国鉄は約1万500両(1960年度)の石炭専用貨車を使用して需要に応えた。国鉄貨物の品目別でも石炭が断然トップで、総輸送量の2割以上(車扱重量換算)を石炭が占めていた。