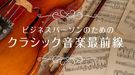今から知っておくべき「定年後再雇用」の現実
60歳以降の給与大幅減を補う給付制度とは
「これからは人生100年時代」と聞くと、老後の生活を不安に感じる方も多いことでしょう。生活資金は必要なので、老後に備えてもちろん貯蓄や投資も大切ですが、いちばん確実にリターンを得る方法はいたってシンプル。元気なうちは働き続ける、ということです。しかし、定年後は厳しい現実も……。
60歳以降の働き方は会社によって異なる
会社が定年を定める場合、60歳以上とする必要があります(高年齢者雇用安定法第8条)。そのため、60歳定年の企業が多いのですが、60歳になった社員を一律で退職させられるわけではありません。定年年齢を65歳未満に定めている会社では、従業員が65歳になるまで、次の3つの措置のいずれかを実施する必要があります。
それは、「65歳まで定年を引き上げる」「65歳までの継続雇用制度を導入する」「定年そのものを廃止する」というものです。継続雇用制度とは、本人が希望すれば、定年後も引き続いて雇用されるもので、厚生労働省の2017年「高年齢者の雇用状況」によると、継続雇用制度の導入により雇用確保措置を講じている企業の割合は80.3%となっています。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、2013年4月以降は、原則として希望者全員を対象とすることになりました。
ところで、なぜ65歳まで雇用が守られる仕組みが設けられるようになったか、おわかりでしょうか。それは、老齢厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられているからです。60歳で定年になっても、年金がもらえるのは65歳から。これでは生活に行き詰まってしまう……ということで、自ら働き生活ができるように、65歳までの雇用確保措置を企業に義務付けたのです。
ところが、政府はさらに公的年金の受け取りを始める年齢について、受給者の選択で70歳超に先送りできる制度の検討を進めており、2020年中にも関連法改正案の国会提出を目指しています。65歳はおろか、70歳までを視野に入れながら、今後は働き方を考える必要があるといえるでしょう。