人は物語を作って予測する。(…)人は頑張れば将来がわかると信じている(…)人は事実にあてはまればどんな説明も受け入れる。
(マイケル・ルイス『かくて行動経済学は生まれり』より、ダニエル・カーネマンらのメモから抜粋)
ストーリーでわかるってなんだ?
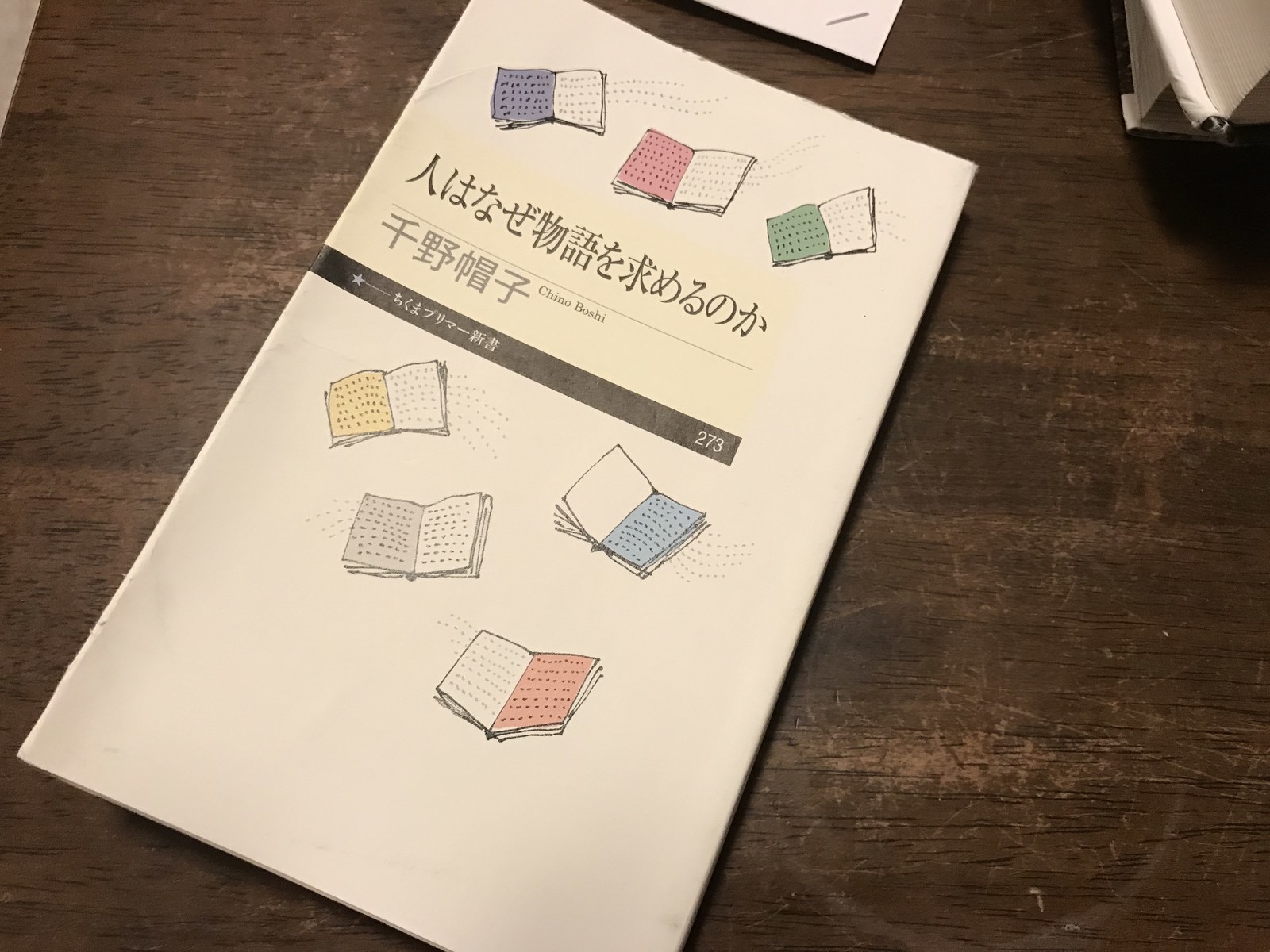
本書『人はなぜ物語を求めるのか』にならって、クイズからはじめてみよう。
問題:とある村に、伝統の雨乞い踊りがある。その踊りをすると必ず雨が降る。それは一体、どんな踊りでしょうか?
一応、答えに進む前に一言書いておくと、確かに答え通りに踊れば、絶対に雨が降る。
正解:「雨が降るまで踊り続ける踊り」。
なんだよ、と拍子抜けしただろうか?
この本のテーマに即して、重要なのは村人は雨乞いをした「から」雨が降ったという物語で認識していることだ。
人はストーリーから逃れることができない、物語る動物である。人の思考の枠組みのひとつである「物語」で私たちは苦しむこともあれば、ちょっとしたコツで救われることもあるーー。
本書の主題だ。
人生のストーリーを求めて…
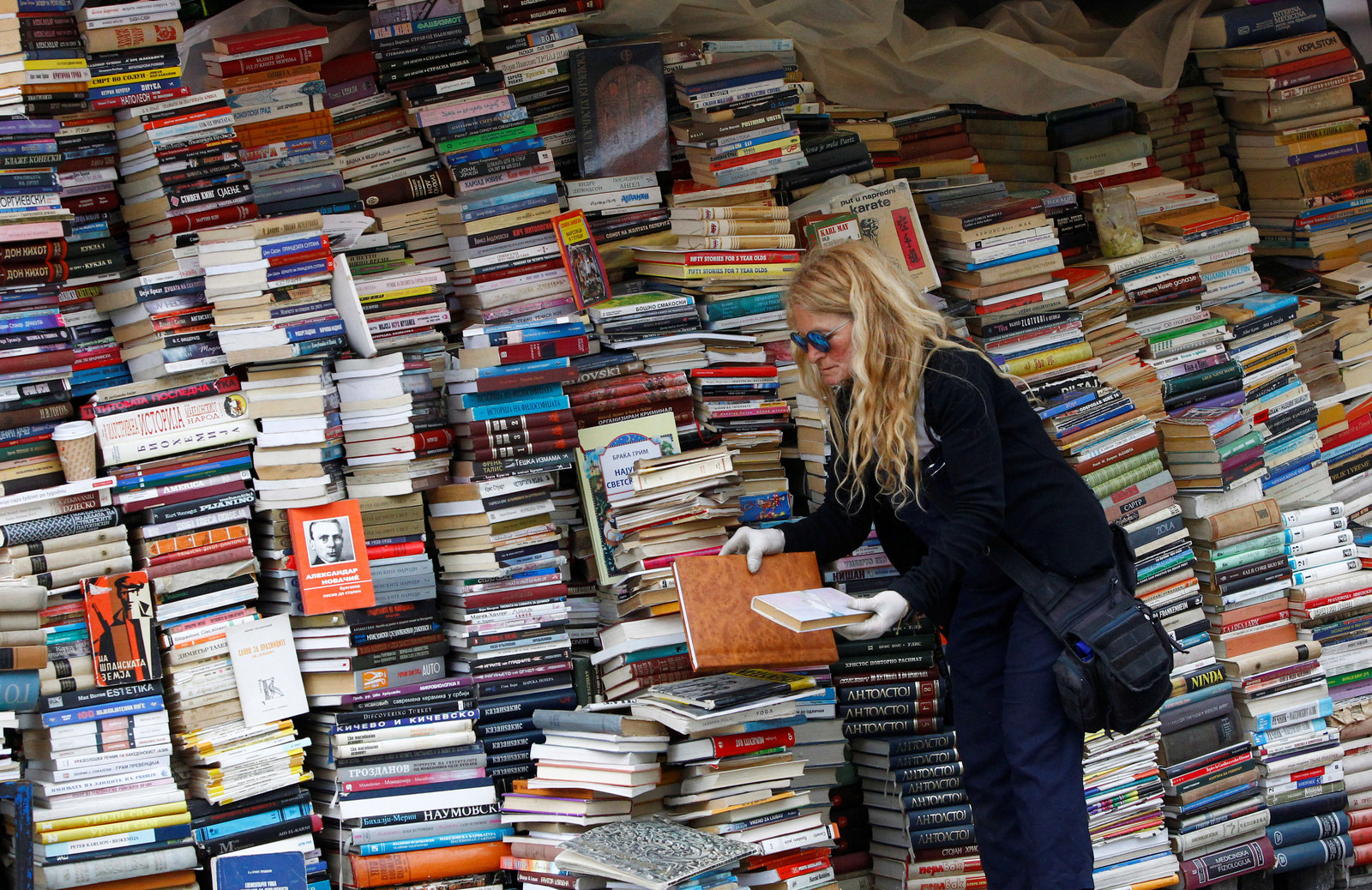
人は「なぜ」を知りたがる動物だ。
なぜ生きているのか。どうして、自分がこんな理不尽な目にあわないといけないのか。人はなにかにつけストーリーで捉え、わかろうとする。これが曲者だ。
「わかる / わかった気になる」とはなにか。
著者は文学研究にとどまらず、認知神経科学、哲学、心理学等々の研究を参照しながら、論を進めて、こう述べる。
「できごとの因果関係が納得できるものであるとき、人間はそのできごとを『わかった』と思ってしまうらしい」
人は、なにかが起きたとき、わからないことに耐えるより、ストーリーを動員して理解しようとする。
例えば、人はAのあとにBが起きると、AのせいでBが起きると認識する癖がある。こんな風に。
「ネイビーのネクタイをしたときは面接試験を突破できた。他のネクタイではなくこれでいこう」
他ならぬ私の就職活動での経験だ。ネクタイと試験結果は、よく考えればほとんど関係がない。
多少、面接官の印象は変わるかもしれないが、どう考えても他の要素のほうが合否に大きな影響を与える。それでも当時は必死に縁起を担いでいた。
前後関係に加えてーいい加減であっても、それっぽいー因果関係の説明が加わると、ストーリーはさらになめらかにつながっていく。
問いにたいして、なめらかなストーリーがあれば、人は納得してしまう。
さっきのクイズでいえば、雨乞いをしたことと、雨が降ることの関係は、村人からするとなめらかにつながっているストーリーになる。
陰謀論でも説明がないよりマシ
なぜ自分にとって不本意な状況にあるのか?特定の誰かが世界を牛耳っているせいだと考える。これは陰謀論のパターンだ。
雨乞いしかり、陰謀論しかり。たとえ荒唐無稽なストーリーでも、なめらかにつながっていると思えれば、なにも説明がないより、はるかに納得が得られる。
『説明が正しいかどうか』よりも、また『その問が妥当かどうか』よりも、僕たちはともすると、『説明があるかどうか』のほうを重視してしまう。ストーリーでそこを強引に説明してしまうことがある。
ストーリーと「〜〜すべき」論のやっかいな関係

そして、ストーリーは人間のいろんな思考の癖とともに作動する。例えば道徳である。
悪いことをやられても結果的に報われる因果応報のストーリー、悪いやつを倒してすっきりする勧善懲悪なストーリー……。
古今東西の道徳的ストーリーにみられる「あるある」だ。著者はこうした図式が頻出するのは「因果応報という図式が人間の心に巣食っている」からだ、と指摘する。
勧善懲悪の典型的なパターンは道徳的に劣った敵を倒すというもの。
人は道徳的に劣った人たちを倒すという物語ですっきりした気持ち、快楽を手にいれる(不倫スキャンダル報道が典型だ)。
因果応報、報いあれ!でも……
因果応報はどうか。これは「道徳的に収支決算のあった世界」だと言える。
人は世界は公正である「べき」だと考え、正しい行為は報われ、道徳的に間違った行為は罰せられる「べき」だと考えているのではないか。
この考え方自体が、人間の心の癖だという「公正世界」の仮説を紹介し、著者は道徳的な「べき」論とストーリーが組み合わさることの副作用に踏み込む。
公正世界は、善い結果には善いことになった原因が、その裏返しで悪い結果には悪い原因があるという世界だ。
東日本大震災、そして福島第一原発事故で考えてみよう。
当時、東京都知事だった作家・石原慎太郎さんは「天罰だと思う」と語った。彼は「日本人の悪」という因果応報のストーリーで震災、原発事故を理解しようとした。
なにか不幸なできごとが起きた以上、必ず悪い原因がある。
因果応報に基づき、ストーリーを組み立てると、甚大な災害、原発事故で理不尽な思いをした人たちになにか原因があると責めることにもなる。
犯罪被害に付きものの「被害者にも落ち度がある論」と同じパターンだ。因果応報は、被害者バッシングを肯定するストーリーにも転化するのだ。
あるいは、「このせいで不幸が起きた」とストーリーに合致する悪役を探し出してきては、叩く。
他責のストーリーは、ニュースをみていればでいくらでも見つけることができるだろう。ニュースもまた「物語」の集積である。
人はストーリーに苦しめられる
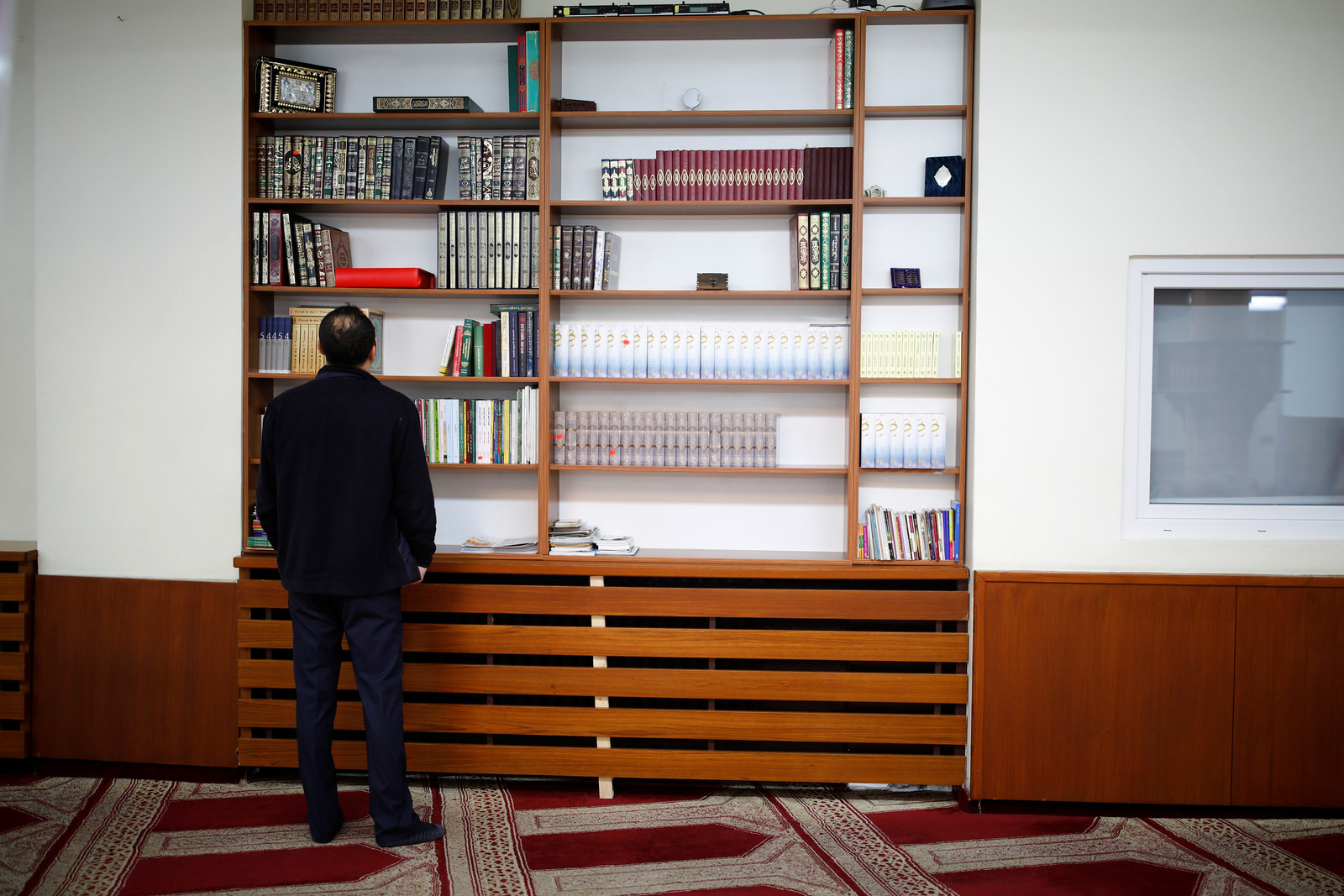
さらにやっかいなことに、因果応報は「自分」に向かうことがある。
「〜〜をしなかった私が悪かったんじゃないか」「あのときこうしていれば……」
悪い結果になった理由があるはずだ、という考えに基づき、頭の中でストーリーが組み立てられる。本当のことは誰にもわからないのに、「自分が悪い」というストーリーはつながっていく。
著者は、べき論によって「ストーリーに人間が苦しめられる」という。
ストーリーに追い詰められる人生は、ちょっと生きづらい。
では、どうしたらいいのか。
私の言葉でまとめると、大事なのは、そのストーリーも所詮、自分が作ったものに過ぎない、と発想を切り替えることだ。
「人は物語る動物」。つまり、自分がストーリーをつくっている。
因果応報論に陥りやすいと、思考の癖を自覚すれば、誰かを責めてスッキリするというストーリーに「ちょっと待てよ」と留保することができる。
生きていれば、時として説明のつかない理不尽なことは起こる。
そこで、安易なストーリーで「わかった気」になったり、「自分が悪い」というストーリー以外の道もあると思えること。これが重要だ。
人生に期待しない、という選択
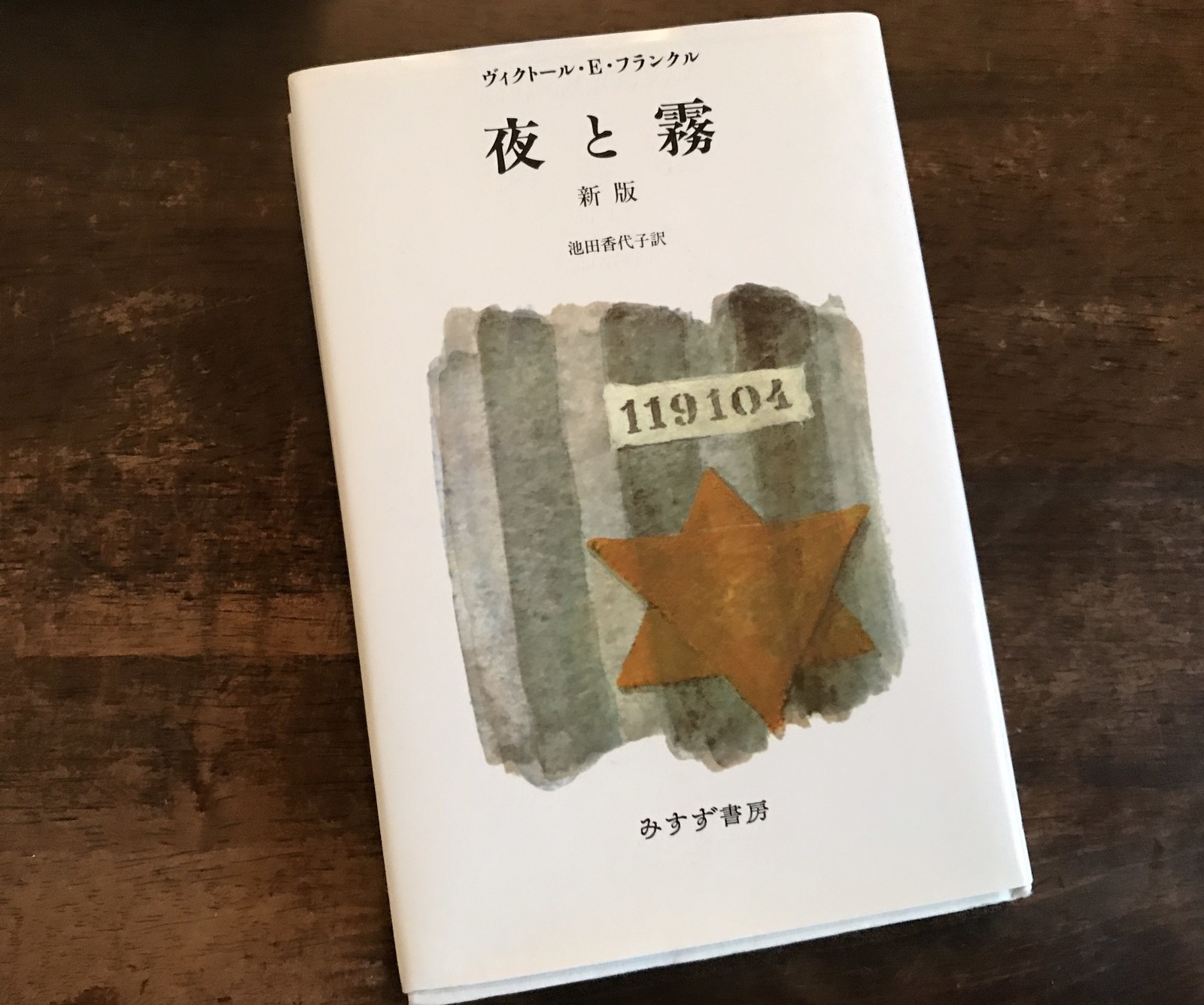
著者が、精神科医ヴィクトル・E・フランクルの名著『夜と霧』を論じる箇所が参考になる。
フランクルはナチスの強制収容所で、2人の被収容者が自殺願望を語ったときの体験を綴る。
2人は人生に絶望し、生きていることになんの期待も持てないという。自分の人生でなにか起きるかもと期待していたからだ。
収容所という彼らの身にふりかかった現実は、絶望のストーリーしか生み出さない。
ここでフランクルは、2人にとって必要なのは「人生についての問いを180度変える」ことだった、と書いている。
つまり、人生に期待するのではなく「わたしたち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ」
フランクルは続ける。
生きることは日々、問いかけてくるではないか。その問いに言葉を弄するのではなく「行動によって、適切な態度によって」正しい答えを出していくのだ、と。
やがて、2人は「未来に彼らを待っているなにかがある」ことに気づく。
一人は外国で待っている自分の子供を思い出し、もう一人はある本を完成させるという仕事があることを思い出す。
彼らは、人生のストーリーを「漠然と人生に期待して絶望する」というものから、待っている仕事や子供という、なにかのために生きるというストーリーに変えることで、自殺を思いとどまった。
思えば、人生への「期待」はしばしば人を追い詰める。
誰かに、自分に期待にもとづくストーリーを押し付ける。そして、自分の人生に期待したものが手に入らないと嘆き、「誰かが悪い…」「自分が悪い…」というストーリーにつなげていく。
人は物語る動物だからこそ、勝手に他人に期待しては失望するという人生から降りるというストーリーをつくることもできる。
なんか生きづらいな、と思ったときに自分のストーリーを見直してみたらどうなるか。楽しく生きる方向にストーリーの力をつかえると、少し気楽になるかもしれない。
この本の射程は、狭い意味での物語論にとどまらない。「物語」で、無駄に苦しまずにすむためのヒントをぎゅっと詰め込んだーーそんな一冊である。
サムネイルはアントニオ・ベラルディのコレクションより(AFP=時事)
バズフィード・ジャパン ニュース記者
Satoru Ishidoに連絡する メールアドレス:Satoru.Ishido@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.
