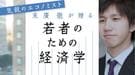関ヶ原の戦い、「本当の勝者」は誰だったのか
教科書が教えない「徳川家康」以外の人物は?
関ヶ原古戦場には、馬防柵や陣旗などが再現されている(画像:PJ / PIXTA)
「関ヶ原の戦い」の勝者は、言うまでもなく徳川家康だ。
そして、彼の指揮の下、合戦の勝利に貢献したいわゆる「東軍」所属の大名たちは、その後の江戸幕府の政権下で原則として重用され、逆に敗者の「西軍」大名は「外様(とざま)」として蔑まれる。
しかし、こうした風潮の中で、勝者である「東軍」に匹敵、またはそれをしのぐ「真の勝利」を手にした西軍大名も存在した。
「日本史を学び直すための最良の書」として、作家の佐藤優氏の座右の書である「伝説の学習参考書」が、全面改訂を経て『いっきに学び直す日本史 古代・中世・近世 教養編』『いっきに学び直す日本史 近代・現代 実用編』として生まれ変わり、現在、累計20万部のベストセラーになっている。
本記事では、同書の監修を担当し、東邦大学付属東邦中高等学校で長年教鞭をとってきた歴史家の山岸良二氏が、「関ヶ原、真の勝者」を解説する。
敗者、毛利家が抱えるフラストレーション
江戸時代の某年正月――。
新たな年を迎え祝賀ムードに包まれる長門国萩城(山口県萩市)の本丸御殿で、整然と居並ぶ家臣たちを前に、ひとりの家老が藩主に問いかけました。
「殿、徳川を討つ準備が整いました。いかがいたしますか」
一同に緊張が走る中、藩主はこう答えます。「いや、まだ時期尚早である」と。
これは、長州藩(山口県)における恒例となった年頭行事の一幕で、「関ヶ原の戦い」で敗北し、それまでの所領を大きく減封された毛利家は、その屈辱を決して忘れることがなかったというエピソードとして広く知られる俗説のひとつです。
「関ヶ原の戦い」では、敗北した西軍大名の大半が「改易(領地没収)」「減封(石高減少)」といった憂き目に遭う一方で、勝者となった東軍大名もその後の江戸幕府の下で、必ずしも「十分な待遇と安泰」を約束されたわけではありませんでした。
では、この戦いでの「最終的な真の勝者」はいったい誰だったのか。
少し見方を変えれば、実際の表面上の勝敗とは別に、あの「意外な大名」が浮かび上がります。
今回は、「関ヶ原の戦い」をテーマに、東軍のリーダー徳川家康をもしのぐ「本当の勝者」について解説します。
トピックボードAD