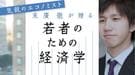東大が「東京六大学野球」で戦い続ける意味
9日に開幕、連続最下位から抜け出せるか
「ノーアウト一塁。エンドラン行きます」。8月のある日。東京都文京区の東大本郷キャンパス内にある東大球場では、東大野球部が打撃練習をしていた。フリー打撃のように見えるが、一味違う。打撃用のケージに入る打者が自分で状況や作戦を想定し、それを宣言してから打つという実戦的な練習だ。打者が打つと、強いゴロが遊撃手の右へ転がった。「それじゃあダブルプレーになるよ!」。まわりの選手たちから厳しい声が飛んだ。
夏の甲子園は花咲徳栄高校(埼玉)の優勝で幕を閉じ、大学野球のシーズンが到来した。東大が所属する東京六大学リーグは、9月9日に開幕する。東大は今春、10戦全敗した。昨秋のリーグ戦から数えて14連敗中。1998年春から39季、最下位が続いている。
東大が六大学リーグ加盟時に誓った「2つの約束」
東大は2010年秋の早大2回戦から2015年春の立大2回戦まで94連敗を喫し、東京六大学リーグワーストの連敗記録を更新し続けていた。2015年春の法大1回戦に6対4で勝って連敗を止めるまでの間、周囲からは「なぜ東大が東京六大学にいるのか」「東大は脱退すべきではないか」という声が上がっていた。
しかし、東大は東京六大学リーグにとって必要な存在である。歴史的な背景を知れば、それが納得できるはずだ。
まず、東大は日本野球の先駆者であるという前提がある。日本に野球が伝えられたのは1872年。アメリカ人教師ホーレス・ウィルソン氏が、東大の前身の一つである第一大学区第一番中学(現在の東京都千代田区)の校庭で、授業のかたわら生徒たちに教えたのが始まりとされている。こうして野球が伝わった先の一つである旧制一高(現在の東大教養学部)は1880年代から1890年代初頭まで日本野球界をリードする強豪であった。
2つめは、東京六大学野球連盟が発足する経緯だ。リーグの原点は1903年に初めておこなわれた早慶戦だ。その後、1914年に早慶明による三大学リーグが誕生。1917年に法大、1921年に立大が加わり、五大学連盟となった。そこに一高の野球を受け継ぐ東大が加わることが日本の野球のためにもリーグの人気のためにもなるという機運が高まり、1925年春に五大学の運営会議が東大の加盟を承認。同年秋から六大学によるリーグ戦が始まった。
リーグに加盟する際、当時の東大野球部長・長与又郎は部員たちに「絶対に自ら連盟を脱退すると言わないこと」と「一度は優勝すること」と激励。部員たちがそれを約束したと伝えられている。
3つめは、天皇杯に関すること。1競技1つという原則がある天皇杯が、硬式野球では東京六大学リーグという一連盟の優勝校に下賜されている。プロ野球の日本シリーズを制したチームでも、社会人の日本選手権や大学選手権で優勝したチームでもない。この重大な事実に、東大が大きく貢献したのだ。