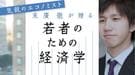「成長できる」「成長できない」企業の大きな差
失墜する名門とは明確に違う5つの共通点
かつては日本を代表していた有名・名門企業が本業の不振や不祥事の発覚などによって、経営が立ちゆかなくなるケースが出ています。これらの企業は過去の栄光を忘れられず、激変する時代の波に乗り切れなかったことが原因なのでしょう。
拙著『好調を続ける企業の経営者はいま、何を考えているのか?』でも解説していますが、こうした激変の時代にあっても、瞠目(どうもく)するほどの躍進を遂げている企業があります。私はこうした企業やその経営者には5つの共通点があると考えています。
激変の時代にあっても成長する企業の共通点
(1)自社に都合の悪いトレンドも逆に利用
難しい時代に舵を取る経営者の資質として、社会の変化を素早く察知し、その変化を味方につける能力が挙げられます。成功報酬型のネット広告に先鞭をつけ、創業以来15年連続で増収を続けているファンコミュニケーションズが、そのうちの1社です。
柳澤安慶社長は、このように語ります。
「特殊なポジションを取るだけで商売がうまくいく、たとえば、エライ人と知り合いだったりすると、それだけでうまくいくことがあります。そういう閉塞した、市場化の遅れている場所にいた企業、そこでうまくいっていた企業が、インターネットによってあらゆるものが次々と市場化されていく中で、時代のトレンドに対応しきれなくなっている。それが現代です」
どんなに優秀な企業でも、自社に都合の悪いトレンドは、いつかどこかで発生します。他社の提供するサービスが好評で、自社に都合の悪いトレンドを作り出していることが往々にしてあります。
わかりやすい例でいうと、紙媒体の広告枠で圧倒的な強さを誇った企業にとって、インターネットの普及は脅威であり、PCでのネット広告に強みを確保した企業には、スマホの普及は脅威なのです。
自社に不都合なトレンドは必ずいつか発生します。その逆風をプラスに転化する挑戦の意志を持ち、目をつぶるのではなく、逆に行動すること。これは成長を継続する企業の強さの源泉といえそうです。