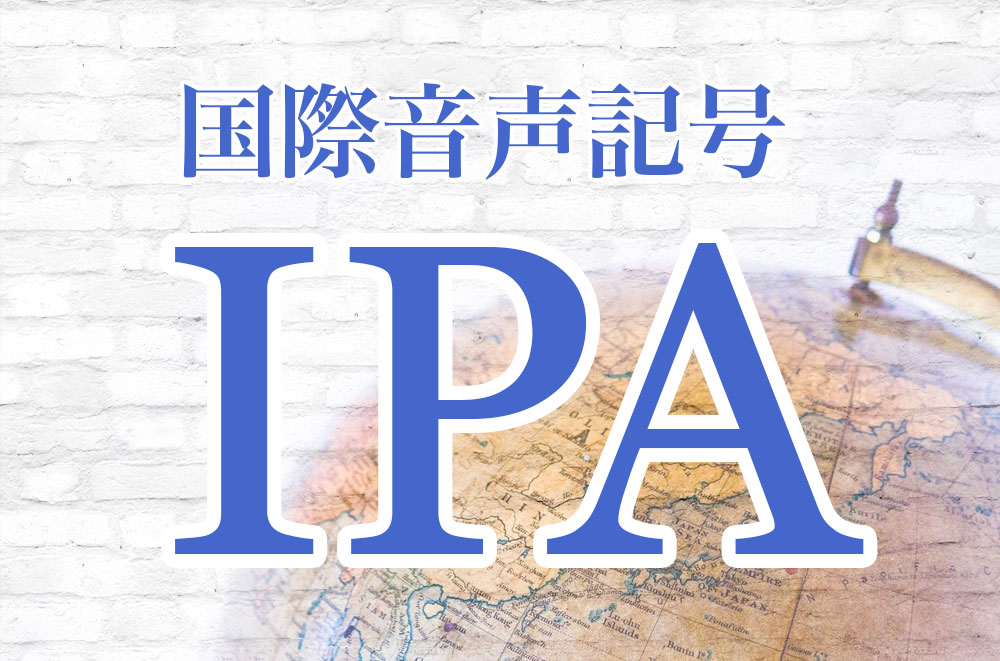こんにちは、アメリカ在住ライターのタカコです。
今年(2017年)の5月以降、日本の名古屋や神戸などの港湾地域を中心に、ヒアリが発見されたというニュースを何度か目にしました。
私の住んでいるテキサス州にも、ふつうにヒアリが生息しています。
ニュースで聞いた方も多いと思いますが、このアリ、本当に怖いんです。
【動画】東京・大井ふ頭で5例目が確認された #ヒアリ
— NHK「クローズアップ現代+」公式 (@nhk_kurogen) July 7, 2017
ヒアリを見つけたら?刺されたら?https://t.co/F8AKBYt0I8 pic.twitter.com/XbbrIBvEef
今回は、このヒアリの怖さについて書いてみようと思います。
ヒアリとは?
では「ヒアリ」についてまとめます。
ヒアリは英語で「fire ant」
このヒアリですが、漢字では「火蟻」と書き、英語では「fire ant(ファイア・アント)」といいます。
以前、「かかし(scarecrow)」は、一度聞くと忘れない単語だと記事にしましたが、この「fire ant」もその仲間と言えます。
fire(火)+ ant(蟻)= fire ant(火蟻)ですから!
ヒアリは南米原産
ヒアリは南米原産のアリで、日本で見つかったのは海外からの貨物に混じって侵入してきたのが原因だと言われています。
とても攻撃的で、繁殖力が高いことが特徴です。
夫の話によると、ここアメリカでも、やはり南米からの貨物に混じってやってきたのが始まりだそうです。
毒を持つ恐ろしいヒアリ
日本人の感覚からすると、「たかがアリでしょ?」と思うかもしれません。
実は、私も渡米してきたばかりのころ、そう思っていました。
でも、このヒアリ、本当に怖いんです!!
なぜこのヒアリを甘く見るべきではないのかというと、猛毒を持つアリだからです。
「世界の侵略的外来種ワースト100選定種」という悪名を持つほどです。
それもそもはず、「ヒアリ」の名前の由来である「火(fire)」ですが、刺されると火傷のような激しい痛みがあるからです。
さらにひどいことに、人によってはアナフィラキシーショックを起こし死ぬこともあります。
ヒアリの生息場所
そんなヒアリですが、私の住んでいるあたりでは、寒い冬以外はごく普通にいます。
そう……ごくフツーに。アメリカ原産のものじゃないのに、フツーにいるんですよ……
ヒアリがよくいる場所は……
- 家の庭
- 公園
- 町なかの植え込み
- 歩道のわき
などです。
「ヒアリ(fire ant)」は、とても繁殖力の高いアリですが、このアリの猛威に、ここ原産の動物たちが太刀打ちできていないとも言えます。
【動画】ヒアリの巣
巣を踏んだりして傷つけてしまうと、無数の働きアリが一斉に出てきて、あっという間に足に這い上がってきて攻撃します。
先ほども書きましたが、「ヒアリ」には、毒を持った針があり、その針で刺してきます。
これは私の録った動画ですが、本当にすごい量のアリが一斉に巣から出てくるのがわかるかと思います。
もちろん、周りの人に襲いかかるといけないので、誰もいないときに突いています。
この動画のアリ塚は、前日に雨が少し降ったため、巣の盛り土がかたくなっています。できたばかりの巣の土はもっとパラパラです。
知らずに巣を踏んでいて、気づくとひざ下が這い上がってきたアリで真っ黒になっていた、という話も聞くくらいです。
そんなアリが一斉に攻撃するんです。
1匹や2匹に刺されるならまだしも、無数のアリに刺される可能性もあります。
ヒアリ対策まとめ
このヒアリの対策ですが、どうすれば良いのでしょうか?
まずは普通のアリとの違いを知って、見分けたいものです。
ですが、正直なところ、ふつうのアリと見分けるのは厳しいと思います。やや赤っぽい色なのですが、なにせ小さいですので……。
では、アメリカに住む私が見分けられなくてもできる「ヒアリ対策」をまとめてみます。
ヒアリの巣には絶対近づかない
こちらは公園の芝生で見つけた、「fire ant」こと「ヒアリ」の巣の写真です。
「見つけた」と書きましたが、べつに全然珍しくありません(笑)。
アリの「巣」は、英語で「nest」と言います。鳥や蜂の「巣」も同じですね。
こんな風に、巣のあるところには、土がこんもり盛っています。「アリ塚」です。
「アリ塚」は、英語で「mound」と言います。
サラサラではなく、少しパラパラしたような土です。
緑の芝生にこんもり盛られた土。こんなのを見ると、つい踏んづけたくなりませんか?
でも……
そんなことをしては絶対ダメです。絶対!!
こんな感じで、わりとわかりやすい感じなので、とにかく近寄らないことです!
草に隠れていることもある
上の写真のようなものなら「巣があるな」とすぐにわかりますが、芝生が伸びていたりすると隠れていて見逃すこともあります。
……そうなると、知らないうちに誤って踏んでしまって……という大変なことが起きることも。
もしアリ塚が見えなくても、「草の中にはあるかもしれない」ということを常に考えています。
ヒアリに刺されないように長靴を履く
ヒアリ対処法として、わが家では娘が庭で遊ぶときには、必ず長靴をはかせています。
私や夫でも、少し長くいる場合は、長靴をはくことも多いです。
また、巣ができていないかの見回りも欠かせません。
ヒアリ専用の殺虫剤
公園や町なかで見つけたら、近寄らないのが一番ですが、自分の家の庭ではそういうわけにはいきません。
お店では、ヒアリ専用の殺虫剤が何種類も売られています。
わが家には小さい子どもがいるので、できたら薬剤はまきたくありません。
でも、子どもが興味本位で触ったり、誤って踏んだりして刺されてしまうことを考えると、やむを得ず薬の力に頼っているのが現状です。
女王アリを退治しないと解決しない
もし、殺虫剤がうまくいっているように見えても、巣の奥にいる女王アリを退治しないことには、またどんどん繁殖してしまうんです。
私も何度か試していますが、なかなか退治することは難しいです。
一度は全滅したかに見えても、何日かすると薬をまいた巣の横に新しい巣ができていたりします。
もしものときのために「ポイズンリムーバー」
あと、我が家ではもしも刺されたときのために、ポイズンリムーバー(poison remover)というものを買い置きしています。
運良くまだ使ったことはありませんが、刺されたときにはこれで毒を「吸い出す」ことで病院に行くまでの応急処置ができます。
アマゾンでも購入できるようですので、あらかじめ持っておくと安心感があります。
これからも一生使うことがありませんように……。
「ヒアリがいるかも?」と意識する
こうやってまとめてみましたが、最も大切なのは注意を怠らないことです。
「もしかしたらヒアリがいるかも?」と意識しているだけで、刺される可能性はグーンと減ります。
日本ではまだその意識がないので、もしヒアリが繁殖しはじめたら気をつける必要がありますよね……。
実際のところ、私は渡米してきて以来、ずっと気をつけているので一度も刺されたことはありません。
刺された方の話では、大人でもつらい痛みだと聞きます。
この場で体験談を披露できず、すみません……。かといって、披露するために刺されようとも思いません。そんな勇気は全くないです(笑)。
刺されてはいませんが、常に「刺されたらどうしよう」とビクビクしていますし、土のある場所では、巣がないかきょろきょろ足元を見ながら歩いています。
小さい子どもがいると、もっともっと気をつけないといけません!
こんな強いアリが、日本に上陸しようとしているんですよ!! なんとか阻止してほしいです!
日本でもいつかこんな風に注意して暮らさないといけないかもしれないと思うと、とても残念ですし、心が痛みます。
海外への渡航が簡単になり、海外から物がどんどん入ってきている世の中です。
それに伴って、もともと日本には全くなかった虫や病気が入ってきてしまうことを防ぐことは、もはや難しいのかもしれませんね。「セアカゴケグモ」のように。
さて、「fire ant」は「ヒアリ」ですが、「firefly」ってなんでしょうか? 気になる方はこちらもどうぞ!