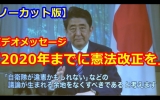政治主導は正義だがルールと透明化が必要(特別寄稿)

首相官邸サイト:編集部
官僚は不法な政治介入に屈すべきでないし、シンクタンク的に多様な選択肢を発信することも期待されている。しかし、それと同時に政治の意思の機能的な執行者であることも期待されている。
このふたつの矛盾しがちな要請をどのようにバランス良く実現していくかは、古今東西の官僚機構にとって頭の痛い難問であり続けてきた。
加計問題は、中曽根政権あたりから始まり、民主党政権下でやや幼稚なかたちで進展した政治主導が、菅官房長官を頂点としたリーダーシップで強い力を発揮しているなかで、あきれ果てた岩盤規制を守り続ける一方、無邪気に法を無視して天下りの斡旋をしていた文部科学省の事務次官が更迭されたことに端を発した。
前川喜平氏は、大富豪であり、数千万円の退職金は既にもらっているし、息子は医師であるとなれば、政権に睨まれて困窮する小市民的な心配もない。しかも、中曽根弘文氏の義兄という背景もあれば、永田町の政治ゲームのなかで味方を見つけるのも容易な立場だった。
私は、加計学園の問題で、政治の意向が過度に発揮されたとは思わない。志願者も多い獣医学部を新しい発想で創ってもいいのではなかということも、地方振興や業界の抵抗の少なさを考えて四国はどうかというのについて、他の要素にも目配りしながら方向性を示していくとか、出来るだけ急げということも政治家として当たり前のことだ。
その過程で、獣医業界側の要望を呈して民進党でも玉木代議士や自民党でも麻生太郎副総理に近い人々が動いていたし、加計学園にはむしろ地元で民進党の江田五月氏などのほうが直接的な関係をもっていたが、それだって、悪いこととは思わない。
また、政治家の意向を忖度して強い意向を誰が持っているというのも役所のなかで誇張して書くこともよくあることだ。正々堂々とそういえばいいのに、文書があるとかないとか、公文書かどうかとかいう議論に巻き込まれてつまらん反論をしたのが、大失敗なのである。
フランスにおける政治主導と官僚機構
しかし、この問題を離れていえば、政治主導、官邸主導は必要なことだが、その一方で、ルール作りをし、透明性を確保しないと、行政の中立性を害するとか官僚を萎縮させるとかいう弊害も心配だ。
すでに書いたように、安倍内閣はここ30年くらい叫び続けられてきた政治主導を名実ともに実現しつつある。そうなると、今回の加計問題は、あまりにもいじましい復讐劇でしかないので、一緒にされたくないとはいえ、このまま政治主導がなんのしばりもなく暴走することに危惧をいだく霞ヶ関の住人やOBも少なくないのである。
私自身にとって、この問題は、40年近く前からの関心事である。1980~1982年にオランド前大統領やマクロン新大統領の母校であるフランス国立行政学院(ENA)に留学してフランスにおける政治主導が行政の活力を奪うことなくどう実現されているかを、「フランス式エリート育成法」(中公新書)という著書や論文などで紹介して以来、ことあるごとに紹介し日本にどう導入するかを論じてきた。
しかし、デカルト的な明晰さは日本人の好むところでなかったのか、日本における政治主導はあいまいな形で進み、その矛盾が今回の事件にいびつな形で表出したのだと思う。
官僚人事と政治主導
官僚の人事を仲間内の順送り人事から政治の意向も加味していこうとしているなかで、 公務員の中立性を保ちちつつ政治の意向も適正に反映させるバランスが取れたシステムが確立されるべきだ。
官僚機構は、民間企業と違って代替するほかの組織を持たない存在である。そのときの政権の意向を反映するだけでなく、将来の別の政権のもとでも機能しなくてはならないし、その経験を活かして多様な選択肢を提供できるシンクタンクでもある。
一方、その時々の政権の政治的意思をもっとも迅速に実現していくマシーンでることも要請されている。
そのふたつの要請を両立するために、日本と並ぶ官僚国家であるフランスでは、いくつかの工夫をしているし、私はこうしたシステムの導入をENA留学から帰った1982年から主張し続けている。
たとえば、フランスには事務次官は存在しない。アメリカなどでも次官はいるが、次官補などに対して序列で一位だというだけだ。中国の官僚機構でもそうだ。日本のように、大臣が会長であるのに対して社長だというような事務次官は普通ない。人事などは総務局長が担当だ。
フランスでは、大臣の手足になるのは、大臣官房だ。いわば補佐官室で、官房長は首席補佐官というべき存在で、大臣の代理人だ。政治任命なので、経歴は問わないが、普通は官僚出身者だ。その省の官僚が多いが、他省庁からも来る。とくに、フランスではマクロンのような財政監察院、フィリップ首相のような国務院、オランド前大統領のような会計検査院というグランコールと呼ばれる三つの組織の人間がスーパー・キャリア官僚となっており、官房長の供給減だ。
そして、官房のメンバーは10人くらいからなるが、だいたい、官僚が半分強といったところか。
局長などは、大臣が官房長の補佐を受けて任命するが、大統領や首相の助言もされる。実務能力がないと困るのは大臣なので、それほど極端な政治任命はされない。
野党や大臣の政敵に近い幹部はどうするかといえば、中枢から離れたポストに待避する。それが省内ということもあるし、外郭団体のこともある。ただし、降格や肩たたきで辞職を強いられることはない。
このようなシステムのお陰で、野党のブレーンとなっている官僚も多いし、それが、円滑な政権交代を可能にしている。このような官房(補佐官)システムは地方自治体にあっても適用可能だと思う。
評価や基準は客観的にしたうえで堂々と政治判断を
もうひとつの問題は、政策決定にあたって、定められた基準に従い客観的に決定が行われてるという無理なフイクションを立てながら、実態は、 善悪はいろいろだが政治的、社会的配慮で決定が行われていることだ。
基準や分析結果の数字の方を結論ありきで操作するという惡弊になっているのである。加計でも、実際には政治的に方向付けがされながら、後付け的に選考基準がされた印象がある。
私は、政治的な意思を反映したら、 それと分かるように示して国民に対して責任を持つのが好ましいと思う。
東京都の豊洲問題でも、移転に賛成派も反対派も、自分で出したい結論に合わせて効果を試算したり、基準を設定していた。そのあげくが、超政治的に豊洲も築地も両方という驚天動地の選挙ファーストの結論になってしまった。
そんなことやめて、経済効果はこういう順序だ。しかし、こういうことも大事だと思うので、こういう結論を出した。これを議会でも議論して欲しいし都民も広く議論して欲しいというのが、あるべき姿だと思う。
そうしていけば、小細工や苦し紛れの説明などせずに、客観的な評価はこうだが、あえて、こういう政治判断を行ったとして、正々堂々と政治判断の是非は選挙での有権者での投票で問えばいいことになる。
安倍首相は、混乱をきたした原因を政治主導のあり方の未熟さにあると認め、行政の中立性ともバランスの取れた政治主導のあり方を確立することをもって、国民への提案とすることを提案したい。
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間